
学び続ける力 リカレントストーリーー歩みと成長を止めない東京理科大学におけるリカレント教育とは
目次
東京理科大学の紹介

東京理科大学は1881年に前身である『東京物理学講習所』が設立され、「実力主義」を貫いています。真に実力を身につけた学生のみを卒業させるという方針のもと、以下の特徴を持ちながら教育を行っています。
- 指定科目の単位取得を進級条件とする「関門制度」を採用
- 講義と演習を組み合わせたカリキュラムで基礎学力の養成を徹底
- 多くの実験を取り入れ、講義と連動させて学びの質を高める
高い研究力と就職率を誇る理工系総合大学として、日本における専門教育を牽引する大学の1つです。7つの学部を擁し、理学と工学を協働させた教育研究を行っています。
- 理学部第一部
- 理学部第二部
- 工学部
- 薬学部
- 創域理工学部
- 先進工学部
- 経営学部
「日本の理科大から世界の理科大へ」を目標に、積極的な国際化を進めており、85の大学など学術研究機関(31か国)と協定を結び、学生交流や教員交流、共同研究などを行っています。
研究室の数は410と理工系大学では最大規模の多様な研究環境を提供。THE世界大学ランキング2024では「研究力」の指標で、国内私大3位。修士授与数ランキング「理学分野」私大1位、「工学分野」私大2位。実就職率は94.4%と非常に高く、大規模大学(卒業生数4,000人以上)のランキングでは全国1位。
これらの特徴により、東京理科大学は「教育力」「研究力」「実就職率」において高く評価されています。
リカレント教育とは
リカレント教育は「生涯にわたって学び続ける」という概念で、以下のような目的があります。
- 個人においてのキャリアアップやキャリアチェンジ
- 企業の競争力向上
- 社会参加の促進(特に女性や中高年層の再就職支援)
似たような言葉に「リスキリング」がありますが、リスキリングは、「職業能力の再開発、再教育」が目的で、主に「DXや第4次産業革命といった社会の変化に対応するための知識や技術を学び直すこと」を指します。
東京理科大学では大学創立当初から現在も夜間学部を開設しており、社会人に学びの機会を提供する数少ない教育機関です。2001年に一般教養講座を主体とした「生涯学習センター」の設置を機に、同センターを発展的に改組した”社会人教育・リカレント教育の拠点”として、2018年に「東京理科大学社会人教育センター」のもとに「東京理科大学オープンカレッジ」を設立した東京理科大学。
今回は経営企画部の小原正之次長に、東京理科大学オープンカレッジにおけるリカレント教育についてお話を伺いました。
社会人に向けたビジネス講座の先駆者でもある東京理科大学。講座数も日本最大!

ー貴学にはリカレント教育のための学びを深められる講座が豊富ですが、力を入れるようになったきっかけを教えてください。
小原経営企画部次長(以下、小原次長):もともと大学の成り立ちが夜間学部メインということもあり、以前から多くの社会人が学んでいます。
現在も夜間学部のほか、社会人を対象とした夜間コースや、MOT(Management of Technology)という社会人向けの専門職大学院など多くの正規課程で社会人が学べる環境を整えています。
東京理科大学オープンカレッジはリカレント教育機関として、社会人のためのビジネス講座を年間200講座展開しておりますが、これほどの講座数を提供する大学は他にありません。
リカレント教育のような誰もが受けられるオープンな形のビジネス講座の提供は、日本で圧倒的な規模であると認識しています。
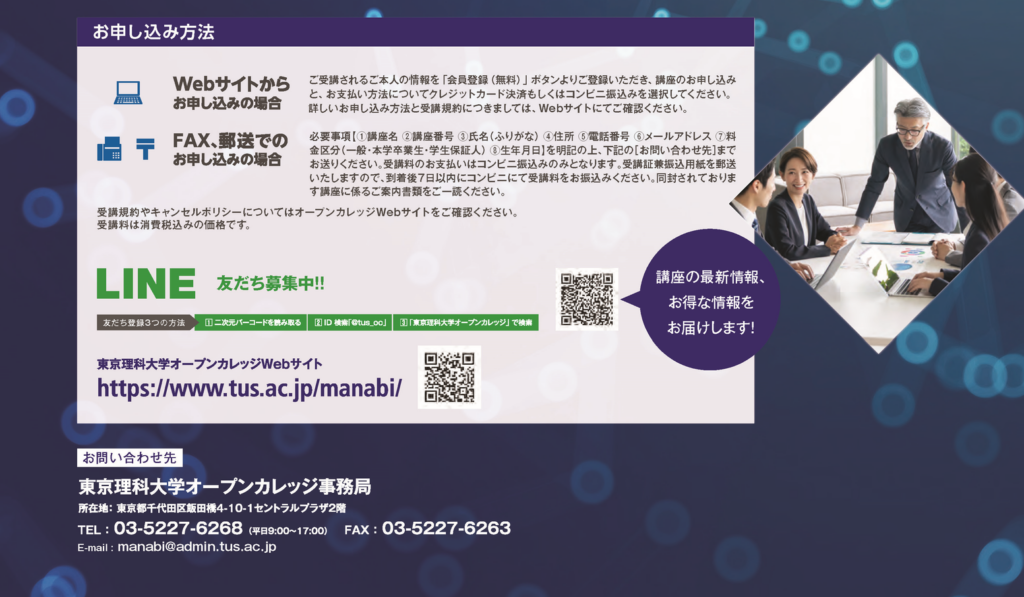
自律的な学びを後押し!大学という教育機関だからこそ提供できる「寛容な学び舎」の提供
ー貴学でのリカレント教育のコンセプトや思いというのは、どのようなものがありますか。
小原次長:本学で今非常に強く感じているのは「自律的な学びを促進したい」という思いです。昔も今も社会人での学びは、会社や社外での研修に参加するのが主流だと思いますが、これらは昇進や昇格試験に絡んでいることが多く自発的な学びとは異なります。どちらかといえば、受け身のものではないでしょうか。
しかし、本来「大学で学ぶ」ということは、もう少し寛容なものだと思います。自由な発言や失敗しても許されるという場であると思っています。カルチャーセンターとも研修会社とも違う「大学らしい学び」があってもいいのではと思うのです。
このような考えからも本学では学びやすい環境を整えることによって、自律的で自発的な学びを後押ししたいと考えています。
多彩なキャリアを持つ講師による”本当に”知って欲しい講座を追求

小原次長:さまざまな経歴やキャリアを持つ方たちに講師をお願いしています。学内だけでなく学外でのありとあらゆるリソースを活用し、講座の企画から協力いただいています。
役員や管理職向けの講座であれば、さまざまなテーマを高名な方や視座の高い方から学べる講座を展開したり、社会の数字を読めるようになるために、国や銀行に関わる方にマクロ経済の講座を開いてもらったりなど、普段なかなか接しない方による講座を開講しています。
”社会人の方たちに本当に知ってほしいものはなんだろう”という視点で企画しているので、研修会社では扱いにくいテーマや、本学教員によるアカデミックな講座、実務家の方から学べるものなど多彩でバランスの良い講座を提供できるよう心掛けています。
ー貴学だからこそ学べるといった何か特徴的な講座はありますか?
小原次長:以前ある企業の方から「私は矛盾の中で生きているので、とても生きにくいです」というお話をうかがいました。この方は人事に携わる方でしたが「働き方改革と言われている中、仕事は増えているのに残業を減らすようにと会社から言われ、日々の矛盾の中で生きなくてはいけないのはとても苦しい」と聞き、本学で「このような悩みを解決できる人はいないだろうか」という話になりました。このような経緯があり企画したのが「諦めない、決めつけない!矛盾を共存させる謎解きと戦略」講座です。さらに、働きやすい職場づくりをサポートするために、「社内のエンゲージメントを高める講座」、「DXや自動化の事例紹介を通じて社内展開のヒントを学ぶ講座」、「ビッグデータを活用し、新たなビジネスモデルを学ぶ講座」なども企画しました。これらの講座を通じて、企業の皆様が抱える矛盾に向き合い、長期的な成長を実現するための機会を提供しています。
また、ユニークな講座として「“学び”の学びについて」という講座もあります。この講座は学び方を忘れがちな社会人の方に「学び方とは何か?」を考えてもらい、新たに学び始めるきっかけを提供することを目的としています。
この講座には明確な答えはありません。「自分自身の学びを見つめなおすこと」をテーマとしており、一般的な研修のように一つのストーリーを追って最後に納得するものではありません。参加者同士が「学び」について議論を重ね、最終的に答えが出ずモヤモヤとした感覚を残す内容が特徴的です。
このように大学だからこそ学べる、ありとあらゆる分野の先生方や企業の方をお招きして学びを提供しているのが本学の講座の特徴です。
オンデマンド配信がないからこそ自由に発言できる
ー講座の様子を教えてください。
小原次長:本学は「寛容な学び舎」として他にはない学びの場を提供しています。通常、研修や講座の受講となると自分の恥ずかしい経験は話さずに、ビジネス書に書いてあるようなセオリーを話すことが多いと思います。
しかし、本学のビジネス講座はそのような硬い感じではなく、それぞれ自由に発言して自分の失敗談や会社での失敗例なども自由に話せる「寛容な学び舎」を提供したいのです。社会人における学びは成功例だけでなく、自由な発言や失敗例からの学びが多いと思っているからです。
そのため、本学では自由な発言を推進するために録音や録画等を一切せず、オンデマンド配信はしていません。こうすることで、安心して自由に発言できる環境を整えています。
このような「自由に発言できる振り幅のある講座」こそが本学の特色であり、他校にはない充実した学びを提供できる理由だと思います。
ー社会人向けのビジネス講座が約200講座ある中で、どれを受講しようか迷ってしまうこともあるかもしれません。「このように選んでみては?」というアドバイスをお聞かせください。
小原次長:まずはテーマやタイトルを読んで、直感的に「面白そう」と思ったものを入り口にしてもらうと良いのではと思っています。直感として感じたものを自主的に学ばないと学びには繋がらないと思うからです。
年間200講座という講座数には意味があります。このくらいの規模感がないと、個々人に刺さる講座が提供できません。当初は50講座ほどの講座数からスタートした本学ですが、この講座数でなければ、それぞれの「学んでみたいこと」に出会えません。
例えるなら、本学のビジネス講座は“フードフェス”のようなものです。多彩な講師がさまざまな視点から作り上げた講座の中から、受講者が気軽に「美味しそうな」講座を選べるように工夫しています。
また、1講座約4,000円~5,000円と手頃な価格で提供しているため、その時の旬や流行を反映した講座が展開されることもあります。この多様性や手軽さ、規模感が、課題解決や成長を支えるものになると自負しています。
リカレント教育のきっかけに相応しい東京理科大学

ーリカレント教育に対する発展的なコンセプトとともに、他大学と比較しても豊富な講座数を誇っていますが、何か課題はありますか。
小原次長:日本全体の課題として、リカレント教育やリスキリングの明確な定義がまだ定まっていないように感じます。また、大学がリカレント教育を提供しているという認知も広がっていないのが現状です。
そのため、リカレント教育を推進したい企業の方やリカレント教育に興味がある個人にとって、どこで情報を得られるのか分かりづらい状況にあるのではないでしょうか。
多くの方がリカレント教育の講座を探す際、まずは母校のホームページを確認するのが一般的です。しかし、多くの大学ではビジネス講座の提供が少なく、5〜10講座程度しかない場合も多く、そもそも講座を提供していない大学も少なくありません。母校のホームページで講座が見つからない場合、研修会社さんのホームページを確認する人も多いと思われます。
こうした状況において、本学が豊富な講座数を誇り、学びの場を提供していることが広く知られていないということに忸怩たる思いを感じます。
現在、本学の最大の課題は「認知を広げること」であり、今まさにこの課題が重要なフェーズに差し掛かっていると感じています。
今後の展望
ーリカレント教育への歩みを止めない貴学ですが、今後の展望について教えてください。
小原次長:現在の講座は、フードフェスで選べるアラカルトメニューのような形式ですが、体系的に学べる「コース料理」のような講座も必要ではないかと感じています。一昨年、100時間ほど学ぶプログラムを提供した際に非常に好評だったため、今年から既存の講座を繋げ、体系立てて学べるコース形式の講座にチャレンジしています。
もちろん、自主的な学びへの入口となる講座も重要ですが、「アラカルトだけでは物足りない、もっと深く学びたい」という方向けに、計10回ほどの講座を今年度から提供しています。現在の講座数を維持しつつ、このようなコース形式の講座も根付かせていきたいと考えています。
ー最後に、読者の皆さまへのメッセージをお願いします。
小原次長:「日本人は大人になると学ばなくなる」とよく言われます。そのため、「オープンな場だからこそ提供できる寛容な学びの場」が、私たちのキーワードです。
気軽に学んでみたものの、「今すぐ役に立たない」「急に人生が豊かになるわけではない」と感じることもあるかもしれません。しかし、後々になって花開く学びや教養もきっとあるはずです。
現在、多くのことは本や動画配信で学べますが、物事を俯瞰してみるために必要な知識や深い教養は、何かと掛け合わせたり、自分自身の経験と重ね合わせたりすることで深まります。東京理科大学のオープンカレッジは、そうした学びの場を提供しています。文字だけでは伝わらない生の声や話、旬のトレンドこそ、後に役立つ貴重なものです。
東京理科大学オープンカレッジでは、「学ぶこと自体が面白い」と感じていただける講座が豊富に揃っています。大学ならではの環境で、失敗を恐れず挑戦できる寛容な学びの場を提供しています。皆様のご参加を心よりお待ちしています。
