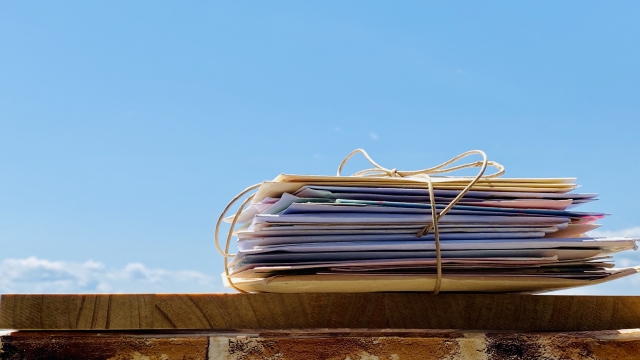
引っ越しするなら郵便局へ転居届を!転送サービスの手続き方法を解説
引っ越しに関連する手続きは本当にたくさんあり、大変ですよね。
住所変更などの手続きも多数あるため、手続きが遅れると、旧宅に郵便物が届いてしまうかもしれません。
そんなトラブルを避けるためにも、ぜひ郵便局の「転送サービス」を活用してください。このサービスを利用すると、手違いで旧宅に配送された郵便物を、新居まで配達してくれるのです。大切な郵便物を確実に受け取るためにも、必ず申し込みをしておきましょう。
今回の記事では、便利な転送サービスについて詳しく紹介します!
▼引っ越しやるやることリスト(PDF)はこちらでダウンロードできます 引っ越しやることリスト!荷造りから役所の手続きなど準備から引っ越し後までを時系列で解説!
目次
引っ越ししたら郵便局に転居届を!転送サービスでできること
郵便局の「転送サービス」とは、引っ越し後に旧宅あてに送付された郵便物を、登録した新居へ転送してもらえるサービスです。引っ越しの際には、各所に住所変更の手続きが必要になりますが、うっかり忘れてしまうこともあるでしょう。
郵便局へ転居届を提出すると、郵便物の転送をしてもらうことができます。住所変更の手続きを忘れていて、旧宅へ配送された郵便物を、新居まで転送してくれるサービスです。
「必要な書類はすべて住所変更したから、あとはいらない。転送してもらわなくてよい」と、考える方は少なくありません。しかし、いらない郵便物であっても、誤配されれば旧宅へ住まわれる住民の方への迷惑となりますし、個人情報漏洩を防ぐためにも、転居届は必ずしておきたいサービスです。
便利なだけでなく、誤配によるトラブルも防げますので、引っ越しの際には必ず手続きをしておきましょう。
▼マイナンバーカードの住所変更手続きについては、こちらがおすすめ!
引っ越したらマイナンバーカードの住所変更手続きを!流れや注意点を解説郵便物の転送手続きでできること
役所で転出届や転入届をするだけでは、郵便物は新居へ配送されません。旧宅あての郵便物については、そのまま旧宅へ配送され、放置されてしまうか、差出人へ宛先不明として返還されてしまいます。
このような事態を防ぐためにも、郵便局の転送サービスを活用してください。サービスの料金は無料で、転送にかかる追加費用も不要です。このサービスを申し込むと、郵便局で取扱う手紙やはがき等が、新居へ転送されます。
<転送される郵便物の種類>
- 手紙
- はがき
- ゆうパック
- レターパック
- クリックポスト
- ゆうパケット
- スマートレター
- レタックス
- 第三種郵便物
- 第四種郵便物
- 国際郵便
ただし、これらの郵便物でも「転送不要・転送不可」と明記された郵便物は除外されます。転送されず、差出人のもとへ返送されることになります。
また、郵便局以外の業者が配送している手紙(ヤマトのメール便など)は、業者が異なりますので転送されません。
申し込みから転送が開始されるまでの日数
転送が開始されるのは、届出をしてから約3日〜7日後となります。
特に引っ越しのシーズンには手続きが込み合うことが予想されます。引っ越しの前に余裕を持って手続きをすませておきましょう。
転送サービスを受けられる期間は、届出日から一年間となります。
転送手続きの状況は、「お客様控え」または「転居届受付番号」から確認できます。
転送サービスは世帯でなく個人で利用可能
転送サービスは、世帯ではなく個人での申し込みが可能です。
家族世帯で住んでいる方が、自分ひとりだけ進学・就職・転勤などで転居することになったとき、自分あての郵便物だけを転送してもらうことができるのです。
旧居に残る家族には、これまで通り郵便物が配送されますのでご安心ください。
転送サービスを受けられない郵便物に注意しよう
転送サービスで転送される郵便物は、前述したとおり、郵便局が取り扱う手紙やはがき、ゆうパックなどになります。
しかし、「転送不要・転送不可郵便」は例外です。これは、差出人が「受取人がこの住所に住んでいないときは返還してほしい」と意思表示しているものです。転送不要とされた郵便物は、新居へと転送されずに差出人へ返還されますので注意してください。
「転送不要」となる郵便物の例
国や地方自治体の機関、銀行からの郵送物、クレジットカード会社からの郵便物などは、「転送不要郵便」として指定して発送されることがあります。
これらの書類は、登録された住所へ正しく発送する必要のある重要なもので、転送届を提出していても、新居へ転送されず、差出人へ返還されます。
これらのトラブルを防ぐためには、住民票の転出・転入手続きを正しく行うことです。また、銀行やクレジットカード会社の住所変更手続きを早めにすませておきましょう。
その他の転送ができない郵便物の事例
自宅のポストに届いている手紙等は、すべて郵便局から発送されているわけではありません。
ヤマト運輸のネコポス・クロネコDM便や、佐川急便の飛脚メール便などがその一例です。これらのメール便は郵便局のサービスではなく、運送会社が異なるため、郵便局へ転送サービスを申し込んでも転送されません。
クロネコヤマトの転居転送サービスは、下記のホームページから手続き可能です。
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/redelivery/tenkyo/
佐川急便は、転送サービスを実施していません。
郵便転送サービスの申し込み方法は? 簡単にできる3つの方法
郵便転送サービスの申し込み方法は、「パソコン・スマホ」「郵便局窓口」「ポストへ投函」の3つの方法があります。
手続きは、24時間いつでも申し込みができるパソコン・スマホからがおすすめです。
詳しくみていきましょう。
パソコン・スマホ(e転居)で手続きする
パソコンまたはスマホで「e転居」にアクセスし、画面の指示どおりに必要事項を入力していきます。
e転居はこちら:https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/
ゆうびんIDの登録がまだの方は、新規登録をしてから手続きをしましょう。登録するときは、メールアドレス(携帯メールのアドレスは不可)が必要です。または、マイナンバーカードでのログインも可能です。
ゆうびんIDを登録すると、転居手続き以外にも、集荷の申し込みやゆうパックスマホ割りなどのサービスが利用できるので、とても便利です。転居届の受付状況もネットで確認できるので、おすすめの手続き方法です。
郵便局の窓口で手続きする
最寄りの郵便局の窓口に直接、転居届を提出する方法です。
郵便局に設置された転居届用紙に必要事項を記入し、以下の書類を添えて提出します。
<個人の方の必要書類>
- 本人確認書類(運転免許証・各種健康保険証など)
- 転居者の旧宅が確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードまたは住民票等、官公庁が発行した住所の記載があるもの)
参考:https://www.post.japanpost.jp/question/100.html
転居届用紙をポストに投函して手続きする
転居届用紙は、全国の郵便局に設置されています。必要事項を記入し、切手を貼らずにポストへ投函するだけで、手続きが完了します。本人確認書類などを添付しなくてもよいので、とてもお手軽な方法です。
窓口に手続きに行ったけれど、必要書類が不足していたり、また、新居の住所などを記入できなかったりした場合には、必要事項を記入したうえで、後日ポストへ投函すれば手続きが完了します。再び窓口へ行く必要はありません。
転居届用紙は、パソコン・スマホなどでダウンロードができないため、用紙を受け取りに郵便局まで行く必要があります。

郵便の転送手続きはどのタイミングで行う?
転送手続きは、引っ越しの前(およそ1週間前まで)に行いましょう。
申請から完了まで少し時間がかかるため、余裕を持って手続きを行う必要があります。
ただし、あまりに早く手続きをすると、転送期間が短くなってしまいますのでおすすめしません。転送サービスを受けられるのは、「届出日から一年間」となります。、だいたい1週間前には手続きをするとよいでしょう。
転送手続きは、「届出日」と「転送開始希望日」を記入できます。届出日はそのまま届出をする日を記入し、転送開始希望日には、新居へ入居する日を記載しましょう。
届出日から一年を経過すると、自動的に転送サービスが終了します。延長を希望する場合は、もう一度新しい転居届を提出しましょう。1年に満たず転送サービスを終了したい場合で、たとえば旧宅(実家など)へ戻られるのであれば、改めて転居届を提出することにより、新居から旧宅へ転送される形になります。
転送手続きをしないと郵便物はどうなる?

郵便局の転送サービスは、必ずしもしなければいけないものではありません。しかし、思いがけないトラブルが起こりえますので、ぜひ届け出ることをおすすめします。
転居届を出さずにいると、どのようなトラブルが起こるのでしょうか?具体的にみていきましょう。
行き違いで大切な書類が新居に届かない
「すべてのサービスの住所変更を完了させたから、転居届は必要ない」と思われるかもしれません。しかし、住所変更手続きには、意外と処理に時間がかかるもの。行き違いで旧宅へと届けられる可能性はあります。引っ越しに関連する重要書類が、新居に届かないと困りますよね。
これらのトラブルをふせぐために、転居届を提出しておくとよいでしょう。
旧宅へ配送された郵便物を他人に見られる
すべての住所変更手続きを完了させたつもりでも、日頃使っていない通販のDMなど、住所変更をしていない書類が旧居あてに配送されてしまうことが考えられます。
引っ越したことを知らず、知人が手紙を送ってくるかもしれません。はがきであれば、あて名や内容をみられてしまいますし、封書でも中身を開けられてしまう可能性があります。旧居へ新しく入居される方が、適切に対処してくださればよいですが、思わぬトラブルとなる可能性もあります。
転送サービスを利用すれば、住所変更をしていないサービスに気づくことができます。転送期間1年以内に、ゆっくりと住所変更を行えばよいので、確実に住所変更ができます。
次の入居者に迷惑をかけてしまう
転居届を提出せずに引っ越しをしてしまうと、次の入居者にご迷惑をかけてしまいます。
郵便物の誤配があったときは、すみやかに郵便局へ連絡をしなければなりません。次にお住まいの方が、誤配郵便物として郵便局へ届出をしなければならず、大変な手間をかけてしまいます。
次に入居される方のためにも、きちんと転居届を提出しておきましょう。
長期不在のときは「不在届」を提出しよう
長期出張などで不在にする場合や、引っ越しするものの転送サービスを利用するほどでもない短い期間の場合などは、「不在届」を提出しておくと便利です。
不在届は、郵便局の窓口またはパソコン・スマホでダウンロードできます。
不在届はこちら:https://www.post.japanpost.jp/question/115.html
期間は最長30日間で指定できます。その間に届いた郵便物は、郵便局で保管され、保管期間が満了すると、配達してくれるサービスです。
郵便受けに放置しなくてすむので、とても安心ですね。
転送サービスでできないこと
以下のようなケースでは、郵便物の転送ができないので注意してください。
転送不要郵便の転送
転送不要郵便は、前述のとおり、差出人が「この住所以外へ届けるのは不可」としている書類になります。
新居へは転送されず、差出人へ返還されます。
国や地方自治体からの郵便物、銀行やクレジットカードなどが転送不要として送られることがあります。これらの住所変更は優先的に行っておくとよいでしょう。
海外の新居へは転送不可
海外へ転居するとき、日本の旧居あての郵便物を海外の新居へ転送したい、と希望される方は少なくありません。
しかし残念ながら、海外へ郵便物を転送することはできません。
民間業者が行っている転送サービスを検討されるとよいでしょう。
参考:DANKEBOX https://jp.dankebox.com/
ECONOMOVE JAPAN https://www.economovejapan.com/service/rusutaku.html
amnet https://www.amnetos.jp/service/srv06_10.html
自宅あての郵便物をすべて会社へ転送するのは不可
仕事が忙しくて、会社に滞在している時間が長い方は、「自宅宛ての郵便物をすべて会社に送ってほしい」と考える方もおられるかもしれません。
しかし残念ながら、そのような転送サービスはありません。
入院中に親族への転送は不可
入院しているときだけ、親族に手紙を受け取ってほしい、と考える方もおられるでしょう。
しかし郵便転送サービスは、郵便物等を受け取る方がお住まいでない所への配送はされません。
このような場合は、不在届の提出がおすすめです。最長30日間で、指定した期間、郵便局で郵便物を預かってくれます。
どうしても入院中に受け取りたい郵便物がある場合は、転送先に病院を指定するとよいでしょう。この場合は、事前に病院にも確認をしてください。
死亡した方の郵便物の転送は不可
家族からの申し出でも、亡くなった方への郵便物を転送することはできません。
受取人が亡くなった場合には、郵便物は差出人へと返送されます。
こんなときどうする?転送サービスの疑問まとめ

4人家族のうち1人だけの郵便物を転送できる?
実家などから離れて暮らすことになった場合、家族の郵便物はそのままに、自分あての郵便物だけを転送してもらえます。
転送届には、「転居者氏名」と「引き続き旧宅に住む人」を記載する項目があり、個人で転送先を指定できるようになっています。
転送するときに差出人に新居の住所が知られてしまう?
転送時に、差出人に新居の住所が知られるのではないか、と不安になる方は多いと思います。ですが、新住所が通知されることはありませんのでご安心ください。
転送不要郵便で、差出人に返送される場合でも、差出人に新居が通知されることはありません。
転送期間が過ぎたら郵便物はどうなる?
転送期間が終了すると、自動的に転送サービスも終了となり、旧宅あての郵便物は「転居先不明」として差出人へ返還されます。転送サービスを延長したい場合は、再度転送届を提出しましょう。
転送期間を延長する方法は?
期間内にもう一度転居届を提出することで、延長の扱いとなります。申し込み方法は最初に行った転送サービスと同様の方法で手続きができます。
転居届のサービス期間はどこで確認できる?
転居届を提出し、サービスを申し込んでから開始するまでの間に3日〜7日ほど必要になります。サービスが開始されているかどうか、また、終了しているかどうかは、インターネットで確認できます。
e転居 受付状況確認はこちら:https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/ETN40S10MMC.html
確認には10ケタの転居届受付番号が必要になります。
転居届受付番号の確認方法は、e転居(パソコン・スマホ)で申し込みをされた方は、受付完了時に登録したeMailアドレスあてに配信されています。
郵便局の窓口またはポスト投函で転居届用紙で提出された方は、お客様控えに番号が記載されています。
転送手続きには期限がある?
転送手続きの期間は、「届出日より1年間」となります。「転送開始希望日」から1年間ではないので、注意してください。
転送サービスの期限を確認するには?
2つの方法があります。
1.パソコンまたはスマホでe転居にゆうびんIDを入力してログインします。
転居届受付番号を入力すると、利用期間を確認できます。
2.転送された郵便物には「転送期間終了日」が記載されています。こちらで残期間を確認できます。
転送サービスを解除するには?
転送サービスを解除する手続きは特にありません。1年を経過すると、自動的に解除されます。
新しく転居するとき、または旧宅へ戻るときには、新たに「転居届」を提出する必要があります。
届出から1年以内に「転居・転送サービス」を解除をすることはできないため、工夫をしなければなりません。
下記の例のように、「転居・転送サービス」の手続きを 2回行いましょう。
1年以内に別の場所へ引っ越すときの届け出の例
- 旧住所から新住所1への「転居届」を提出する
- 新住所1から新住所2への「転居届」を提出する
進学や就職、単身赴任などの理由で新住所へ引越したものの、
1年以内に旧住所へ戻ってきたという場合も「転居・転送サービス」の手続きを2回行う必要があります。
1年以内に旧住所へ戻るときの届け出の例
- 旧住所から新住所への「転居届」を提出する
- 新住所から旧住所への「転居届」を提出する
「転送届」の届出日から1年以内に再度引越しをする場合は、
再び「転居届」を出す必要があると覚えておくと良いでしょう。
入院中に病院へ郵便物を転送できる?
転居届に、病院名・病棟名・お部屋の号数を記入してください。ただし病院によって、受付窓口を設けている場合があります。入院先の病棟に確認をしてください。
海外の新居へ転送できる?
転送サービスでは、海外への転送はできません。海外出張などで長期間不在にする場合、「不在届」を提出すると、最長30日間郵便物を保管してもらえます。ご都合に合わせて活用してください。

面倒なライフライン手続きはでんきガス.netがおすすめ
引っ越しのときに便利な「郵便転送サービス」について解説しました。引っ越しに関する手続きはたくさんあり、とても大変ですよね。住所変更などの手続きをもれなく完了させるためにも、郵便局へ転居届を提出してください。転居届は、パソコン・スマホでe転居のサービスを利用するか、郵便局窓口・ポスト投函で提出する方法があります。ご都合に合わせて最適な方法を選んでください。
パソコン・スマホなら、ほかにもさまざまな郵便局のサービスがありおすすめです。転送サービスの期限は1年間。大切な郵便物を確実に受け取るためにも、手続きをお忘れなく。
また、電気やガスなどの手続きはお済みですか?
面倒な電気やガス・インターネットの手続きにはでんきガス.net(0120-911-653)がおすすめです。でんきガス.netは、ライフライン手続きを一括手配できるので、手続きが電話一本で完了します。引越しの負担を軽くしたい方はぜひ利用してみてくださいね。
| 受付窓口 | でんきガス.net |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-911-653 |
| 受付時間 | 8:00~20:45(年末年始を除く)
※Web受付は24時間受付 |
▼でんきガス.netについてはこちら でんきガス.netとは?電気やガスの面倒な手続きを無料手配してくれるって本当?
