
SDGs 大学プロジェクト × Ferris Univ. – Part 1 –
目次
フェリス女学院大学の紹介


フェリス女学院大学の母体となるフェリス女学院は、1870年(明治3年)に、アメリカ改革派教会から派遣された宣教師メアリー・E. キダーにより創設されました。日本初の近代的女子教育機関で、2020年に150周年を迎えました。
大学には文学部、国際交流学部、音楽学部の3学部があり、横浜市内にある2つのキャンパス(緑園キャンパス、山手キャンパス)で、約2,200名の学生が学んでいます。
フェリス女学院がその歩みのなかで大切にしてきたのは、「For Others」という教育理念です。この言葉は「他者のために」と訳すことができます。大学では、さらに「他者と共に」という共生の問題意識も大切にし、現代のさまざまな問題と取り組んできました。環境問題への取組み、多文化共生に向けた地域活動、ボランティア活動、バリアフリー活動といった活動が、学生たちの手によって積極的に展開されてきました。
「For Others」はただのモットーに終わることなく、日々の実践と結びついて息づいています。
「3Re(スリー)」プロジェクトとは

本学では学生有志が横浜市資源循環局と手を組み、学食での食品ロス削減を目指す「3Re(スリー)」プロジェクトを推進。「Replace(コンビニの選択から食堂へ)」「Recycle(売り切れはいいことだと容認してもらう)」「Renew(新たにSDGsにつながる行動を)」という3つの「Re」の達成を目標としています。
このプロジェクトの大きな特徴は、人が自然と望ましい行動を取るようにデザインや仕掛けによって誘導する「ナッジ」という行動経済学の理論を取り入れていることです。
今回は、プロジェクトに関わる国際交流学部の高雄綾子准教授と学生の白井結梨さんにお話をお聞きしました。
食品ロス削減に「ナッジ」を活用
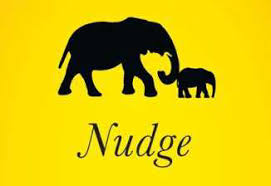

-まず、お二人が食品ロスについて思うことをご説明いただけますか?
高雄准教授:国際的には、まだ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」と、食べられない部分を捨てる「食品廃棄」は分けて考えられています。一方、日本ではこれらが一緒に「食品ロス」と表現されることから、政府や企業と一緒に消費者も取り組んでいく必要性が強調されていると思います。
白井さん:実は私は、もともとそこまで食品ロスに興味を持っていたわけではありませんでした。大学で高雄准教授の授業を受けたことがきっかけとなり、日本だけでなく世界的な問題にまで視野を広げなければいけないと考えるようになりました。
-「3Re(スリー)」プロジェクトとはどのような取り組みなのでしょうか?
高雄准教授:このプロジェクトは、横浜市資源循環局から、「ナッジ(行動デザイン)」という考え方を取り入れた食品ロス削減への取り組みを学食で展開したいとの提案があって始まったプロジェクトです。
ナッジとは、罰則のような規制や報酬のような経済的インセンティブ(誘因)に頼らず、人々が無意識に望ましい行動を取ってしまうように導く仕掛けを設計する手法です。これは行動経済学から生まれた理論で、公共政策分野でも幅広く実践されています。
学食側へのヒアリングを通し、本学の学食での食品ロスは過剰な仕入れによる廃棄が大部分を占めていることが分かりました。これは一見、消費者である学生が関与できる余地が少ないため、ナッジの活用の意味が見いだせないことになります。
困ったなと思いつつよくよく話を聞いてみると、過剰仕入れは利用者数が読めないなかで、サービス低下につながる売り切れを回避するためにできるだけ多く仕入れておくという経営判断によって起こることが分かりました。これは、利用者に売り切れをある程度容認してもらえるという関係づくりによって、ある程度解決可能なものです。そこで、仕入れを減らして仮に売り切れるメニューが出たとしても許してもらえる心理環境を作り出すことを目指しました。
売り切れをポジティブに


-学食での問題解決に向け、具体的にどのような活動をしたのですか?
高雄准教授:2022年度は、売り切れは食品ロスの削減につながるというポジティブなメッセージを発信するポスターを掲示した他、メニュー写真のデジタル表示を実施しました。
白井さん:これまでは券売機の横にしかメニューがなく、食券を買うのに時間がかかって混雑してしまう問題がありました。そこで列に並んでいる間に選べるように、デジタルフォトフレームを活用してメニューを増設。売り切れがあればすぐに知らせて他のものを選んでもらうようにし、人の流れを改善できるように工夫しました。
また、もともとご飯の量を少なめで頼むことはできたのですが、このこと自体あまり認知されていませんでした。現在はこれを周知できるようなポスターも掲示しています。
他にも、学食ではメニュー用のサンプルとして本物の料理を展示しているのですが、これをデジタル表示に切り替えることも検討しています。
高雄准教授:デジタルフォトフレームでのメニュー表示に行き着いたのは、待ち時間の短縮だけが目的ではありません。お客さんである学生に学食とのコミュニケーションを促すことで、受動的にサービスを受けるだけでなく、食品ロスを減らすために一緒になって参加してほしいという意図があります。
こうした取り組みにより、顧客満足度を上げると同時に、学食での仕入れ量を調整してもらうことで食品ロス5%減を達成しました。また、ご飯の量を少なく指定できることを周知したことで、月に5キロほどの米の消費量削減が実現しました。
-これ以外にも、ナッジ理論を活用して検討した施策はありますか?
高雄准教授:他にナッジとして検討したものは、例えば「アプリで予約販売する」「テイクアウトの需要が高いので残った食材を弁当として販売する」「券売機をキャッシュレスにして待ち時間を短縮する」などです。また、もっと学食とコミュニケーションを取れるようなナッジを考えてみるように促すと、「SNSでの情報発信」というアイデアも出ました。
ただ、学生たちとしては、ポイント制や割引のような経済的インセンティブを切り離して考えるのはなかなか難しかったようです。多くの選択肢から好きなものを選ぶという「消費者」の前提から離れられないのだと分かりました。
学食と学生が問題意識を共有


-プロジェクトを進めていく中で苦労したことや大変だったことをお聞かせいただけますか?
白井さん:コロナ禍で登校の機会が減少した時期があったため、そもそも学食に来ないから興味を持ってもらえないという問題がありました。
また、学内にいても学食では料理を注文しない学生もいます。その理由を考えてみるにあたって調査を行ったところ、多くの学生はコンセントのある席を利用したいという思いを持っているのにも関わらず、コンセントのある座席が埋まっていて利用できないといったいわゆる「電源難民」の学生が多いことがわかりました。
ですので、人が少ないうちにコンセントがある席を確保し、食事は購買で買ったパンなどで済ませてしまう学生は少なくありません。プロジェクトでのディスカッションでは、このような学生の立場から見た事情も説明して認識をすり合わせました。
高雄准教授:学生たちがそもそも学食にあまり関心のないことが分かり、少なからずカルチャーショックを受けましたね。ディスカッションでは、女子大ならではの「ヘルシーさ」や「おいしさ」と食品ロス削減をつなげられるように意識しました。
-プロジェクトを進める上では学食の運営会社との協力や調整が不可欠だったと思いますが、どのように連携されたのでしょうか?
白井さん:おそらく一学生や先生がやりたいというだけでは難しかったと思います。今回のプロジェクトがスムーズに進められたのは、横浜市の資源循環局の方たちも関わってくれたおかげが大きいのではないでしょうか。
-プロジェクトを通してうれしかったことや印象的だったことはありますか?
高雄准教授:学食の運営会社の方と学生たちが直接話し合う中で、問題意識を共有できたことです。コロナ禍を経て、どれだけお客さん(学生)に喜んでもらえるかを模索する中で、サービス過剰になりがちな状況を立ち止まって見直すきっかけになりました。
また、学生たちも、いつでも好きなものが食べられるという状態がいかに食品ロスを生み出す構造の上に成り立っているか実感できたのではないでしょうか。出来事というよりもプロセスの中で、食品提供者と消費者が一緒に考えていくことで解決できることはたくさんあると考えさせられました。
白井さん:プロジェクトの認知度はまだまだ低いですが、他の学生から学食が利用しやすくなったという声を聞くと、取り組みが少しずつ浸透しているのを感じてうれしいですね。自分自身も学食を使いやすくなったと感じますし、友人から「ご飯を少なめで頼んでみたよ」と報告してもらえることもありました。
新しい認識に触れることが変化の鍵


-プロジェクトに取り組む際、SDGsとの関連性などは意識されましたか?
高雄准教授:まさにSDGs12の「つくる責任、つかう責任」を実践で学べたと思います。誰も食品ロスを出したくて作ったり食べたりしているわけではありません。しかし、社会経済的な構造が売り切れや品切れに不寛容な心理を作り、結果的に過剰サービスになってしまっているのが現状です。このような課題をどうすればナッジで解決できるのか、まだまだ試行錯誤しています。
好きなときに好きなものが食べられることは当たり前なのではなくとても幸せなことだと認識し、そうでない場合があっても「まあいいか」と思える人を増やしていくことが、結果的にSDGs12の目標達成につながるのだと思います。
経済的インセンティブへの高い関心は、学生たちが「自分はともかく他人は」合理的に選択するものだと信じていることから来るものですが、ナッジを通じて非合理な行動にも理解が及んだのではないかと思います。
ただ、この学びを学びとして自覚している学生がいないため、行動や心境の変化にはまだ至っていません。変化に至るためには、既存の認識構造との違和感を自覚し、新しい認識の存在を知る必要があります。
例えばヨーロッパでは、食品ロスとなりそうな食材を扱うスーパーやレストランが誕生し、余った食品をシェアできるようなアプリなども発達しています。学生だけでなく学食の運営会社の方も、このような新しい認識に触れる機会が少ないとなかなか変化に至らないのだと感じました。
日本の場合は食品衛生の観念が非常に発達しているため、このようなスーパーやレストランはなかなか普及しづらいと思います。そうなるとやはり、限られたメニューの選択肢を受け入れて仕入れ量を減らしていくしかないので、豊かな食生活という点からは魅力のないものになってしまいます。課題は多いものの、日本ならではの食品ロス削減ナッジができればとても意義あることだと思います。
今後の展望
-最後に、今後の展望をお聞かせください。
高雄准教授:SNSでメニューの人気投票を実施し、メニューごとの仕入れ量や仕込みを細かく調整できるようにしたいと思っています。投票に参加してもらうことで、学生にも学食運営の参加者になってもらいたいですね。
そして大学組織として食品ロスとどのように向き合うかも大きな課題です。プロジェクトを通して見えてきたのは、学食も企業としてクライアントである大学の意向に答えなくてはならず、そして大学もやはり企業として顧客である学生の満足度を高めたいと考えており、この両者の認識が合致して意図せず食品ロスを生み出す構造を作ってしまっていることです。
このような現象は多くの社会分野で発生していますが、そこでは利用者や消費者の参加が大きな意味を持ち、この点にナッジを活用したSDGs達成への取り組みの可能性があると思います。
白井さん:学食での取り組みを成功に導くことができたら、学内の他の部分でも応用できると思っています。まずは学食での取り組みを一層進めていきつつ、SDGsに関する活動をしているサークルとも協力していけたらと考えています。もっと他の先生や学生も巻き込んでいきたいです。
