
SDGs 大学プロジェクト × Tohoku University of Community Service and Science. -Part 2-
目次
東北公益文科大学の紹介
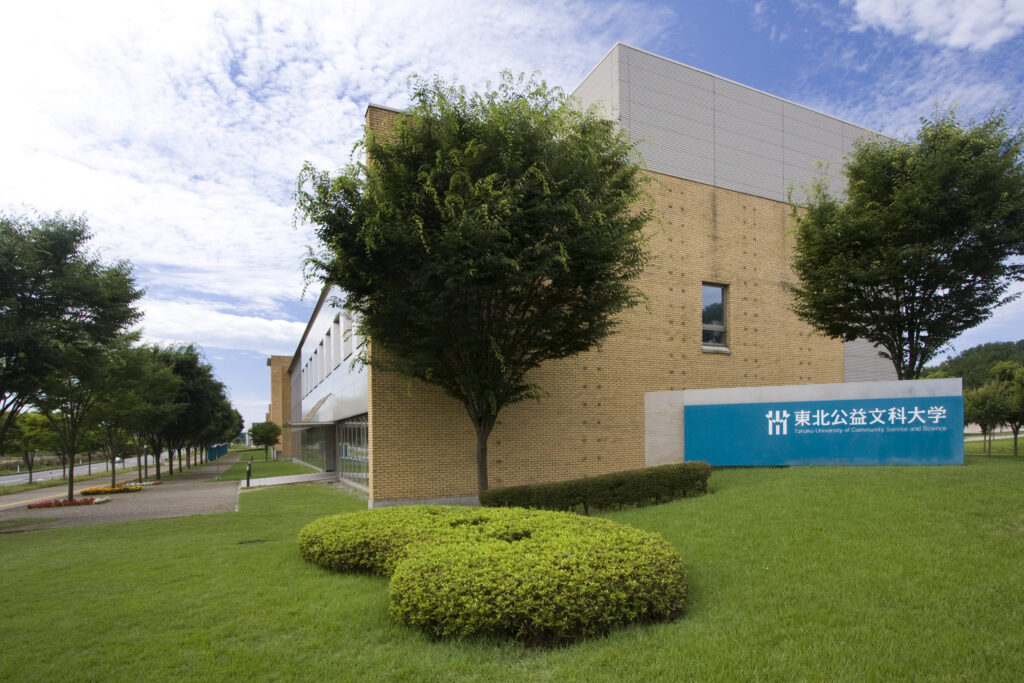
東北公益文科大学は、「この地に四年制大学を!」という地域の皆さんからの熱い要望を受けて、山形県と庄内地域14市町村(当時)が出資する公設民営方式で、山形県酒田市に2001年に開学しました。
学びの大きな特長は、「他大学にはない“公益”を理念として、1つの学部の中で文系・理系両方を学ぶことができ、情報科目を全員が必修で学ぶこと」。公益学部公益学科の中に経営、政策、地域福祉、国際教養、観光・まちづくり、メディア情報の6つのコースを設置し、グローバルな視野を持ち、地域の人々とともに、地域社会が直面する経済、行政、福祉などの課題にリーダーシップを持って果敢に取り組む人材を育成しています。
学生活動団体 Praxisの活動の内容と目的
退田秀太朗さん:Praxis(プラクシス)という団体名は、その由来がドイツ語の「実践」にあります。当団体は、酒田市の日向(にっこう)地区を主要な活動の場とし、学生それぞれの「好き」や「得意」を活かしたアプローチで活動に取り組んでいます。
Praxisの活動の一環として、「日向里かふぇ」というコミュニティカフェにおいて、月に1度の頻度で店長を務め、メンバーが季節やイベントに合わせたメニューを企画し、お客様に提供しています。
また、日向地区内の空き家を再利用して、地域との交流の場を築く「にっこりはうすプロジェクト」にも取り組んでいます。
このプロジェクトでは、DIYでベンチを製作したり、竹を使用してブランコを制作したりしています。地域の魅力を少しずつ発信する拠点としての役割も果たすことができればと考えています。
他にも、酒田市内の鳥海八幡中学校の「総合的な学習の時間」に講師として招いていただき、中学生として地域のためにできることを検討するワークショップを行ったり、庄内総合支庁で展開される「食の都庄内」というプロジェクトとの協働で、「日向里かふぇ」のメニュー開発に向けて郷土料理について学んだりしています。
「日向里かふぇ(にっこりカフェ)」での活動


退田さん:「日向里かふぇ」が営業している建物は、以前は「日向小学校」として使用されていましたが、地元の住民・行政・企業・大学生等の共創によるDIYプロジェクトによって生まれ変わりました。
このカフェでは、地元で収穫された新鮮な野菜やそれらを加工した食品、工芸品なども販売しています。私たちがカフェを担当する際は、ハロウィンやクリスマスなどの季節イベントに合わせたメニューにしたり、「にっこりはうすプロジェクト」で地域の方から借りた畑で自分たちが育てた野菜を積極的に活用しています。

関野大斗さん:カフェではできるだけ地域で作られている野菜を使用し、「地産地消」を実践しています。お客様に提供する際には、生産地や生産者の情報が伝わるように工夫しています。
また、自家栽培の際には、地元の農家から育て方を学び、対話を通じて美味しい野菜の活用方法についてのヒントを得ています。
一方、自家栽培していない野菜などをメニューに取り入れたい場合には、地域の農家から直接購入するなど、地域農業との連携も心がけています。
「にっこりはうすプロジェクト」の内容


関野さん:「にっこりはうすプロジェクト」は、昨年度に立ち上げた取り組みです。このプロジェクトは、酒田市の公益活動支援補助金を活用しました。
補助金については、Praxisのメンバーがこの支援制度を見つけ、申請時に必要となる計画書や予算書などの書類を作成し、詳細が理解できるようなポスターを製作しました。
その結果、申請が承認され、事業を始動させるために不可欠な資金を調達することができました。
事業に関しては、日向地区にある空き家の改修が主要なプロジェクトであり、建築関連の仕事をされている住民の方からの協力と助言を受けながら、必要な材料を調達し、家具(ベンチなど)や遊具(ブランコなど)を製作しました。このブランコは竹を主要な素材として使用しましたが、地元産の素材を最大限に活用することを心掛け、竹を伐採する作業から取り組みました。また、昨年度にはこのプロジェクトに関連するワークショップを4回開催しました。
さらに、これまで野菜の栽培は地元の方の畑を借りていたのですが、今年度からは「にっこりはうす」の敷地内に独自の畑をつくり、とうもろこし、かぼちゃ、さつまいもなどを栽培し、地元の「日向里かふぇ」に提供するための食材としました。
Praxisに入ったきっかけ

土田瑞貴さん:Praxisに入会した理由は、Praxisの活動内容が学生ができることややりたいことを活かすものであり、参加しやすく、自由な雰囲気を感じたからです。
さらに、自分の好きなことを通して、地域の方々と交流できることは、私の成長にとって非常に貴重な機会であると考え、参加することにしました。
退田さん:私の場合、1年生の時に行われたサークル紹介でPraxisという団体の存在を知りました。その際、「日向里かふぇ」というコミュニティカフェの運営や、空き家利活用の取り組みについて聞いた際、大変興味を持ちました。
正式に入会する前に、一度その活動に参加させていただきました。その際に、Praxisのメンバーと地域の皆さんが非常に温かく、アットホームな雰囲気が感じられました。この温かさと取り組みに惹かれ、Praxisに入会する決断をしました。
関野さん:私は、将来社会で働く際に、生まれ育った地元に何か還元できる仕事をしたいという思いを高校時代から抱いていました。
そして、友人から声をかけられ、Praxisに仮メンバーとして参加することになりました。Praxisの活動内容は地域に密着しており、私の将来のやりたいことに関する重要なヒントを得ることができると感じたため、Praxisへの入会を決意しました。
実際にPraxisの活動に携わってみて、日常生活では接することが少ない目上の方々、それこそ高齢者から子どもまで、幅広い年齢層の方々と交流する機会が得られることは非常に貴重な経験であると感じています。
Praxisの活動に取り組む中での課題
関野さん:地域全体で高齢化が進行しており、普段情報を伝える手段として利用しているSNSなどのネットワークは有効ではありません。また、紙媒体での広報も効果が限られたため、活動を進める上でも最終的には個人単位での直接連絡という方法が有効であるという実感を得ました。
とはいえ、多くの人への情報発信や共有が大切だと思いますので、このような状況を踏まえ、適切な情報の発信方法について、模索しています。
退田さん:現在の課題として、私たちが取り組んでいる活動と、地域のニーズとの乖離を感じるところもあり、これを修正する必要があると考えています。
地域の皆様に喜んでいただける方法や、情報を共有する手段についても考慮しながら、メンバーと地域の皆様の思いや考えのすり合わせが不可欠だと感じています。
関野さん:活動を通じて、地域の皆様との円滑なコミュニケーションは極めて重要であり、同時に課題であると考えています。
この中で、「日向里かふぇ」でのランチ提供時には、私たちの思いをメッセージカードに込めるなど、コミュニケーション促進のための取り組みを実施しています。
さらに、私たちが主体となって行っている活動に限らず、地域のお祭りや運動会などのイベント、地域づくりのワークショップなどにも積極的に参加し、Praxisでの活動や私たちの取り組みがより多くの皆様に理解されるよう努力しているところです。
活動を続けるモチベーションとは?
土田さん:私のモチベーションの源泉は、地域の皆様と直接コミュニケーションをとる機会が多いことから、私たちの活動の結果を皆様のリアクションというカタチで触れることができる点にあります。
さらに、活動を通じて失敗することもありますが、そのような失敗経験を活かして改善策を実行し、地域の皆様から喜んでいただくことが、私のやる気を高める要因となっています。
退田さん:私が活動を続けるモチベーションは、何よりもメンバーとの交流が一番の要因だと考えています。
プロジェクトを進行する際には、計画通りに進まない場面もあり、その都度修正が必要となることがありますが、その過程で仲間たちと協力し、改善や問題の解決策を考えることで、お互いの絆が深まり、楽しく取り組むことができることが、モチベーションに繋がっていると感じています。
関野さん:私が活動を続けるモチベーションは、地域の皆様からいただく反応と、その反応から得られる達成感が非常に大きな要因です。
特に、「にっこりはうすプロジェクト」のDIY活動において、中心メンバーの一員として関わりました。この活動においては、さまざまな悩みや課題に直面することもありましたが、地域の皆様から温かいお言葉をいただき、励ましを受けました。
このような支援があったことにより、私はこの活動を続けることの意義深さを感じ、モチベーションを高める要因となったと痛感しています。地域の皆様からの励ましや温かい言葉こそが、私がこの活動に取り組む上での重要な要素であり、モチベーションの源泉であると確信しています。
Praxisの活動による気付きや学びについて
退田さん:Praxisの活動に参加し、最も重要な成果として実感しているのは、「行動力」です。自身の「やりたいこと」や地域への貢献を考える過程で、その実現には積極的な行動が不可欠であることを理解し、それを実践するよう努力しました。
また、自身の経験を通じて得た知識をPraxisのメンバーと共有するだけでなく、Praxisの目的や魅力を同級生にも伝えることで、意欲的な2年生メンバーが17人まで増加しました。積極的な行動が皆を動かすことにつながりうれしく思います。
土田さん:Praxisの活動を通じて得た気づきについて、普段の学生生活では接点が少ない幅広い層の方々と交流する機会が多かったことから、私の考え方や視点に新たな視点を加えることができる貴重な機会であると感じています。このような経験を通じて、自身の見識や考え方を広げられることで多くの気づきを得ました。
関野さん:私がPraxisの活動を通じて学んだことは、組織をつくる難しさです。私は以前Praxisの副代表を務めていましたが、後輩の増加や組織の拡大により、喜びと同時に組織を効果的に運営する難しさを実感しました。
さらに、Praxisのメンバーだけでなく、地域の他の関係者との関わりがある団体であることから、全体のメンバーの意見調整や、個人単位での取り組みへの情熱の差異に直面し、将来的には社会で組織を束ねるのに必要となる経験と学びをPraxisの活動を通じて得ていると感じています。
指導者の立場から見た学生の成長について
小関准教授:学生の成長は、個々に異なるものです。克服すべき課題もそれぞれ異なるでしょうから、学生一人ひとりがそれぞれの課題に気付いたとき、克服しようとする努力に触れたとき、目標を達成して手応えを実感しているとき、そのような様子に接することができると、私としても大変喜びを感じます。
日々一生懸命努力している学生たちに伴走しながら、今後も様々な個性を持つ彼らを見守っていきたいと考えています。
これからの展望

退田さん:Praxisは、学生の「やりたいこと」「できること」を活かせるという信念のもと、地域とのつながりを大切にしています。今後、さらに活動の幅を広げることを目指しています。
とはいえ、Praxisという大学生の団体は、そのメンバーが定期的に入れ替わり、持続可能な団体を維持することが課題となっています。さらに、地域の状況も変化しているため、これらの課題に対処しながら、持続可能な団体を築いていきたいと考えています。
今後も参加するメンバー全員が協力し、目標に向かって楽しみながら取り組んでいきたいと思っています。
