
SDGs 大学プロジェクト × Chiba Univ.
目次
千葉大学の紹介
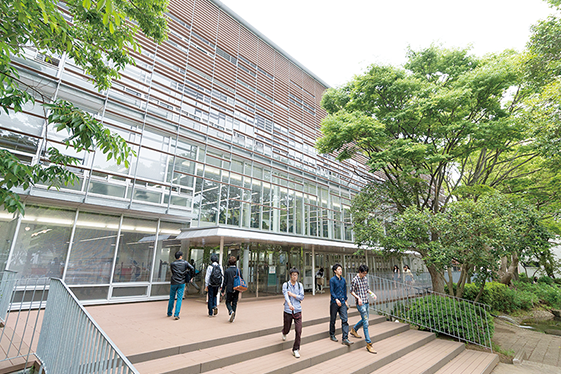

千葉大学は、1949年に千葉医科大学、千葉師範学校、東京工業専門学校、千葉農業専門学校などが合併し、新制の国立総合大学としてスタートしました。その後、2004年に国立大学法人千葉大学が設立され、千葉大学は同法人により運営されることになりました。
現在、千葉大学には10つの学部と大学院があります。国際教養学部、文学部、法政経学部、教育学部、理学部、工学部、園芸学部、医学部、薬学部、看護学部の10学部に加え、人文公共学府、専門法務研究科、教育学研究科、融合理工学府、園芸学研究科、医学薬学府、看護学研究科、総合国際学位プログラムなどが設置されています。また、附属図書館や医学部附属病院、共同利用教育研究施設、学部附属の教育研究施設、教育学部附属の幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校などが大学の構成要素となっています。
2023年現在、国立大学法人千葉大学の教職員は約3,500名で、学部学生の入学定員は2,317名、収容定員は9,732名です。大学院の収容定員は3,093名で、国立大学としての規模や内容は非常に充実しています。
千葉大学のキャンパスは、大学本部が置かれる西千葉がメインキャンパスであり、医学・薬学・看護の教育研究の拠点として亥鼻、園芸学部のある松戸、環境健康フィールド科学センターの柏の葉、デザイン・リサーチ・インスティテュートの墨田サテライトの5つのキャンパスがあります。
SDGsに取り組まれたきっかけ
千葉大学では、学生主体の環境マネジメントシステムを20年間にわたって継続しています。このシステムは2003年にスタートし、同年10月には学生委員会が結成されました。
そして2004年4月からは、環境マネジメントシステムを実務教育の一環として取り入れ、学生に対して単位を付与するようにしました。この20年間の活動を通じて、私たちは着実に前進してきました。
2015年にSDGsが採択され、社会全体に浸透してきた時点で、大学も環境エネルギー方針を改定し、SDGs達成に向けた行動と社会貢献を目指す文言を盛り込みました。さらに2019年からは、これまでの環境報告書をサステナビリティレポートに変更しました。これにより、環境活動だけでなく、ジェンダー平等や障害を持つ学生への支援など、社会的な取り組みも報告するようになりました。
長年にわたる学生主体の環境マネジメントシステムは、マンネリ化を避けるために新しいチャレンジが必要です。そのため、単に環境負荷を減らすだけでなく、社会的な側面にも目を向ける必要性を感じました。全ての人々が取り残されることのないようなアプローチで活動を進展させることが重要だと考え、大学内でもこの変化に対する反対意見は少なく、SDGsへの切り替えが実現しました。
SDGs施策の内容
本学では、様々なSDGsの取組みを行っていますが、今回は環境ISO学生委員会についてご紹介いたします。
環境ISO学生委員会

環境ISO学生委員会は、約300名の学生が所属し、キャンパスごとに地区を分けて活動しています。さまざまな活動を行っており、具体的な例を挙げると、特に長期間かつ大規模に行っているプロジェクトとして、京葉銀行との連携があります。
このプロジェクトに関連して、京葉銀行との取り組みをまとめたサイト「エコ発信局」があり、プロジェクトの報告や記事の掲載などが行われています。このプロジェクトでは、毎年SDGsに関する啓発ポスターの掲載も行われていますが、このポスターは環境マネジメントシステムを受講している1年生が作成しています。
1年生は授業の最初にポスター作成に取り組みます。大体毎年100人以上の1年生がいるため、少人数のグループに分けられ、約20のグループが作成に取り組みます。それぞれのグループは授業の最後に皆の前で発表し、投票で最も優れたポスターを選出します。この方法により、デザインにも熟考がなされたポスターが制作されるだけでなく、1年生が委員会に入ったばかりの初企画がこのポスター作成になるため、学生としてSDGsについて学びながら取り組むことができるようになっています。
▼エコ発信局のページはこちら エコ発信局~いそちゃんの部屋~ | 京葉銀行
活動する上での困難
企画運営する上で共通して感じることは、環境やSDGsに対して意識の違いが非常に大きいと思います。特に学生の意識に関しては、今まで環境やSDGsに関する活動に触れていなかったとしても、委員会に入ってくる学生は企画を進める中でどんどん知識を身につける傾向があります。
しかし、委員会に入っていない学生に対しては、「環境ISO学生委員会っていう名前ぐらいは聞いたことあるけど、実際どんなことをやっているかあまり知らない」といった声もありますし、「SDGsに関してもそんなに意識することでもないよね」という考え方も見受けられます。
しかしながら、大学で活動するからには学生に対しての啓発や意識向上も大きな役割の1つだと考えています。そのため、環境ISO学生委員会では学内の啓発活動にも取り組んでいます。例えば、構内の事業者と連携した活動を多く行っています。学食から出る生ごみを生協さんと協力して集め、それを学内の落ち葉と混ぜて堆肥にして販売したり、学内にあるライフセンターというコンビニのレジ袋有料化やプラスチック削減の取り組みを進める中で、米ストローも販売しています。
こうした取り組みによって、年々興味や関心の度合いが上がってきていることを実感しています。大学内での取り組みを通じて、より多くの学生に環境やSDGsに対する理解を深めてもらえるよう努めています。
環境ISO学生委員会で活動するモチベーション

私としては、委員会内外を問わず、他の人との交流が非常にモチベーションになっていると感じています。まず、委員会内では約300名のメンバーが所属しており、お互いに助け合いながら企画を進めています。
実際に、企画に困ったときでも相談すると、熱心に考えてくれたり、アイデアを出してくれるメンバーがたくさんいます。そのようなお互いの支え合いが、私たちのモチベーションを高める一因だと思います。
また、委員会の外部としても活動する中で、多くの外部の方々とのつながりがあります。企業や他の大学の環境系団体、サークル、そして千葉で環境活動をされている団体などと連携してプロジェクトを進めています。これらの方々が私たちの活動に賛同し、応援してくださることも大きなモチベーションとなっています。
特に、他の大学の活動の様子を知ることで、「同じ学生でもこういう取り組みをしているんだ」「こういう風に頑張っているんだ」という刺激を受け、個人として成長する機会となっています。学ぶことも多いため、こうした経験も私たちのモチベーションに繋がっていると思います。
今後の施策

2003年に委員会が発足し、今年でちょうど20周年を迎えることから、私たちは活動を継続し、さらなる発展を目指しています。具体的に、継続していきたい点は、学生主体という特徴を大切にしています。これは、委員会の発足当初から大事にしている価値であり、今後も企画の運営から環境エネルギーマネジメントシステムの運用まで、学生主体で取り組んでいく意向です。
一方で、発展させたい点としては、委員会内外を問わず、様々な交流活動を増やすことを考えています。
これは、コロナ禍によって恒例だった活動がストップしてしまったことにも関連しています。以前は委員会内で学生が集まり、仲を深めるようなイベントを行っていましたが、コロナの影響で実現が難しくなりました。しかし、今年に入って徐々に状況が緩和され、委員会内での交流を深めるイベントにも取り組んでいます。
さらに、外部との交流も大切にしています。例えば、タイに10名ほど派遣して環境に関する学びを促進するプログラムを計画していましたが、コロナの影響で一時中止になりました。しかし、最近では行けるようになり、外部の方々との連携を強化していく意向です。
これらの取り組みを通じて、私たちの委員会の活動をより充実させ、環境への貢献をさらに高めていきたいと考えています。
高校生へのメッセージ

私が個人的に活動していて感じる、環境ISO委員会の素晴らしい点は、何にでも挑戦できる雰囲気があることだと思います。委員会内では、失敗しても許される環境があり、そのため失敗しにくいと感じています。まず、環境マネジメントシステムの授業があることで、ビジネススキルから環境に関することまで幅広い知識を学ぶことができます。さらに、先生方も企画についてわからないことがあれば、私たちにも相談できる雰囲気を提供してくださるので、その点も私にとっては非常にありがたいです。
ですから、環境やSDGsに関わらず、「大学に入ったら何か新しいことにチャレンジしたいな」と考えている方には、本当に環境ISO学生委員会がぴったりだと思います。自分でそう言うのも控えたいのですが、ぜひぜひ、私たちの委員会に興味を持って入ってきてくれる後輩の皆さんをお待ちしています。心から歓迎します。
