
SDGs 大学プロジェクト × Tokyo Future Univ.
目次
東京未来大学の紹介


東京未来大学は、社会が求める“人財”を育てることを使命とし、社会に出るための準備期間として社会で働くうえで必要なマナーや仕事への取り組み方、姿勢、そして働くことの価値や喜びを4年間伝え続けています。
そのため、入学前から、在学中、卒業後まで一貫してサポートする総合的な学生支援体制である『エンロールメント・マネジメント』を取り入れています。学生のさまざまな悩みや不安、希望、要望をどのようにサポートできるか徹底して考え、実行に移し、学生の抱える問題に向き合っています。
本学独自のキャンパスアドバイザー(CA)、クラス担任、専門科目の教員の3方向から、学生をサポートし、学習面だけでなく、進路・生活面の相談までをフォローしています。
SDGsに取り組まれるようになったきっかけ
母体である学校法人三幸学園としてもSDGsへの関心が高く、系列の専門学校や通信制高校でもSDGsを視野に入れた取り組みをしています。
本学でもSDGsへの関心を学内外へ高める目的で、大学祭にてSDGsを意識した出展・出店の取り組み、ブログを通じて先生方の研究・教育・社会貢献活動を記事にする取り組みに力を入れています。
本学は、比較的小規模な大学であることから、地域社会と一緒に育んでいくという観点から、大学祭やブログなどを通した取り組みを考えました。
大学祭について
学⽣主体で創る⼤学祭「MIRAI FES.2023」を2023年10⽉28⽇(土)、10⽉29⽇(日)、10月31日(火)の3⽇程で、開催します。地域企業と連携したワークショップなどを開催するほか、SDGsの理解を深めるゲーム出展やごみ削減の創意⼯夫など、本イベント全体でSDGsに取り組んでいます。
本学では昨年度よりSDGsを意識した出展・出店の取り組みを学生主体で行っており、来場者へ各出展・出店ブースで17項目のうちどれに該当し、どういった目的で実施しているかなども明文化して行っています。
MIRAI FES.では、学生の「学び」と「成長」という部分に重きを置いているのですが、学生には「学び」と「成長」の中には勉強だけなく、それが社会にどう繋がっていくのか、学んだ先に、自分達が社会で活躍する上でどのように社会と繋がるのかという観点で、SDGsとの関連を考えてほしい、という思いがあります。
MIRAI FES.では、学生は8ヶ月もの期間をかけて、出展内容、企画内容をSDGsの項目と関連づけて準備を進めていきます。例えば、縁日を題材とする企画であれば、縁日らしい体験コーナーや企画を考える際、企画内容・コンセプトが、SDGsのどの項目と紐づけられるのか、を考えながら創りあげていきます。
過去には、企画内容を優先して出展・出店内容を考えてしまうことで、各クラスで設定するSDGsの項目が重複してしまうケースもありました。特に重複しやすい項目は、ゴミ問題や海の汚染など、いい意味で学生が意識しやすいゴールでもあるのだろうとも思いますが、学生が様々な方面からSDGsの17項目を偏りなく取り入れて進めていくことが望ましいと考えています。
学生が主体的に、大学の学び内容(心理学や保育・教育学、経営学)をブレンドしつつSDGsに繋がる点を模索しながら、8ヶ月間でより一層、企画内容をブラッシュアップしていくことを期待しています。
▼⼤学祭「MIRAI FES.2023」についてはこちら -MIRAI FES.2023-
学生の活動

本学では、クラス制を用いており、小規模大学の強みを活かして、クラスごとに出展・出店をします。4月からの2ヶ月で企画を考えつつ、企画内容を鑑みてSDGsに繋がる項目も併せて考えていきます。企画内容がまとまった段階で、学生は企画書を作成し、後日実施される企画プレゼンテーションの場に備えます。
企画が出揃った段階で、企画プレゼンテーションの場を設け、全クラスの出展・出店内容を、教職員を相手にクラスの代表者がプレゼンテーションを実施します。このプレゼンテーションは、他のクラスと競い合う仕組みでもありますが、発表後に、教職員からフィードバックをもらい、企画内容の磨き上げをする目的でもあります。
このような流れを通して、物を無用に使わないことや、リサイクルできるものは他にあるかなど、自身の周辺からSDGsを取り入れる意識を持ち、大きな規模でなくとも、自分たちに出来ることを考える癖はついてきたと感じています。SDGsと大きく捉えてしまうととっつきにくいこともあると思いますが、自分達の手の届くところから繋がりを見つけてより一層この興味が広がっていくことは素晴らしいことだと思います。
大学祭の今後の予定
SDGsに傾倒しすぎてしまうことで、ものを作る制限が徐々にコストダウンをするという認識になってしまうことは望んでおりません。昨年はSDGsを全面に出して実施していたのですが、今年はSDGsの観点はもちろん取り入れますが、全面的に押し出すというよりは「あって当たり前」というもう1つ上の段階に変えていこうと考えています。
大学祭の開催形態
昨年度の大学祭はオンラインと来校のハイブリッド型での実施でしたが、今年も両方開催する予定ではあるものの、対面での企画を中心に考え、一部をオンラインで中継する程度の予定です。
大学祭を通じて、地域の方々へ本学の日々の研究・教育を知ってもらう機会となり、SDGsを意識するきっかけのひとつになってもらえれば、嬉しく思います。
Webメディア「Future」について
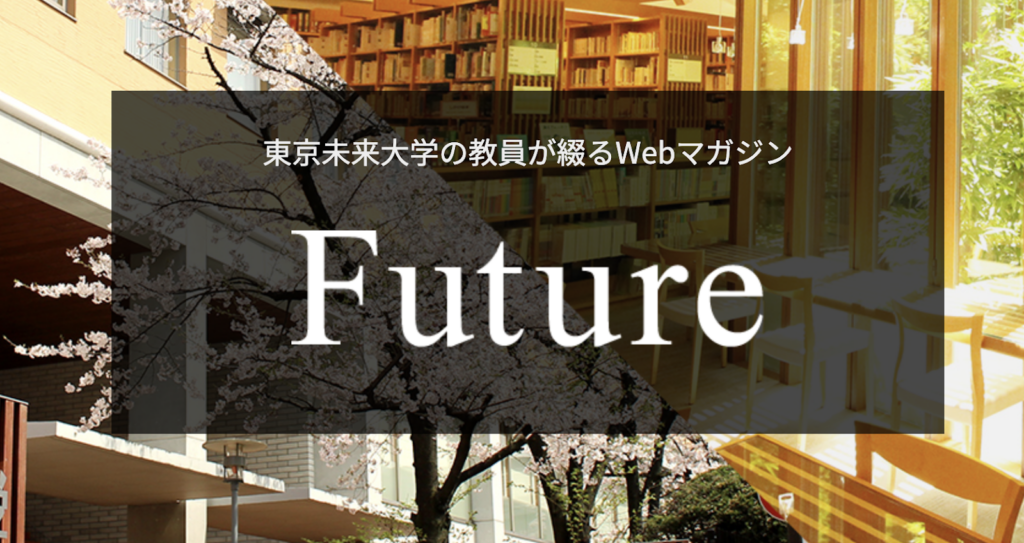
教員ブログのコンテンツは、開学当初から行っている取り組みではありました。
ブログメディアを通じて、教員の研究内容や個性といった、パンフレットやHPに掲載されていない、より深い情報を、高校生や保護者、高校教員の方に届けることを目的に立ち上げていました。
従来は、こども心理学部、モチベーション行動科学部、それぞれでブログコンテンツが存在しており、大学全体でWEBメディアの見直しをするタイミングで、学部それぞれのブログを統合する動きをとったことから、新たに「Future」という教員が綴るWEBマガジンの立ち上げをしました。
立ち上げのタイミングが、世の中にSDGsへの感心が高まっていた時期であったこともあり、本学としてもSDGsとの関わりを世に発信する場がなかったことから、WEBマガジンにSDGsの項目を紐づけて原稿を提供してもらうことで形にしていきました。
▼Webマガジン:Futureについてはこちら Future|東京未来大学の教員が綴るWebマガジン
メディアの運営における教職員との連携
実際に記事を書いているのは教員で、教員から提出のあった原稿を広報担当職員がWEB掲載を行っています。原稿を提出する際に、執筆内容がSDGsのどの項目に該当するのかを選択してもらっています。SDGsの取り組みを発信する機会・場とする目的に加え、本学としても、教員各々の研究内容やテーマがどのSDGsに該当するかを意識する一助にもなっていると考えています。
取り入れた後の成果・取り入れる前後での変化

大学祭における変化については、学生のSDGsの認知向上に繋がったように感じます。学生がSDGsについて発信する場所はやはり大学祭が大きいと思います。今年度は特にSDGsを全面に出す働きかけはしていませんが、学生たちの出展において自然とSDGsが意識されるようになったことは大きな変化だと受け取っています。
また、大学祭とは別に、「みらいプロデュース」という学生の企画コンペティションの取組みがあるのですが、新規提案企画の内容にSDGsの観点を取り入れた企画が増えるなど、学び観点の企画提案の中にSDGsのものがいくつかあったりもします。
学生は大学祭が、教員はWebメディアの発信が、それぞれSDGsを意識するきっかけとなっていますが、ブログのように定期的に更新される媒体においてSDGsに関連する記事を定期更新出来ることは、とても重要なコンテンツだと認識しています。
今後の展望や取り組み
ブログを通じ、SDGsとの繋がりを作っていくコンテンツを創っていく中で、二巡目に入った際にまた改めてSDGsを紐づけて考えるきっかけになったり、学生にアプローチをしてみようかななど、教員の内部的な意識づけが深まり、ブログで発信する内容もそこがより意識された内容に深まっていってほしいと思っています。
また、SDGsを視野に入れた活動が学生主体で広がっていくことにも期待しています。
大学祭を含めた学生との関わり
大学祭というところでは、学生自身がSDGsも含めた社会問題というものに対していかに自分事として捉えていけるかだと思っています。だからこそ自分が学んで将来に結びつく、というところを考えるとてもいいきっかけであると考えています。
したがって、今後そういったところを私たちが大学として仕掛けを考えることはもちろん、学生がもっとこんなことができる、あんなことができる、あそこはこういう風に変えられるかもしれないというような、学生が主体的に学び、主体的に大学生活を送れるようになっていけたらいいんではないかなと強く思います。
SDGsも然り、そのほかの社会問題は沢山あるなかで、自分で探求していき、これからの将来の課題感と、自身の進路を考えるきっかけのひとつとしてSDGsを益々広げていけるといいのではないかと考えています。
足立区内での大学連携強化
足立区内の大学連携も強化していきたい思いが区・大学ともにあるため、他大学との連携事業においてSDGsの取り組みが広がっていくことも視野に入れて検討したいと考えています。
足立区内には現在、6大学があります。どの大学も大学祭の実行委員などで学生同士が連携するということもあり、多くない大学数だからこそ、それ以外にもイベントなどで連携していきたいと思っています。
すでに情報交換や学友会自治委員会(大学を良くしていくことを目標とした委員会)の学生同士の定期的な交流はありますので、さらに連携を強化していくこと、学生発のSDGsへの理解を求める活動や意識をした活動が積極的に増えていくことに期待しています。
