
SDGs 大学プロジェクト × Osaka Seikei Univ.
目次
大阪成蹊学園について

大阪成蹊学園は、1933年の創立から90年以上にわたる歴史と伝統を誇る総合学園です。幼稚園から大学まで多岐にわたる教育機関を展開し、約7,700名の在籍者と約640名の専任教職員が所属しています。創設以来、「桃李不言下自成蹊」の精神のもと、多角的な知識と実践力、そして「人間力」を備えた人材の育成に努めています。
学生が主体的に学ぶことを支援する「LCD教育プログラム」を導入し、アクティブラーニングを全面的に展開しています。特に、産官学連携プロジェクトや課題解決型学習(PBL)を積極的に取り入れ、実社会と直結した学びの場を提供。企業や地域社会と協力し、学生が現場での実践力を養える環境を整えています。
大阪成蹊大学では2023年4月にデータサイエンス学部や看護学部を新設し、文・理・芸にわたる幅広い分野で専門性と応用力を培う教育を推進し、次代を担う人材が多様なフィールドで活躍できるようサポートしています。
大阪成蹊大学×企業の挑戦! 新たな黒ごまコンビニスイーツの誕生
― 昨年、株式会社ローソンと株式会社和田萬と共同で開発された『スプーンで食べる 黒ごまレアチーズケーキ』は、どのような経緯で誕生したのでしょうか?
大久保 結衣さん(以下、大久保さん):私たちは、同じ髙畑ゼミに所属しています。配属後すぐに、まずはどの企業と連携したいかについて話し合う機会がありました。
私はかねてより「商品開発に挑戦してみたい」という思いがあり、候補企業の中から和田萬さんを第一希望に挙げていました。一方で、南野さんも同じく商品開発に興味があり、ローソンさんを希望していたんです。
髙畑先生の後押しもあり、2人でペアを組んで商品開発に取り組むことが決まりました。その後、ローソンさんや和田萬さんからアドバイスを受けつつ、2人でアイデアを出し合いながら3回の商品の企画提案を行い、最終的に南野さんが提案した「黒ごまレアチーズケーキ」が採用されました。
▼大阪成蹊大学HP 私たち”らしさ”全開!大阪成蹊大学の学生が産学連携により『かわいいスイーツ』を共同開発し、人も、地球も、ハッピーに!

― このアイデアの決め手となったエピソードはありますか?
南野 愛優花さん(以下、南野さん):黒ごまレアチーズケーキのアイデアに至るまでには、2人で「どのような商品を開発したいか」について話し合いを重ねました。そこで、「コンビニで売るなら、やっぱりスイーツを作りたい」と意見が一致したんです。
次に、コンビニで販売されているさまざまなスイーツを調査し、消費者に喜ばれる商品とはどのようなものなのかをリサーチしました。その過程で、「ごまの風味とチーズは合うかもしれない」という発想が生まれ、2回目の提案でこのアイデアを出しました。企業の方々から良い反応をいただけた時は、本当に嬉しかったです。
― 最初の提案から商品が発売されるまで、どのくらいの期間かかりましたか?
南野さん:最初にローソンさんへ企画を提案したのが3月で、商品が販売され店頭に並んだのが10月です。8月末までに商品を完成させる必要があったので、開発には約5ヶ月かかりました。
髙畑 能久教授(以下、髙畑教授):2年生の11月にゼミの配属や連携企業が決まり、12月頃からすでに準備を始めていました。2人は12月に和田萬さんと最初のキックオフミーティングを行い、その後は店舗や工場へ見学に行くなど、積極的に活動していましたよね。
8月に商品が完成した後も、10月3日の発売に向け、店頭POPの制作や大学祭でのイベント企画、お客様へのアンケート調査など、コラボ商品に関する活動に1年弱の時間をかけて全力で取り組んでくれました。

― 学外の企業と共同での商品開発は、お二人にとって初めてだったのでしょうか?
南野さん:はい、初めてでした。商品開発だけでなく、企業の方々との連携も初めてだったので、最初は言葉遣いやマナーについて戸惑うことが多かったです。
髙畑教授にメールの内容を添削していただいたり、適切な話し方をご指導いただいたりしながら、少しずつ経験を積むことができました。
髙畑教授:本学の経営学部 食ビジネスコースでは、栄養学や調理学などもカリキュラムに組み込まれています。例えば、プロの調理師の指導を受けたり、フードコーディネーターの資格を目指せる課程も用意されています。
一般的な経営学部のイメージとは少し異なり、文理融合型で食ビジネスに関する専門知識を学べる点が本コースの特長です。こうした学びがあるからこそ、今回のような商品開発が実現できたと思っています。
▼大阪成蹊大学HP 大阪成蹊大学 経営学部 経営学科 食ビジネスコース紹介ページ
ゼロから挑んだ商品開発、学生たちが手がけた商品の魅力
―商品の特長やこだわりについて教えていただけますか?
南野さん:アイデアを練るなかで、商品にはかわいらしさと贅沢感を持たせながらも、手に取りやすい価格設定も大切だという結論に至り、「かわいい・贅沢感・お値打ち」の3つを重視しました。
どうすればこれらの観点がお客様に伝わるかを考えながら、開発を進めました。例えば「かわいらしさ」では、チーズケーキの上にマーブル模様を描いたり、ピンクのパッケージで視覚的な可愛さを詰め込みました。
「贅沢感」については、和田萬さんこだわりの黒いりごま・黒ごまペースト・脱脂黒ごまの3種類使っている点がポイントです。特に、ごま油を絞った後に残る脱脂黒ごまを使うことで、素材の良さを引き出しつつ、価格を抑えられました。
品質を保ちながらお手頃な価格になるよう、企業の方々と工夫を重ね、誰でも気軽に楽しんでもらえる商品が実現できたと思っています。
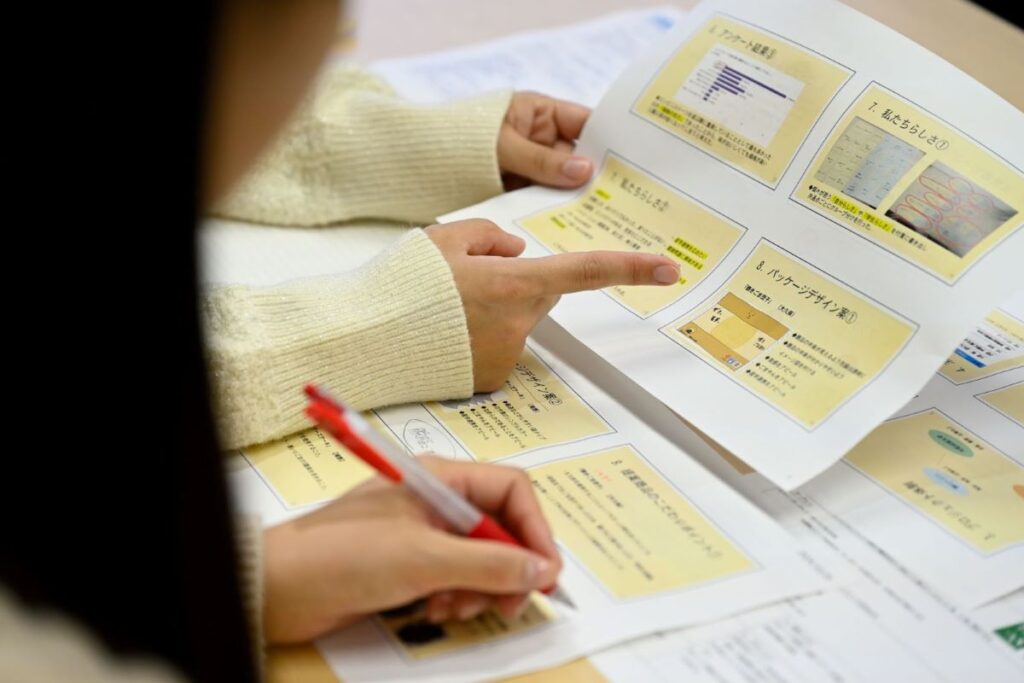
― 特に気に入っているポイントについても、ぜひ教えてください。
南野さん:レシピはもちろんですが、パッケージにもこだわりました。まず初めにお客様の目に入る部分ですし、パッケージ買いする方も多いですよね。私たちの似顔絵を入れたり、ピンクを基調としたデザインに仕上げたことで、かわいらしく目に留まりやすくできた点が気に入っています。
大久保さん:すべて気に入っているのですが、特に気に入っているのは、ローソンさんや和田萬さんと何度も試食を重ねて完成させた、ケーキの食感と味です。ケーキの一番下にクランチを敷き、その上にレアチーズケーキを重ねています。
普通のレアチーズケーキとは一味違い、クランチ層のザクザクした食感も楽しめるところを特に気に入っています。

― この商品にはSDGsの要素も取り入れられているようですが、そのきっかけや経緯について教えていただけますか?
南野さん:SDGsについては、テレビや授業を通して少し知っていた程度でした。
そうした中、和田萬さんの工場見学で「ごま油を作る際に残る搾りかす(脱脂黒ごま)は使い切れず廃棄したり、家畜の飼料に使われています」というお話を聞きました。その場で脱脂黒ごまを試食させていただいたところ、香りや味が普通のごまと変わらず、とても美味しかったんです。
これをただ廃棄してしまうのはもったいないと感じ、脱脂黒ごまを商品にうまく活用できないかを2人で考える中で、商品を通じてSDGsやアップサイクル食品を知ってもらうきっかけになればという想いが生まれました。
大久保さん:この商品開発を通じて、脱脂黒ごまのように、まだ活用できるのに捨てられてしまう食材が多くあることを知りました。また、アップサイクル食品の認知度はまだまだ低いことも実感しました。
私も、商品や今後の取り組みを通じて、もっと多くの方にSDGsやアップサイクル食品について知ってもらいたいという想いを持つようになりました。
無我夢中の挑戦! 商品開発で発揮した力と新たな視点の発見
― 今回の商品開発において、「ここに力を発揮できた!」と感じられた工程や、印象に残っている役割はどんなところですか?
南野さん:私たちは商品開発の経験がなかったので、最初は「どこまで任せてもらえるのだろう?」という思いがありました。しかし実際には、工場見学から始まり、商品のアイデア出し、イメージ図や価格設定を含めた商品提案、試食やパッケージデザインなど、さまざまな工程に関わることができました。
特に印象に残っているのは、官能評価です。家族や友達以外の企業の方に試作品を試食していただき、率直な意見を聞くことができました。自分たちは「良い」と思っていた点も、他の人の意見を聞くことで新たな視点に気づかされ、とても良い経験になりました。
こうした評価をもとに、最終的に商品を発売できたことはもちろん、官能評価自体が非常に貴重な経験として心に残っています。

大久保さん:商品が完成するまで、2人でさまざまなことに挑戦しました。中でも一番心に残っているのは、やはり完成したパッケージや中身を目にした瞬間です。それまでの努力が形になったことを実感し、とても達成感がありました。
髙畑教授:2人は無我夢中で取り組んでいたので気づかなかったかもしれませんが、彼女たちの頑張る姿や成果をゼミで紹介することで、他の学生たちにも良い刺激を与えていたと思います。
また、毎年3,000人以上が来場する大学祭では、初めてのイベントを企画しました。この活動はメディアにも取り上げられ、ホームページでも紹介されるなど、PR効果も大きかったですね。
特にZ世代の間では、アップサイクル食品の認知度が低い面があります。ごまの栄養面についても、若い世代にはあまり知られていませんでした。今回の取り組みを通じてそうした知識も広まり、和田萬さんからも感謝の言葉をいただきました。
本商品に使われている脱脂ごまは、搾りかすと言えど、きちんと衛生管理されている食材です。和田萬さんからは、「家畜の餌や肥料ではなく、食品として活用できないだろうか」という要望をいただいていました。
今回の商品開発を通じて、そのニーズに応えることができたと思います。この実績がきっかけとなり、今後は脱脂ごまを活用した商品がさらに広がっていくことを期待しています。
また、ローソンさんとは売上目標も設定していました。実は、先輩にあたる代では目標を達成できなかったのですが、2人は見事クリアしました。学生だからといって甘くならず、プロ目線での目標を達成したことで、ローソンさんからも称賛の言葉をいただきました。

― 商品の発売後、周囲の方々からの感想や、企業担当者の方からフィードバックはありましたか?
南野さん:家族と一緒にお店に買いに行き、実際に食べてもらっただけでなく、ゼミの友人やバイト先の方々からも感想をいただいたりして、とても嬉しかったです。
商品が完成するまでの過程では、ローソンの部長さんから厳しめのご意見をいただくこともあり、悩んだ時期もありましたが、それを乗り越えたからこそ「商品をたくさん売りたい!」という強い気持ちが生まれました。また、「チーム全員で成功させたい」という思いを共有できたことも、大きな励みになりました。
「伝える力」を学んだ商品開発 挑戦と経験がもたらした成長
― 今回の商品開発を通じて、身に付いたスキルや経験は何ですか? また、その経験が活かされたエピソードがあれば教えてください。
大久保さん:自分の考えを、相手にわかりやすく伝えることの大切さを学びました。言葉選びや表現を工夫することで、自分の考えを相手にしっかり伝えられるようになったと思います。
また、開発中には厳しい意見をいただくこともありましたが、どうしても実現させたいという強い気持ちも相まって、諦めずに最後までやり抜く力も身につきました。
この経験は、就職活動にも大きく役立ちました。面接でも、自分の思いをどのように伝えるかが重要です。緊張しながらも、商品開発で培った「伝える力」を活かし、自分の意思をしっかり伝えられたと感じています。
髙畑教授:日本のごまの自給率は0.01%以下と非常に低く、ほとんどが輸入に頼っています。和田萬さんは国産ごまを守ろうとされており、2人も実際にごまの収穫体験をさせていただきました。この貴重な体験は、一緒に収穫に参加した他のゼミ生にも良い刺激になったと思います。

また、和田萬さんが運営するカフェのシェアキッチンを借りて、大久保さんが提案した「ごま団子」を1日限定で提供するイベントも行いました。このイベントは、商品開発がきっかけで生まれた取り組みです。
商品開発において、考えたすべてのアイデアが商品化されるわけではありませんが、それでも自分のアイデアが形にならないことは残念ですよね。自らのアイデアを実現できたことは、彼女たちにとっても大きな達成感になったと思います。
大久保さん:今回、私たちは2人で一つの商品開発に取り組んだため、私が提案した企画は残念ながら商品化されませんでしたが、和田萬さんから「ごま団子のアイデアも実現したい」と声をかけていただいたんです。
南野さんと一緒に「生姜焼き定食」を考案し、シェアキッチンをお借りしてお客様に提供しました。その際、デザートとして私が提案したごま団子を提供することができたので、商品化には至らなかったものの、この取り組みに悔いはないと感じています。
― 今回の経験を通じて、日常生活に何か変化はありましたか?
南野さん:大久保さんと私は、キャンパス近くのローソンでよくスイーツを買うのですが、商品開発を経験してからは、まずパッケージの裏を見て、原材料や成分表示をチェックして楽しむようになりました。
以前はあまり注目していませんでしたが、商品の裏に隠されたこだわりや材料に関心を持つようになりました。これは、まさに今回の経験から得られた新しい視点だと感じています。

今後の展望
― 今回の経験を踏まえ、これから挑戦したいことや目標について教えてください。
南野さん:今回の商品開発の経験は、私の将来にとても大きな影響を与えてくれました。初めて一から商品を作り、挫折しそうになったり、厳しい意見を受けて落ち込むこともありましたが、2人で力を合わせて乗り越える中で、達成感や楽しさを実感しました。
もともと食に興味があったのですが、「商品開発職」という具体的な道を考えたことはなかったんです。しかし、全員で商品を作り上げることの魅力を知り、「将来はこの分野で社会に貢献したい」と思うようになりました。
自分のアイデアが形となって世の中に広がっていくことはは大きな喜びであり、自信にもつながると感じています。私は食品業界へと進む予定ですが、将来的には商品開発に携わることのできる部門に進みたいと考えています。
大久保さん:私は南野さんとは異なる業界に進む予定ですが、今回の経験で身についた「自分の意見を伝える力」や「効率よく動く力」は、どの業界でも重要だと感じています。
商品開発を通じて、限られた時間の中で効率よく動き、自分の考えをどのように相手に伝えるかといったスキルを磨くことができました。これから社会に出て働くなかでも、このようなスキルは必要になるはずなので、今後も大学生活やその後のキャリアで活かし、さらに伸ばしていきたいです。
