
SDGs 大学プロジェクト × Tokiwa Univ.
常磐大学の紹介

常磐大学は、「実学を重んじ真摯な態度を身につけた人間を育てる」という建学の精神を掲げる学校法人常磐大学が設置する高等教育機関として、茨城県水戸市に1983年に人間科学部を擁して開学。以後、2017年に総合政策学部、2018年度に看護学部を開設し、現在、3学部9学科に約3,000人の学生が学んでいます。教育理念に「自立・創造・真摯」を謳い、人間の本質に迫る学際的なカリキュラムと、現代社会が直面する諸問題に対し具体的な解決策を提示する総合的なカリキュラムを通し、豊かな国際感覚で問題を捉え、社会や地域に貢献できる社会適応力や課題解決につながる社会活動力を身につける実践的な学び、まさに「実学」を提供しています。
地域連携分野では、とりわけ産学官民連携を重視し、県内のさまざまな企業体や地方自治体、各種団体と連携した取り組みに注力。県内主要企業の経営者による授業や自治体職員を招いての講座も定評を得ています。また、ゼミナール活動の一環として、地元のスーパーやメーカーと共同で地産地消の商品開発に挑戦したり、プロジェクト型授業を通してSDGsの視点から地域の課題解決に導いたりする実践例も増えています。
国際交流の分野においても、学術連携協定を締結する大学を増やし、学部共通科目として実施される「海外研修」は、開講時期や研修先、研修内容を多様化しました。研修受入先の海外の学生とともに地域の課題解決に取り組む研修も創出されています。「交換留学制度」による海外留学では、派遣学生それぞれがSDGsのいずれかのゴールに紐づけた目標を設定し、日本と留学先の共通課題を見い出し、現地での調査や実践的な活動に取り組んでいます。国際交流活動は、学生の短期・長期の派遣や受入に留まらず、今では、オンラインでの交流が身近に実現され、参加学生の視野も人的なネットワークも国境を超えて広がりを見せています。
これからの社会が地球規模でさらに大きく変動していくことが想定される中、常磐大学は、学生一人ひとりが、広い教養や専門的知識とともに、主体性、創造性、柔軟性、発信力、他者を巻き込む力、といった時代の変化を生き抜く力も備え、それぞれの夢を実現するのと同時に、地域社会にも貢献できる人材となるよう、これからも最大限サポートしていきます。
SDGsへの取り組みの背景
常磐大学が「トキワ de SDGs」を掲げ、「常磐大学・常磐短期大学SDGs宣言」を採択するに至った秘話を紹介します。
国連勤務時代にSDGs策定に携わった富田敬子学長によるイニシアティブ
2019年 4月に常磐大学学長に就任した富田敬子学長は、前職である国連経済社会局統計部次長時代、2015年 9月の国連サミットにおいて全会一致で採択されたSDGsの策定に深く関わりました。国連は、2001年、2015年を達成期限に、とりわけ途上国と先進国の格差解消を目指して、途上国への取り組みを重視したミレニアム目標を掲げましたが、達成状況に反省と課題が残りました。
SDGsは、ミレニアム目標を継承・発展する形で、2030年の達成期限までに、世界のあらゆる形態の貧困を撲滅し、すべての人が平等な機会を享受し、地球環境を壊さずに、よりよい生活を送ることができるようになることを目指し策定されたもので、先進国を含めて、政府、自治体、民間セクター、市民社会など、あらゆる社会の構成単位、そして一人ひとりの支援と協力が不可欠となることが謳われました。
17のゴールのもとに169のターゲット、さらに232の指標が設定され、達成状況の評価手法も打ち出されました。採択に至る過程では、国連加盟国政府のみならず、主要国の経済界も早い段階で巻き込み、社会のあらゆるステークホルダーが、ゴール達成に向けて連携をとりながら取り組む構図を示したことで、日本においても、国・自治体のみならず、民間企業やあらゆるレベルの教育機関がSDGs推進の主体として意識され、メディアでも盛んに取り上げられるようになり、SDGsの認知度が急速に高まりました。
富田敬子学長は、SDGsを生みだした国連のまさに中核的な役割の一翼を担い、様々な利害をもつ各国の国連代表団との難しい交渉にも臨んだ、SDGsの舞台裏を知る人物。こうした経歴をもつ富田敬子学長のイニシアティブのもと、常磐大学は、2019年8月、教育機関によるSDGsの世界的な推進を目的に国連が設置した国連アカデミック・インパクト(United Nations Academic Impact=UNAI)に加盟。さらに、2020年4月には、「トキワ de SDGs」を掲げ、「常磐大学・常磐短期大学SDGs宣言」を採択。SDGs推進のロゴも制作し、大学HPにSDGs推進の特設ページを開設し、全学的に取り組むSDGsの活動について情報発信を行っています。
★トキワ de SDGsロゴ(人間科学部コミュニケーション学科 小佐原孝幸 准教授によるデザイン)

▼SDGs推進専用ページはこちら トキワ de SDGs | 常磐大学・常磐短期大学
SDGs施策の内容
「常磐大学・常磐短期大学SDGs宣言」に基づく全学的なSDGsへの取り組みを紹介します。
「全学国際化推進会議」で策定されるSDGsの全学的方針とImpact Ranking への参加
常磐大学では、「全学国際化推進会議」が、SDGsに係る方針策定を担い、さらに毎年度の進捗状況や活動内容を確認・評価する学内機関として機能しています。「常磐大学・常磐短期大学SDGs宣言」により、教職員全員にSDGsの推進、すなわちSDGsの視点での従来事業の見直しや新規事業の取り組み、を呼びかけ、2020年度より、17のゴール全てを網羅した「常磐大学 SDGs関連事業報告書」を取りまとめ、HPで公表しています。
また、2021年度から、世界大学ランキングを手掛けるTimes Higher Education (THE)が主催する、大学のSDGs推進への貢献度を示す「Impact Rankings」にも参加。「Impact Rankings 2022」、「Impact Rankings 2023」にエントリーし、常磐大学は、両年度とも、「1000+」にランキングされました。「Impact Rankings 2023」では、総合得点45.6と前年度より3.2ポイントアップ。とりわけゴール3(すべての人に健康と福祉を)の得点57.2が、エントリーした4つのゴールの中で最も高く、「401-600」にランク付けされ、健康・福祉分野が常磐大学の強みであることが確認されました。
すべての授業をSDGsのゴールに紐づける~履修系統図・シラバスに関連するSDGsを明記
常磐大学は、2020年2月、全学自己点検・評価委員会主催SD研修会を「SDGsと地方大学」と題して全教職員を対象に開催。国連機関の専門家や地域企業のリーダーを招き、地方大学と地域社会の様々な構成員が、SDGs達成に向けどのような連携・協力が可能か、そのための方策と課題を共有する機会を設けました。
この研修において、SDGsの達成には、新規事業を立ち上げるばかりでなく、既存の様々な取り組みを、SDGsに関連づけて新たな視点を付与し、課題解決に向けたプロセスと手法を明らかにすることの重要性を確認。17のゴール達成には、あらゆる事象が相互に繋がりあい、影響を及ぼし合っていることを誰もが理解し、自身の生活にSDGsに関連するアクションを可能なところから少しずつでも取り入れることが提唱されました。
常磐大学では、こうしたSDGs推進への姿勢を土台に、2022年度に、すべての授業をSDGsのゴールに紐づけ、履修系統図に反映することを決定。これにより、常磐大学が開講する大学の授業すべてに、SDGsの17のゴールのいずれかが関連づけられ、可視化されることになりました。2024年度からは、シラバスにもSDGsの関連ゴールを記載する準備が進められ、学生は、授業とSDGsの関係性をより明確に認識することが可能となります。
SDGsの啓発・普及に関わる事業を学内外で展開
SDGsの地域での推進に、大学が重要な役割を担っていることを踏まえ、常磐大学は、常磐大学独自に、SDGsの啓発・普及に関わるシンポジウムを市民へ参加を呼びかけて開催してきました。また、茨城大学、茨城キリスト教大学、等、茨城県内の大学や、水戸市をはじめとする地域の自治体とも連携し、SDGsを直接的に掲げた事業に加え、17のいずれかのゴールに関連する研修・啓発事業にも広く取り組んでいます。
また、2013年度から実施している「TOKIWA 高校生英語プレゼンテーションコンテスト」では、2021年度から、全体テーマをSDGsの推進に結び付け、各参加生徒は、SDGsのいずれかのゴールと関連づけ、関心のある分野での独自調査や自身の実体験に基づく内容を英語で披露します。2021年度よりオンラインでの実施となり、全国各地から参加生徒を迎え、レベルの高いコンテストとなっています。


<常磐大学の主な独自事業>
- オンライン・シンポジウム 「With コロナ時代のSDGs」(2020年11月)
- 常磐大学 社会安全政策研究所主催 第3回茨城社会安全政策研究会「世界及び茨城県におけるSDGsからみた被害者の保護・支援」(2021年1月)。
- オープンカレッジ「高校生×SDGs講座」(講師:富田敬子学長)(2021年9月)
- 若手社員研修「石の上にも3年!セミナー2022」(関連ゴール8:=働きがいも経済成長も、11:住み続けられるまちづくりを、17:パートナーシップ)(2022年9月)
- TOKIWA高校生英語プレゼンテーションコンテスト:My Actions for Advancing SDGs(2022年10月)
<他大学・自治体等との連携事業>
- 「SDGs達成に向けた地域・大学のアクションを考える~茨城大・常磐大・茨城キリスト教大の学長が語る」(2019年7月)
- 茨城大学・常磐大学連携シンポジウム「地域の未来にSDGsをどう活かせるか-大学の役割と実践の知恵」(講師:京都精華大学前学長ウスビ・サコ氏)(2021年11月)

-1024x819.png)
- 水戸市主催、茨城大学・常磐大学共催「ヒューマンライフシンポジウム2022未来へつなぐメッセージ」(2022年10月)
<第1部> 「共に生きるとは何かー難民の声、家族の歴史から考えた多様性―」(講師:フォトジャーナリスト・安田菜津紀氏)
<第2部> SDGs×地域×ジェンダー、安田氏と学生との対談
- 水戸市主催、茨城大学・常磐大学・茨城キリスト教大学共催「ヒューマンライフシンポジウム2023」(2023年9月開催予定)
<第1部> 「SDGsから日本の未来を考える」(講師:フリージャーナリスト・池上彰氏)
<第2部> パネルディスカッション「激論!池上彰×大学生『若者はなぜ怒らない?』」
上記のような啓発・普及に関わる事業の開催のほか、自治体や経済団体、企業、市民団体、等に、SDGsの方針策定や実践活動の導入について、富田敬子学長はじめ、複数の教員を講師として派遣しています。また、地域の小・中学校や高等学校のSDGs理解促進に向けた取り組みもサポートし、地域の小・中学生や高校生をキャンパスに受け入れ、それぞれのニーズにあったプログラムを提供しています。
2020年度から毎年、県立緑岡高等学校の海外短期留学プログラム(バンクーバー研修)の事前学習を本学で実施。SDGsや多文化共生をテーマに学びを深める機会も提供しています。
SDGS施策と学生とのつながりについて
授業や課外活動を通して、実践的に地域社会の課題にアプローチした事例を紹介します。
1年生必修授業「学びの技法II」でSDGs関連文献購読
常磐大学は、2023年度から、全学部1年生の必修授業「学びの技法II」の1コマをSDGsの理解に割り当て、1年生全員がSDGsの基本的な概念や指標を学びます。大学生の中には、中学、高校時代からすでにSDGsについて学びの機会を得ている人も多くなりましたが、改めてカリキュラムの中でSDGsの基本的な概念を学び、4年間を通して、より自身の関心や専門的な学びと関連の深いテーマをみつけ、実践的な授業の履修へ発展させていくことを目的とします。
SDGsをテーマに「アクション」を導く授業の展開
全学部・全学年の学生が履修できる演習型授業「プロジェクトA/C」では、「キャンパスから始めるSDGs:地球市民として生きるために」というサブタイトルのもと、課題解決・実践型の授業が展開されています。
春セメスターには、SDGsについて包括的に理解を深めつつ、グループ毎にキャンパス内でSDGsいずれかのゴールに関連する課題を発見し、解決に導くためのミニプロジェクトを策定・実施したうえで、成果を報告します。
さらに秋セメスターには、受講者全員で取り組む「アクション」を設定。授業の中で、問題意識、行動、課題を明らかにし、課題解決に向けた行動計画に沿って実践します。同時に、取り組んだアクションの学内周知や広報手段も検討して、最後に大会場で成果を披露します。
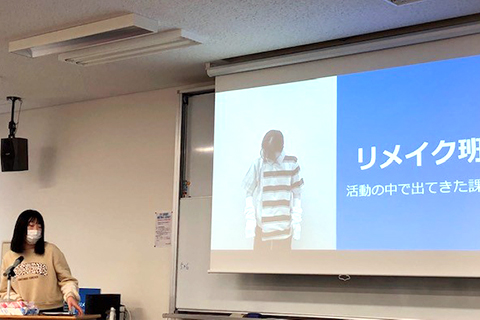
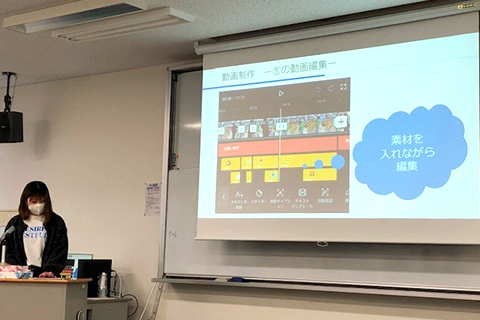
2022年度の「キャンパスから始めるSDGs」では、履修学生が自分たちのファッションから持続可能な服について学び、「Rethinking Our Fashion」をテーマに、衣類の大量生産・大量消費・大量廃棄の問題を取り上げ、衣類に関する学生の意識調査、着られなくなった服のリメイク、ファッションショーの開催、古着を利用したエコバックづくりや作品展示に取り組みました。
2023年2月1日に学内で報告会を開催し、「服」をテーマにした学びから「大量消費・大量廃棄社会」への意識が変容し、今後の日常生活における行動にも影響がもたらされたことが共有されました。
「上級英語」「選択英語C」で、英語を学びながらSDGs推進のアクションに取り組む
総合政策学部総合政策学科の小関一也准教授と人間科学部コミュニケーション学科のKevin M. McManus准教授が、共著で出版した英語のテキスト『Living as Global Citizens: An Introduction to the Sustainable Development Goals』(地球市民として生きる:英語で学ぶSDGs実践入門)(南雲堂、2021年)を教科書に用います。
英語de SDGsをコンセプトに、世界の水、貧困、飢餓、大量消費・大量廃棄社会、の現状と課題を学び、日常生活に何らかの変容をもたらすアクション・プランを作成、実践して報告することで、SDGsに関連する英語の習得と同時に、自身の生活を振り返りながら、SDGsへの理解と行動が履修学生に求められます。
専門の学びから地域の課題解決につなげる
ゼミナールで実践的な学びにつなげた事例を紹介します。
健康栄養学科飯村ゼミナールによる産学連携での商品開発
茨城県の基幹産業とも言える水産業や農業。常磐大学は、2020年9月から「若者の魚離れ解消」をテーマにいばらきの地魚取扱店認証委員会と連携協力をし、「いばらきの地魚プロジェクト」に取り組んできました。
人間科学部健康栄養学科の飯村裕子ゼミナールは、株式会社ヨークベニマルの協力のもと、全国トップクラスの漁獲量の日立鹿島沖水揚げサバを使用した「IBARAKI SABA CURRY」「IBARAKI SABA TOMATO」を共同開発。10月に県内のヨークベニマルの店舗で発売され、今なお高い評判を得ています。


2022年度には、株式会社マルトとの産学連携により、地元メーカーの協力も得て、「野菜摂取量の増加」をテーマに商品開発プロジェクトに着手。茨城県産野菜を使用した3つの商品-「茨城県産水菜を使ったフレッシュサラダ」、「推し野菜餃子~チャンハイプロデュース~」、「ど~ら野菜足りてないでしょ?」を開発し、2022年11月、商品発表会を行いました。
若者の健康面から課題を見出し、その課題の解決・解消に貢献する商品を、地域の産物を活用して企画。試行錯誤を繰り返し、商品として消費者の手に届くまでを見届けるプロセスを体験した学生は、達成感を得たと同時に、社会人に求められるプロとしての責任感やも学び、次なる目標への挑戦を目指しています。
法律行政学科吉田ゼミナールによる「地方自治力向上プロジェクト」

常磐大学「地方自治力向上プロジェクト」は、総合政策学部法律行政学科の吉田勉ゼミナール学生が中心となり、地方自治、自治体、公務員等に関心の高い学生が、自治体職員、首長、市民団体等との間で意見交換、議論などをする機会を自ら作り、交流していくことで、学びを深めるプロジェクト。
2015年度から、住民投票、人口減少社会、女性活躍、自治体魅力度、コロナ禍での大学、自治体職員の在り方、等をテーマに、毎年、企画から準備、運営のすべてを学生が担う形でシンポジウムを開催してきました。
2022年度は、「二元代表制を極める!シンポジウム~地方議会はどこへ行く?」と題し、2023年1月に開催。前半は、学生が、議会と首長の関係について1年間調査した成果を発表。続く後半は、水戸市長、茨城県議会議員、笠間市議会議員、取手市議会事務局長らを招いて「二元代表制のあるべき姿とは?」をテーマにパネルディスカッションを実施し、会場に参加した聴衆とともに、未来の自治体行政の在り方について考えを深めました。
海外研修(フィリピン研修)で協定校の学生とともにネグロス島の課題解決に取り組む

常磐大学は、フィリピンの学術連携協定校であるバゴ市立大学(西ネグロス州バゴ市)と公益財団法人オイスカが現地で運営するオイスカ・バゴ研修センターの協力を得て、2016年度から、全学部・全学年を対象とした「海外研修」プログラムの1つとして、フィリピン研修を実施してきました。
フィリピン研修は、単なる語学研修や異文化体験のみでなく、西ネグロス州の人々を取り巻く様々な課題に着目し、事前学習段階から課題の解決に向けて学びを深め、現地研修中、協定校学生とともに課題に関連した活動に取り組み、発表・報告を行う一連の流れを主軸にしています。
2022年度(2023年2月)に実施したフィリピン研修では、「フェアトレード・プロジェクト」、「教材再生プロジェクト」、「マングローブ・プロジェクト」等5つのプロジェクトを企画。「フェアトレード・プロジェクト」では、オイスカの指導の下、新しい産業として西ネグロス州で生産が広まっている絹糸・絹織物を材料に日本でも販売が見込める商品を提案。
「教材再生プロジェクト」では、大学近隣の小・中学校から寄せられた古いリコーダーなどを消毒して持参し、現地の小学校に寄贈。持参した楽器を用いて音楽ワークショップを行いました。
「マングローブ・プロジェクト」では、地球温暖化の影響を受けて海岸線に変容がみられる地域で、環境保全活動を行っている専門家から指導を受けながら、マングローブの苗木の植林に取り組みました。常磐大学の学生一人ひとりに現地学生がバディとしてサポート。それぞれに深い絆が結ばれ、友好関係は今も続いています。
SDGS施策を取り入れたことによる意識の変化・成果
教職員・学生の意識の変化について、触れていきます。
教職員の意識変化と成果

常磐大学では、従来、教養科目として設置されている「生態学(生態学入門)」や「物質とエネルギー(地球システム科学入門)」といった授業や、SDGsをテーマにした「プロジェクト」科目を通し、授業を履修する学生にSDGsへの理解を深める学びを提供してきました。
しかしながら、シラバスにSDGsとの関連を謳っているのはごく一部で、学生への学びの機会が広がらないことから、2023年度より、全学部の1年次必修科目である「学びの技法Ⅱ」でSDGsを取り扱う時間を設け、常磐大学のすべての学生が、SDGsの基本的な概念を理解する仕組みを構築しました。
並行して、常磐大学が開講する授業すべてをSDGsのいずれかのゴールに紐づけ履修系統図を整備し、さらに2024年度からシラバスにも明記することを機関決定したことで、SDGsの推進が大学での学びに直結している、という意識が教職員全体に共有されました。
また、「常磐大学SDGs関連事業報告書」の取りまとめ作業では、全教職員に情報提供と掲載内容の確認作業を呼び掛けることで、事務職員にも、所属する部署でSDGsに関連する取り組みを開始したり、情報を積極的に共有する動きが広がりました。図書館を所管する情報メディアセンターは、SDGs関連図書コーナーを設置。また、キャンパス内の環境整備を所管する部署は、構内の緑の保全に努め、定期的に情報をHP上で発信しています。
学生の意識変化と成果

SDGsがこれからの地域社会や日本、さらには地球の持続可能性を維持するための鍵となることを理解し、SDGsの推進を必ずしも当初から意識していたわけではなかった学生サークルが、SDGsにつながる地域の課題解決をめざし、学内外で活発に活動を展開しています。
「M4(エムフォー)」は、ひたちなか市那珂湊地区を中心に、アート デザイン ワークショップを通してまちづくり活動に取り組む学生サークル。アートプロジェクト「みなとメディアミュージアム(MMM)」に携り、市役所の空家等対策推進室からの依頼を受けて、那珂湊地区の空き家を地域交流拠点「みなへそ」として再生させました。
「SDGs」という言葉の冠はなくても、貧困、教育、福祉、まちづくり、といった社会の様々な課題に積極的に向き合い、地域のステークホルダーと繋がりながら活動を発展させている学生の姿に、教職員も刺激を受けています。
今後の施策
2030年を達成目標としているSDGsも、策定されてからすでに7年が経過し、折り返し地点に差し掛かっています。2019年末に始まった新型コロナウイルス感染症による世界的なパンデミック、さらにコロナが収束をみないうちに突然始まった2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻が、地球規模の危機となって、市民生活のあらゆる側面に影響を及ぼし、SDGsの進捗にも深刻な遅れが生じていると言われています。
SDGs推進の重要性に、学内での認識が広がる一方で、学生の中には、まだ自分事として理解が深まっていない状況も、直近で行われた学生意識調査から見て取れます。「既存の取り組みはすべて、SDGsのいずれかのゴールに対応する」、という消極的な発想から、「既存の取り組みを、SDGsのいずれかのゴールに対応させることで、課題と解決へのアクションを見出し、実際の行動に繋げる」、という積極的な思考に、教職員と学生が転換できるよう、学部共通科目の「学びの技法Ⅱ」や「プロジェクト」科目と学部・学科別の専門科目を組み上げたロードマップを可視化し、SDGsの視点で学生に提示していく必要性も感じています。
学生ひとりひとりが、卒業までの4年間にSDGsの具体的なアクションを意識し、実践できるような仕組みづくりを急ピッチで整え、2030年までの残り期間、常磐大学の学生が、社会に出て、SDGsが目指す「誰も取り残さない」社会の実現にそれぞれのフィールドで貢献できるよう、常磐大学はさらなる取り組みを続けます。
