
SDGs 大学プロジェクト × Tohoku University of Community Service and Science. -Part 1-
目次
東北公益文科大学の紹介
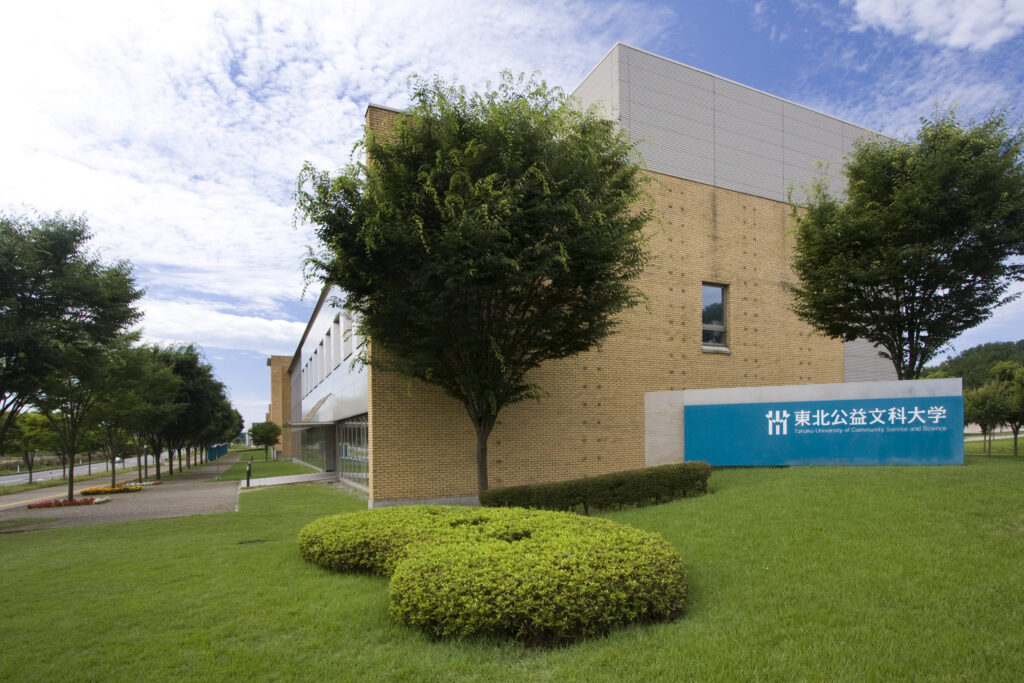
東北公益文科大学は、「この地に四年制大学を!」という地域の皆さんからの熱い要望を受けて、当時の山形県と庄内地域14市町村が出資する公設民営方式で、山形県酒田市に2001年に開学しました。
学びの大きな特長は、「他大学にはない“公益”を理念として、1つの学部の中で文系・理系両方を学ぶことができ、情報科目を全員が必修で学ぶこと」。公益学部公益学科の中に経営、政策、地域福祉、国際教養、観光・まちづくり、メディア情報の6つのコースを設置し、グローバルな視野を持ち、地域の人々とともに、地域社会が直面する経済、行政、福祉などの課題にリーダーシップを持って果敢に取り組む人材を育成しています。
地域共創センターの意義と活動内容
澤邉教授:地域共創センターは、2006年に開設されました。
このセンターは、大学と地域を結びつける役割を担い、行政、企業、ボランティア、そして地域の皆様から寄せられる情報や要望に基づき、学生と大学の各部署を繋げる重要な存在として活動しています。
さらに、2020年より同センターの規模を拡大し、4つの部会(地域連携部会、防災・環境部会、産学官連携部会、デジタル人材育成部会)による活動を展開しています。
なかでも地域連携部会は、もともと地域共創センターの基盤として設置された部会であり、現在も地域の行政、企業、地域の方々と大学との連携を強化し、地域社会の課題に対処するために尽力しています。
地域における学生の役割とは
澤邉教授:学生の発想により、さまざまな新しい活動が始まっています。
これらは、はじめは小規模な活動ですが、地域の皆様に関心をお持ちいただき、地域と学生が一緒に取り組むことで、活動に広がりが生まれ、学生の成長にも寄与する可能性があると考えています。
学生を巻き込むために行っているアクションとは
澤邉教授:私が担当している地域連携部会では、学生の活動支援をメインに行っています。学生が「こんな活動をしてみたい」という際には、その相談や支援を行うと同時に、学生向けの講座の開催、また学生と地域との協働によるまちづくり活動に対する支援を行っています。
具体的には、「学生活動支援助成金」という制度を通じて学生のアイデアやプロジェクトを支援したり、被災地へのボランティア活動に従事したい学生にはバスの利用費用の一部を補助する等の形で、災害復旧支援と地域防災活動に資する「災害復興・地域防災活動支援助成金」を提供しています。また、県内外でまちづくり活動や研修活動を行う場合の旅費やセミナー・講習会の受講料等を助成する「まちづくりインターンシップ補助金」という制度も設けています。さらに、学外の団体からのボランティア活動への参加オファーや、関連情報の収集と伝達にも取り組んでおり、これにより学生個々の活動へのきっかけづくりに取り組んでいます。
しかしながら、コロナの影響により、学生の活動が制約を受ける事態が発生しました。現在は制約が緩和されつつあり、いくつかの活動は元の状態に戻りつつありますが、そのなかには活動が途切れたケースも見受けられます。
このような状況下で、地域共創センターの活動を在学生はもちろん、新入生にも知ってもらうために、また、何か始めたい学生の活動スタートのきっかけになればということで、「チャレンジサポートウィーク(※1)」を開催し、学期初めのガイダンスでは、実際に活動を行っている学生が自身の言葉でその内容を伝える機会を設けています。
さらに、授業や演習での学びを発展させ、学生が自発的にプロジェクトを立ち上げる場合、学生活動支援助成金を活用できる可能性を伝え、支援しています。
地域連携部会としては、より多くの学生が積極的に参加し、新たな仕組みを構築するための課題に取り組んでいます。
(※1)チャレンジサポートウィーク…地域共創センターによる、学生活動を支援するための助成金に関する説明会や、各サークルの魅力を所属学生から新入生や在学生に伝え加入につなげるために、期間を設けて開催する説明会のこと
支援する立場から見る学生の成長は
澤邉教授:学生たち自らが考え、目標を設定し、その達成に向けて努力していく過程で、さまざまな方々との関係を築く機会が増え、想定していなかった活動にも取り組み、関係者との協力を通じて、学生たちは成長しているようです。
さらに、大学の活動は年度ごとにメンバーが変わるため、これまで中心となって活動してきたメンバーが抜けてしまい継続的な活動ができなくなる場合があります。そのような状況の中でも、後輩を指導育成しながら、彼らに活動への共感を促し、新たなメンバーを迎え入れる努力をすることは、学生の成長に大いにつながっているのではないかと考えています。
地域共創センターの展望
澤邉教授:地域共創センターとして、より多くの学生に情報提供し、活動に興味を持ってもらう取り組みを積極的に検討すべきと認識しています。
今後も、学生の活動をさらに効果的に支援できるよう、さまざまな工夫を凝らしていく予定です。
Liga食品ロス削減チームの活動
鈴木冴香さん:Liga食品ロス削減チーム(以下、「Liga」という)は主に、「フードドライブ」と「フードパントリー」の2つを中心に活動しています。

まず、フードドライブでは、例えば缶詰のパッケージに印字ミスがあるために、本来は消費可能な(食べられる)のに店頭に並ぶことなく廃棄される商品や、お中元やお歳暮で贈られたものの、食べきれずに余った食料品を企業や家庭から引き取る活動を行っています。


次に、フードパントリーについてですが、一般的にフードパントリーは、フードドライブによって収集された食料品を、生活が困難な方々やひとり親家庭など、何らかの理由で十分な食料を確保できない方々に無償で提供する活動を意味します。しかし、対象を限定してしまうと、もらいたくても行きづらいなどの弊害が生じるため、私たちは、対象を限定せずに誰でも受け取り可能にし、ひとり親世帯のほか、学生や高齢者など誰でも気軽に食品ロスに対する意識を高められるように活動を展開しています。
これらの活動を通じて、生活が困難な方々への支援と並行して、食品ロスの削減に寄与し、将来的には食品ロスゼロを目指す取り組みを推進しています。


さらに、昨年度からは酒田市との協働事業の一環として、料理教室(サルベージクッキング)を実施しています。料理教室では、冒頭で食品ロス削減に関する講座を行い、グループディスカッションなどを交えながら参加者全員で食品ロスを防ぐ方法について考えます。
また、酒田南高等学校の食育調理コースの先生に協力いただき、家庭で余剰になりがちな食材を活用した料理のレシピを考案していただき、参加者がそのレシピを実際に調理する機会を提供しています。これにより、各家庭で余剰の食材を無駄にしない方法を学び、実践できるよう支援しています。
ほかにも、酒田市内の小学校を訪れ、児童に食品ロスの現状を伝え、食品ロス削減について考える出前授業なども実施しています。
Liga食品ロス削減チームに入った理由
鈴木さん:大学生になって、高校時代までとは異なり、上級生との関わり合い、つまり縦方向のつながりを築くためには、自分から積極的にアクションを起こさなければならないことを強く実感しました。そのため、何かのサークルに所属したいと考えました。
その中で「食品ロス」という言葉が私の目に留まり、強い関心を抱き始めました。同時に、LigaがSDGsに対する問題意識を持って活動していることを知り、その姿勢に感銘を受けました。このような活動に参加し、一緒に活動したいという想いから Ligaに入ることを決めました。
前田実咲さん:私の場合、バイト先の先輩がLigaに所属しており、事前に活動内容を聞いていました。また、入学前に視聴したテレビ番組で食品ロスが社会的な問題として取り上げられていることを知りました。このような背景から、Ligaに興味を持ち始め、実際の活動紹介や雰囲気にも好感が持てたため、入会を決めました。
活動を続けるモチベーションとは?
前田さん:出前授業をはじめ、地域の皆様のおかげで成り立っているLigaの活動ですが、初めてお会いする方がLigaの名前や活動内容をご存知だった時は、これまでの活動が報われたように感じ、活動してきて良かったと思います。また、Ligaの活動に繰り返し参加されている方に気づいた際も、(Ligaの)活動に共感いただけたと感じ、モチベーションに繋がっています。
さらには、PR用のチラシ配布やイベント運営を行っている際、参加者の方から「食品ロスを減らすために食べ切ること」や「買い過ぎないように意識すること」を心掛けているなど、食品ロスに関するさまざまな声が寄せられた時には、私たちの活動の効果を実感し、活動してきて良かったと感じます。
やはり、地域の皆さんが私たちの活動に注目してくれて、誰かの役に立っていると感じることがモチベーションにつながっていると思います。
Ligaでの気づきや学びについて

鈴木さん:食品ロスの削減は、個人の工夫で比較的容易に実現可能であるにもかかわらず、多くの方々があまり意識せずに生活しているように思います。食品ロスとは何であり、どのようにすれば削減できるか伝えることで、多くの人々が食品ロスの活動を実践する可能性が高まるので、食品ロスの削減に向けた一歩として、理解者を増やすお手伝いをすることが重要であると感じています。
前田さん:Ligaは、フードドライブやフードパントリーなどの活動を主な取り組みとしていますが、何よりも先ず、多くの人々に食品ロスについての意識を高めてもらうことが重要だと思います。
現状、やはり啓発活動がまだまだ不十分だと考えており、昨年度からは出前授業やイベント開催時に、単に「フードドライブ」などの言葉の意味を伝えるのみではなく、より詳細かつ深い理解を促すための工夫を行っています。
その結果、多くの方々が食品ロスの問題を認識し、削減に向けた積極的な取り組みを展開していただいていることを嬉しく思っています。
これからの展望
鈴木さん:フードドライブやフードパントリーの継続に加え、1年生からは「子ども食堂」により力を注ぎたいというリクエストがあります。そのため、今後は「子ども食堂」プロジェクトに、より重点を置いて活動していく予定です。
また、メンバーが減少傾向にある現状を踏まえ、今後は、学生のみならず、酒田市内のNPO団体などと協力して活動に取り組む可能性も検討していきたいと思っています。
