
SDGs 大学プロジェクト × Tsuru Univ.
目次
都留文科大学のご紹介
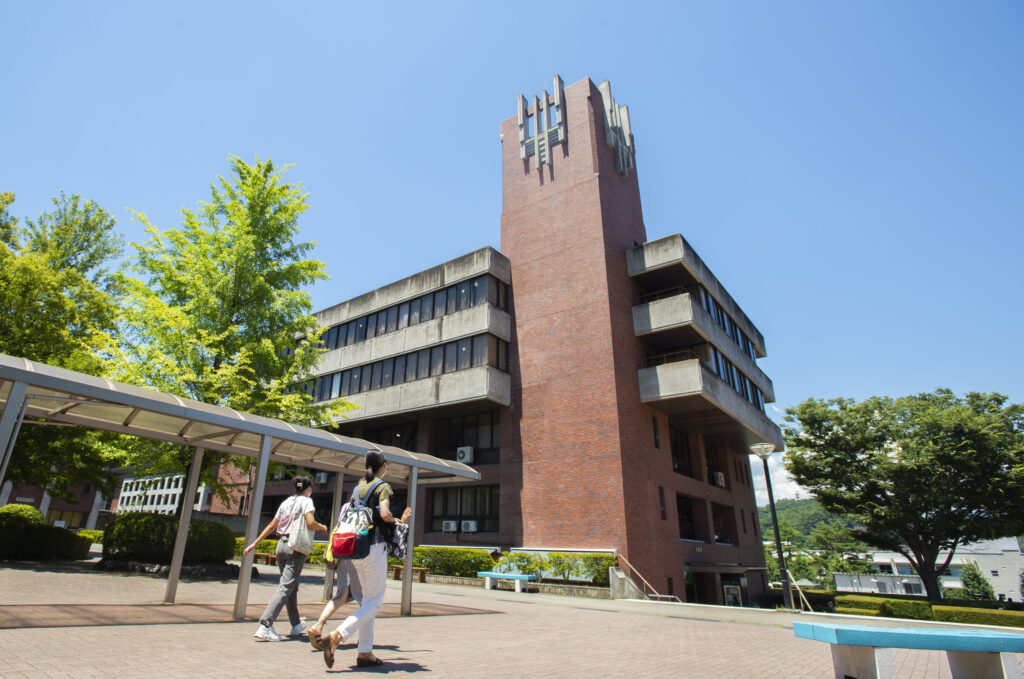

山梨県都留市にある都留文科大学は、「人間探究の大学」の理念を掲げる公立大学です。文学部(国文学科、英文学科)、教養学部(学校教育学科、地域社会学科、比較文化学科、国際教育学科)の2学部6学科を有し、地域に根差したグローバルな人材の育成を目指しています。
また、大学と地域をつなぐ拠点として「地域交流研究センター」を設置。学生たちにとって身近な地域を研究や学びのフィールドとし、地域住民とも連携した活動を展開しています。この他、市民公開講座や自然観察会、機関誌の発行による広報活動などを通し、学生たちの経験や学びを後押ししています。
今回は地域交流研究センターの取り組みについて、北垣憲仁教授と別宮有紀子教授にお話をお聞きしました。
地域交流研究センターとフィールドミュージアム構想

北垣教授:地域交流研究センターは、2003年4月に設立されました。このセンターは、本学と地域をつなぎ、さまざまな活動と研究を促進するための拠点となる機関です。
都留市は、人口が約3万人程度というコンパクトな都市であり、自然と人々との距離が近いという特徴があります。このような環境の下で、本学は多くの市民の方々と協力し、様々な活動を展開してきました。こうした人間関係を大切にし、さらに発展させるために、地域交流研究センターが設立されたのです。
地域には、新たな視点で物事を見つめ直す重要な”手がかり”があります。そのため、本学は地域全体を一種の博物館(ミュージアム)と捉え、実際に現地に足を運んで物事にじかに触れる「フィールド・ミュージアム」というアプローチを重要視してきました。このアプローチを地域交流研究センターでも積極的に推進しています。
-フィールド・ミュージアム構想やそれにまつわるプロジェクトを進めていく上で、大切にしていることを教えていただけますか?
北垣教授:私たちは現場でじかに見る、体験するということを大切にしています。たとえばムササビという動物は大きな木にできた洞と呼ばれる穴で暮らしています。そのムササビを標本として博物館に持ってきてしまうと、たとえばどのような環境で暮らしていたのかなど大切なことが分からなくなります。人の暮らしもそうです。私たちが推進する「フィールド・ミュージアム」は、地域で生き生きとした自然や文化に触れて学びを深めていこうという構想なのです。
そのためには、地域の方々との関係がとても大事になります。地域のサポートがなければ、学びのフィールドは実現できません。本学では、先人たちが工夫して得た経験に学びながら、地域での人間関係を大切に、活動をしています。
具体的な例として、地域交流研究センターの機関紙「フィールド・ノート」では、全学の学生が学科や学年を越えて編集に参加しています。かれらは地域に赴いて観察や記録を行い、市民との交流を深め、この機関紙を制作しています。このような実地の活動を通じて、新たな地域の出会いと交流が生まれています。
さらに、学生が中心となることで、卒業や入学によるメンバーの入れ替わりがあるため、新しい視点で地域の魅力を発見し続ける利点もあります。学生が主体的に参加することで、活動が停滞しにくくなり地域社会との結びつきや新たな交流を生み出しやすくなります。この点において、学生主体の取り組みは大きな意味を持つものと考えています。
地域との関係性が大きな力に
-学生が中心となるということが一つのキーワードになっているかと思いますが、主体的に考えたり行動したりできる学生を育てるため、どのようなことに取り組まれていますか?
北垣教授:学生にとって、地域の方々から声をかけられ、また励ましを受けるという経験は、大きな力になっているようです。やはり座学とは違う喜びがあるようですね。
このような地域との関係は、長い年月をかけて築かれてきたものであり、学生と教員の双方にとって非常に有り難いものです。
-コロナ禍では地域とのつながりが見えづらくなってしまった期間もあったかと思いますが、どのように乗り越えられたのでしょうか?
別宮教授:コロナ禍の頃は首都圏の大きな大学はほぼオンライン授業になっていたかと思いますが、本学では万全の対策をとりつつ、できるものからいち早く対面にしていました。フィールド・ノートも活動が途切れないように工夫して取り組んでいましたね。
北垣教授:確かに、コロナ禍はこれまで経験したことのない出来事でした。地域での取材や編集は対面が基本となるため、遠隔で冊子を仕上げるという経験はこれまでにありませんでした。
ミーティングでもオンライン形式だと意思疎通が難しくなる側面がありました。それだけに学生たちは細かな点に注意を払っていたようです。メールやミーティングにおいても分からない点は徹底的に話し合い、非常に丁寧に慎重に進めていたようです。
取材が物理的に難しい期間において、過去の先輩たちがどのような思いで冊子を制作してきたのかを振り返り、記事にしました。そのさい、冊子のバックナンバーを学生が読み合わせながら編集作業を進めました。先輩たちがどのようにインタビューをして言語化していったのかといった技術的な学びはもちろんありましたが、地域には魅力的な自然や人がまだ豊かにある、ということも再認識できました。
コロナ禍は非常に困難な時期でしたが、どうしたらこの事態を乗り越えられるかを工夫したり、立ち止まり振り返ったりするなど学生は試行錯誤を重ねました。このような経験を通して、自分で考えるという、卒業後の生活を切り拓く大切な力を身につけたのではないかと思います。
地域との交流を深める工夫も
-大学と地域が双方向でスムーズなコミュニケーションを取れるように工夫していることや大切にしてる価値観、地域との交流を後押しする取り組みなどがあれば教えていただけますか?
北垣教授:例えば、学生と市民との交流を深めるための取り組みの1つとして、「文大ボランティアひろば」というプロジェクトがあります。
本学においては、地域でボランティア活動に参加したいという学生の数は非常に多いです。しかし、ボランティアと一口に言っても、多岐にわたる種類が存在します。学生にとってどのようにしてどこで関わるべきか分かりにくいという課題もあります。地域には、ボランティアのニーズが多く存在します。しかし、お互いの要望や希望がずれていたり、安全が確保されていない場合、せっかくの”学びの場”がうまく機能しません。
そこで、市の社会福祉協議会などと連携し、学生の安心と安全を確保しつつ、ボランティアのマッチングを行うための工夫をしています。月に1回開催される「文大ボランティアひろば」では、地域のボランティア活動に実際に関わっている方々をお招きし、学生との交流の場を設けています。
このプログラムは始まったばかりですが、ボランティアに関わる方々と直接交流する機会を通じて、自分もボランティアに参加したいという学生も増えてきました。
別宮教授:私たち教員が知らないところでも、ボランティアなどの自主的な活動を行う学生が多くいます。都留市は規模がそれほど大きくないためか、地域の方々は本学の学生に対して非常に温かいと感じます。地域の人や暮らしとの距離が近いことにより、学生たちが地域の活動に参加できる機会が多いことは、本学や都留市の特徴の一つだと考えています。
先日、本学と都留市、地元の鉄道会社である富士急行株式会社との連携協定に基づいて、市内をハイキングしながらゴミ拾いを行うプロギングというイベントが開催されました。多くの学生が参加し、地域の自然や景観を楽しみながらゴミ拾いを行い、地域住民や市役所の関係者と交流を深めました。
学生と地域が日常的なレベルで楽しみながら触れ合えるよう、市の方々が配慮してくださっているのも大きなポイントですね。
「生きた学び」がもたらすもの

-地域交流研究センターとして、学生に期待する役割をお尋ねしてもよろしいでしょうか?
北垣教授:先ほども触れましたが、地域交流研究センターでは学生が主体的に活動することを大切にしています。本学の学生は全国から集まり、卒業後には地元に戻る場合も少なくありません。
したがって、ここで得た知識や経験を活かし、それぞれの地域の未来を担う人間として成長していただきたいと願っています。
私たちは、座学だけでなく実際の現場で生活や自然と触れ合いながら学びを深めることを「生きた学び」と呼んでいます。理論的な学習に加え、実際の日常生活で必要なスキルや知識も修得していただきたいと考えています。
-活動を通し、どのようなところで学生の成長を感じますか?
別宮教授:小学校、中学校、高校と学校社会の中で過ごしてきた学生たちにとって、身近な大人といえば親や親戚、教師、習い事の先生くらいです。
しかし、本学に入学すると、地域の大人との交流を通じて、他の人々の価値観や考え方に触れ、視野を広げ、共同で物事を進める楽しさや難しさを経験し、社会性を養っていきます。言い換えれば、社会に出てからの疑似体験を少しずつ重ねることができるのです。このような雰囲気が大学全体に広がっており、他にはない本学独自の特徴だと考えられます。
北垣教授:学生の成長はいろいろな場面で実感しています。入学当初は受け身の姿勢で、自分から質問したり主体的に物事を進めたりすることが苦手な学生が少なくありません。しかし、実際に地域の住民とともに社会の現場を見ていくにつれて、自ら進んで動き始めたり、自分から発言をするようになったりする場面に多く出会ってきました。
また、都留市には他の地域から移住してくる方々が多いため、さまざまな工夫をしながら社会で生き抜いている人々の姿に触れる機会が多くあります。この点からも、激動の時代において変化に適応する力を養うための刺激に溢れていると感じています。
学内の環境保全プロジェクトも始動

-地域交流研究センターとしてのこれからの展望を教えていただけますか?
別宮教授:本学は自然環境に恵まれており、大学の周辺だけでなく、キャンパス内も豊かな自然に恵まれています。ムササビ、リス、タヌキ、テン、アナグマなど、さまざまな野生動物を目にする機会があります。また、絶滅危惧種の植物が7種ほど自生しており、他では貴重な自然が普通に存在しています。
最近、学生、教職員、地域の方々と協力して、この自然環境を保全し、世界一の生物多様性と美しさを誇るキャンパスを目指すプロジェクトを立ち上げました。他の大学とは異なり、自然に恵まれた本学だからこそ、キャンパスをフィールド・ミュージアムとしてとらえました。
自然と人間が調和し、共存するキャンパスを環境整備の中核としています。キャンパス内の緑地は単なる景観だけでなく、教育、交流、憩いの場として、また省エネや温暖化対策、生物多様性の保全を目指す場として整備することが目標です。
そのため、単に緑地を整備・保全するだけでなく、自然エネルギーの活用や自然環境の冷暖房への適切な活用なども考慮し、大学全体のマスタープランを策定しました。このプランにおいて、学生の意見を環境整備に取り入れるとともに、地域の方々とも協力して実現することを目指しています。
この計画は長期的なものとなりますが、本学の立地と資源を最大限に活用し、動植物と共存可能な自然豊かで生物多様性の高いキャンパスを整備したいと考えています。この目標達成に向けて、学生が積極的に参加し、活躍できる組織を構築する予定です。
プロジェクトのポスターをキャンパス内に掲示したところ、2023年度だけでも15〜16人の学生が参加を志願してくれました。彼らは専門分野が異なっていても、生物多様性の保全や環境整備を通じて大学に貢献したいという意識が高いことがわかりました。このような活動を通じて、学生たちが専門外でも成長できる機会を提供していくことを考えています。
北垣教授:こちらのプロジェクトでは、本学をみんなが誇りに思える場にしていきたいと考えています。
これまでお話ししてきた地域交流研究センターの活動やフィールド・ミュージアム構想にも、人と自然とがどうしたらうまく付き合えるかを考えていくという視点が欠かせません。本学では、SDGsの発想が広まる以前からその視点を取り入れて実践してまいりました。
その過程で、学生は自身の考えを修正し、他の人の意見を尊重しながら、社会に出る前の最終段階として、様々な学びをフィールドで深めていくことができます。それが本学の大きな特徴の一つだと改めて感じています。
