
SDGs 大学プロジェクト × Tottori University of Environmental Studies.
目次
公立鳥取環境大学の紹介


公立鳥取環境大学は、「人と社会と自然との共生」を実現することを基本理念として掲げ、2001年に公設民営の私立大学(旧名称「鳥取環境大学」)として開学しました。2012年に鳥取県と鳥取市を設置者とする公立大学に生まれ変わりましたが、開学以来の基本理念を継承し、現在に至ります。
公立鳥取環境大学は創立以来、持続可能な社会の実現を目指してきましたが、SDGsの趣旨は大学の基本理念に一致することから、2018年に大学として一丸となってSDGsに取り組むことを宣言しました。これまで培ってきた公立鳥取環境大学の教育、研究等の力を活用し、SDGsの達成に貢献するため、様々な取り組みを行っています。この取り組みは、地域と密接に連携しながら、グローバルな視野を持つ人材も育成する大学の使命そのものです。教育プログラムと研究活動を通じて、環境保全、社会的平等、経済的発展のバランスを重視し、持続可能な社会の構築に寄与しています。
持続可能な社会を実現するためは、環境保全と経済発展を両立させなければなりません。つまり「経営」視点を持った環境学、「環境」を意識した経営学が求められています。公立鳥取環境大学は「環境学部」と「経営学部」を設置しており、「環境」と「経営」の交わる教育と研究が注目されており、日本各地から学生が集まっています。
人と社会と自然の共生を目指す、SDGsの取り組み

― 公立鳥取環境大学様では、授業や学生の活動などを通じ、SDGsへの貢献を積極的に行っている点が特徴の一つとなっています。SDGsに着目されるようになった経緯について教えてください。
2001年に「鳥取環境大学」として開学した本学は、名前が示すように、「人と社会と自然との共生」の実現に貢献できる人材育成と、創造的な学術研究を行うことを基本理念として掲げています。この理念はSDGsの考え方と本質的に一致しており、まさに本学のアイデンティティを体現するものであると言えます。
また、2015年の国連サミットでは、SDGsに関する宣言が発表されました。SDGsは、経済、社会、環境の側面が調和した持続可能な社会を目指す、全世界共通の目標です。17のゴールと169のターゲットから構成されており、これらはまさに本学が取り組んできた課題と密接に関連していました。
そこで本学は、大学全体としてSDGsへの取り組みを推進することを宣言するため、検討委員会を設置し、詳細な分析を行った上で、2018年にSDGsへの取り組みに関する宣言を行いました。
▼ TUES × SDGsについて詳しくはこちら TUES × SDGs | 公立鳥取環境大学
― かなり早い段階から幅広いSDGsの活動に取り組まれていらっしゃいますが、2023年は「脱炭素」をテーマに掲げられていたのはなぜですか?
本学は開学以降、持続可能な社会の実現に向けて取り組むべき課題に取り組んできました。中でも、「脱炭素」は、現在世界が直面する地球温暖化や異常気象をはじめとした環境問題の最も重要なテーマの一つだからです。
▼ 脱炭素の実現に向けた取り組みについて 脱炭素 | 公立鳥取環境大学
本学が「脱炭素」をテーマに掲げたきっかけは、大きく二つあります。
一つ目は、環境省が公募した「第三回 脱炭素先行地域」の取り組みです。この公募に対し、鳥取市や本学を含む四つの団体で共同提案したプロジェクトが選定されたことが、大きなきっかけとなりました。
二つ目は、国連が同時期に発表した「Race to Zero(レース・トゥ・ゼロ)*」という新たな取り組みです。本学も日本の大学で3番目、公立大学として初めてこの取り組みへの参加を決定し、2030年、2050年に向けて脱炭素化を進めるための具体的な計画を策定することになりました。
このように、本学の「脱炭素」への取り組みは、単に教育理念に基づくだけでなく、地域や世界の状況に対応し、より一層加速していくこととなりました。
Race to Zeroとは:2030年までに温室効果ガスの排出量を実質的に半減させる目標を掲げ、それを達成するための具体的な行動を促す国際的なキャンペーンのこと
地域社会と連携し、持続可能な社会の実現に取り組みたい


― 脱酸素の実現に向け、具体的に取り組まれている施策などについて教えてください。
例えば、これまで本学独自で天ぷら油などの廃油をリサイクルし、バイオ燃料に変換する実験を実施しました。植物由来の天ぷら油はバイオ燃料として非常に優れており、カーボンニュートラルな取り組みに繋がります。このバイオ燃料を活用し、スクールバスの運行をはじめとする様々な実験に取り組みました。
また、屋上緑化を施すことで夏場の温度上昇を抑え、エアコンの使用量を削減するなど、建物の消費エネルギーを小さくする工夫も行っています。太陽光発電システムやソーラーウォール、クールヒートチャンバーなどの設備も設置し、省エネおよび再生エネルギーの利用を推進しています。
そして、先にも述べた「脱炭素先行地域」や「Race to Zero」への取り組みなどです。これらの取り組みは、SDGsへの貢献だけでなく、学生の専門分野に向かう学徒としての、また社会人としての成長につながると考えています。
― 鳥取市などの自治体や企業と連携されるようになったきっかけはありますか?
開学当初に比べ、近年では異常気象による自然災害の増加などにより、多くの人々がこれらの問題を自分事として捉えるようになったことから、企業側でもESG投資*やSDGsに対する関心が高まり、連携の機会が増加しているように感じます。
企業、投資家だけでなく地域の方々も、持続可能な未来を築こうとする企業への関心を高めているのではないでしょうか。
ESG投資とは:Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の頭文字を取り、これら三つの側面に配慮した投資を行うこと
― 今後、脱酸素に向けて考えられている取り組みがあれば教えてください。
まだ計画段階ですが、例えば「脱炭素先行地域」の活動の中で、鳥取市の佐治町や若葉台地区など、地域との連携を重視した取り組みをさらに推進していきたいと考えています。
地域との連携を成功させるために不可欠なことは、地域住民の方々も「参加しよう」と思える環境作りです。そのためにも、互いに利益が生まれるWin-Winの関係を構築する必要があると考えています。
例えばバイオマス利用では、地域から木材を集めてバイオ燃料に変換するプロセスにおいて、地域への利益還元の仕組みを考えることが重要です。森林整備やエネルギー使用の最適化についても地域の方々と対話し、持続可能な地域づくりに向けて歩みを進めていきたいと考えています。
今後のことはまだ未知数ですが、学生や地域の人たちを巻き込みながら発展させていきたいですね。
「Race to Zero」への挑戦と持続可能な未来への歩み
― 先ほど、二酸化炭素排出量削減を目指す国際キャンペーン「Race to Zero」への参加に関するお話がありました。継続的な参加条件など厳しいハードルがありますが、貴学ではなぜ参加を決断されたのでしょうか?
「Race to Zero」への参加では、本学が同時期に推進していた「第三回 脱炭素先行地域」の取り組みが大きな後押しとなりました。「脱炭素先行地域」が掲げる地域全体での温室効果ガスの排出量削減という目標は、「Race to Zero」の理念や目標とも合致しており、本学の取り組みが評価される一因となったのです。
「Race to Zero」では、スコープ1から3までの「温室効果ガス排出量削減目標」が設定されています。その中でも、比較的早期に取り組むべき課題の一つとして、「キャンパス内の建物をZEB(ゼロ・エネルギー・ビルディング)化すること」が挙げられています。ZEB化とは、建物のエネルギー消費量ゼロを目指すものであり、具体的には、建物の緑化や窓の断熱性能の改善などの措置が有効です。
そして「Race to Zero」への参加当時は、本学の設備更新時期と重なっていました。この機会をチャンスだと捉え、現在、本学ではスコープ全体を踏まえたZEB化の取り組みを積極的に推進しています。
今後もスコープを進めていくにつれて、目標達成のハードルはさらに高まります。しかし、だからといって何も行動しないのではなく、段階的に次の目標に挑戦していこうという前向きな姿勢で取り組んでいます。
「Race to Zero」での取り組みを通じて、教職員や学生の環境意識を高めることはもちろん、優れた教育研究の活性化にも繋げていきたいと考えています。
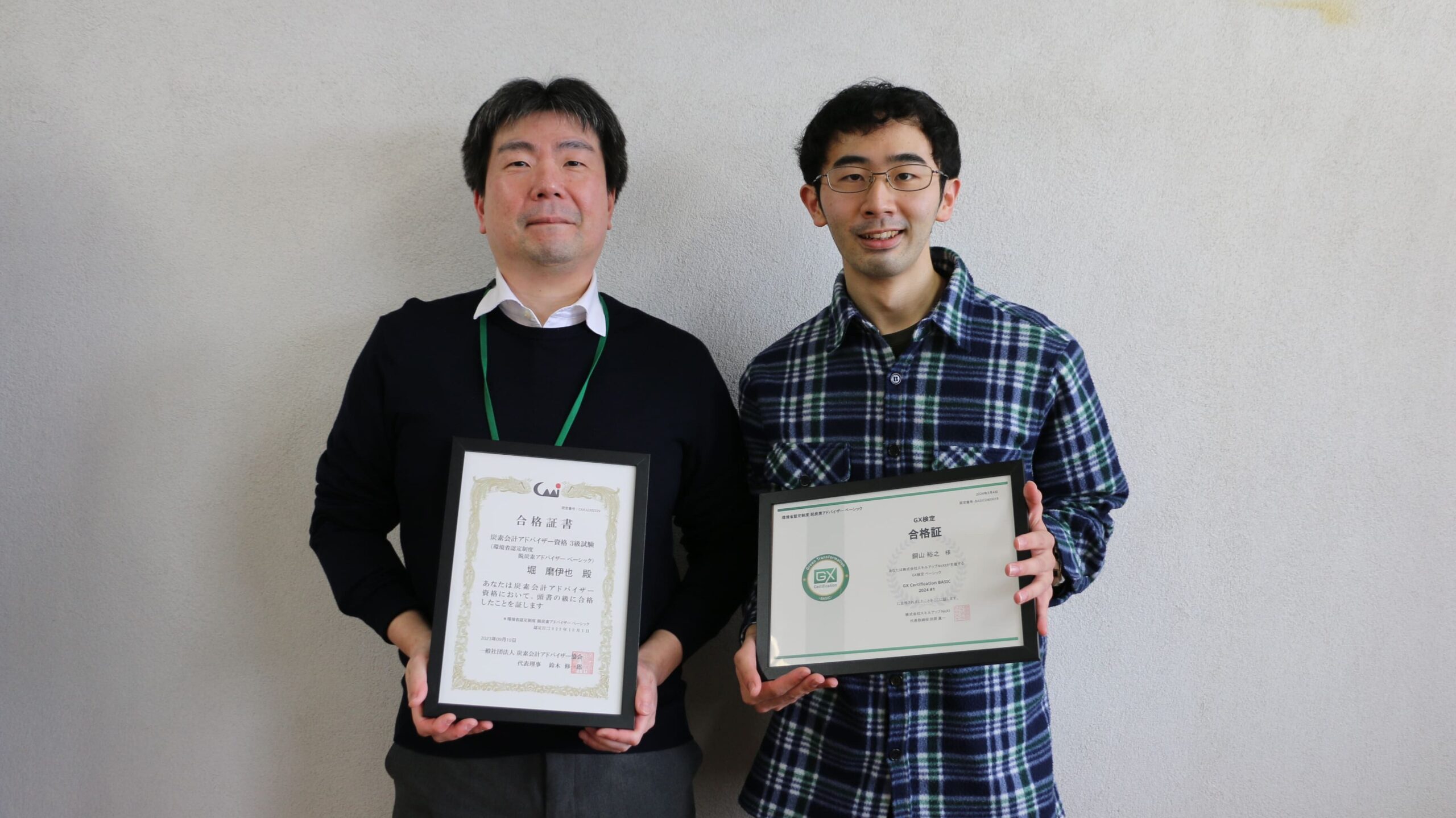
― 「Race to Zero」への参加がきっかけとなった、印象的な活動や出来事はありますか?
まず、一部の特に積極的な学生たちは、「Race to Zero」を知ったことでSDGsへより強く関心を持ち、意識や行動が変化したように感じています。
その具体的な例として挙げられるのは、学生たちの自発的な発案により2023年12月に開催された「TUES Sustainability Week」という5日間にわたるイベントです。学生たち自身が社会の持続可能性について考え、行動に移す気持ちを高めることを目標にして運営されました。


▼ TUES Sustainability Week についてはこちら TUES Sustainability Week を開催しました | 公立鳥取環境大学
学生が発案し、運営の中心となり、教職員や学生によるSDGsに関連したテーマでの講演を行うなど、大学や地域社会の持続可能性について理解を深める場となりました。その他にもパネル展示や地域の清掃活動、ごみの分別を一段と強化するなど、さまざまな取り組みが実施されました。
さらにこのイベントでは、学生の要望に応え、鳥取県知事の平井様を講演に招待することができました。多忙なスケジュールのなか実際に登壇してくださったことは、学生たちにとっても大きな喜びとなったことでしょう。
-1024x1024.jpg)
-1024x683.jpg)
― 「TUES Sustainability Week」は、今後も継続して開催される予定ですか?
はい。次回の「TUES Sustainability Week」は、今年の7月から8月頃に開催を予定しています。
前回のイベントでは、学生たちにとって多くの学びと反省がありました。これらは、彼らの成長に欠かせない重要な要素です。このイベントは基本的に学生主導で運営しているため、大学からの具体的なアドバイスは最小限にしています。学生自身が課題を発見し、解決策を見つける過程は、教育的にも非常に価値があると考えているからです。
そのような経験を踏まえ、今年の夏には第二回目の開催を計画しています。今後も学生たちの主体性を尊重しつつ、継続的に開催していけると嬉しいです。
自主性を尊重したSDGsへの取り組みを通じて得られる学生の「成長」
-edited.jpeg)
― SDGsへの取り組みにおいて、貴学の学生の方々はどのように関わり、どのような役割を担っていますか?
本学には「学生EMS委員会」という団体があり、学生たちが主体的にSDGsに関わる活動に取り組んでいます。この委員会に所属する学生たちは、「みんなが愛する学校を創ろう」というスローガンのもと、学内や鳥取市内の清掃などの社会貢献活動、環境管理活動、資源の節約やエネルギー効率の向上を目指す活動などに、積極的に取り組んでいます。
EMS委員会だけでなく、一般の学生たちも「脱炭素先行地域」に関する活動などにも参加し、役割を担っています。また、地域の動植物などの生息地保全のための環境省が取り組む「30by30*」(自然共生サイトプロジェクト)にも地域の方々といっしょに取り組んでいます。
▼ 学生EMS委員会 についてはこちら 公立鳥取環境大学 学生EMS委員会公式サイト
30by30(サーティ・バイ・サーティ)とは:2021年のG7サミットで合意された、『2030年までに海と陸地の30%以上を健全な生態系を守る自然環境エリアとして保全しよう』という目標のこと。
彼らの取り組みの一環として発案されたのが、先ほどもご紹介した「TUES Sustainability Week」です。その他にも、例えば毎年秋に開催される大学祭では、実行委員会が自発的にゴミの分別の啓蒙活動を行うなど、SDGsに関連するさまざまな活動が増加してきていると感じます。
従来、本学が主導するSDGsへの取り組みは習慣化していたと言えるでしょう。そして、近年では世界的な環境意識の高まりや、近隣地域で発生する自然災害の影響も受け、学生たち自身もSDGsに関する課題を身近に感じ、自ら行動を起こしているのではないかと思っています。
― 貴学では、SDGsに関する取り組みを通じて、学生の方々にはどのような成長を期待されていますか?
繰り返しになりますが、本学の理念は「人と社会と自然との共生」であり、本学の一番の目的は、その理念に沿った活動を通しての「学生の成長」であると位置付けています。
「成長」とは、専門性の向上、社会人としての成熟、問題解決能力の習得など多岐にわたりますが、重要なのは、全て具体的な活動を通じて達成されるということです。学生たちが自ら考え、行動し、時には失敗しながら成功を模索する過程が、真の成長を促すと思います。そして、大切なことは学生自身が自分の成長を実感することです。
さらに本学では、環境学部や経営学部など、各学部で専門性を活かした活動も展開しています。これらの経験を通じて専門的な知識を深めることにも期待しており、すでに一定の成果を感じられています。
SDGsと言うと遠い概念のように感じられがちですが、具体的かつ身近な課題への取り組みから得られる成長や知識は計り知れません。これらの取り組みが持つ意義を大切にし、学生の自主性を尊重しながら成長をサポートしていきたいです。
今後の展望

― 脱酸素の実現に向けた今後の新たな活動や、その他にも取り組みたい課題など、今後の展望について教えてください。
今後、本学としては大きく発展的な改革を行いたいと考えています。少子高齢化に伴い、受験生が減少していく中でも、教育機関として学生たちの成長を支える持続可能な運営を目指すことが重要だと認識しています。
また、Z世代やα世代と呼ばれるこれからの受験生たちは、我々とは異なる視点を持っていると感じています。そこで、本学が掲げる理念に基づきながら、彼らと直接話し合い、彼らが関心を持ちやすい学問領域やプログラムなどを創設していきたいです。つまり、学生たちも大学づくりに参加するということです。現在の一学部一学科の枠組みを拡張することも含め、新たな教育のかたちが検討できるかもしれません。
そして現在、具体的に考えている展望は三つあります。
一つ目は、「TUES Sustainability Week」のような、学生自身が発案し、彼ら自身による創意工夫に富んだ取り組みをさらに増やしていくことです。学生たちが発案したアイデアを実現する機会を提供することで、彼らの関心や創造力を引き出したいと考えています。
例えば、私が長年顧問を務めていた生物部の学生たちにEMS委員会によるSDGsの活動について共有したところ、彼らも触発され、環境省が取り組む「30by30」に基づき、大学のキャンパス自体を自然共生サイトとして整備するアイデアを考えてくれました。
この提案が実現すると、本学の自然豊かなキャンパス内での生物多様性の保全や脱炭素化が進むことが期待されます。現在は提案段階ですが、今後具体的な活動に繋がることをこっそり期待しています。
また、本学には「ヤギ部」というユニークな部活動があります。

▼ ヤギ部 についてはこちら ヤギ部 | 公立鳥取環境大学
適度な個体数のヤギが生息する土地では、ヤギが草を食むことで一定の草原が維持されることから、ヤギの飼育は「草原の喪失に伴う生物多様性の減少」という環境課題について考えるきっかけになります。そして、それは同時に 30by30 の認定条件の達成にも力を貸しています。これらのことの積み重ねによって、キャンパス内に多様な生物が生息できていることは、これまでの学生たちの調査から明らかです。
開学時から実際にヤギを飼育することで、大学内に里山環境を創造し、結果的に生物の多様性も増しています。キャンパスが里山も含んだ30by30の地域内に存在するような環境になっている大学は、他にはないのではないでしょうか。
このように、学生が主体的に考えて実践に移すだけでなく、その活動を広く共有していくことで、他の学生やサークル、有志活動にも興味関心が拡大し、実践の輪が広がることを期待しています。
二つ目は、学生が主体となってガイドを務める「鳥環大SDGsツアー」です。
具体的には、中高生や一般の方々を対象とした「深い学び」になる体験型ツアーを予定しています。デモンストレーションを一度行い、手ごたえを感じています。学生たちが専門分野での学びを生かし、教員とも協力しながら、大学を取り巻く地域でSDGsに関連した知識や技能等を、活動の中で参加者に体験的に学んでもらおうというものです。
このアイデアは、コスタリカなどで実施されているエコツアーの大学版といってもいいでしょう。大学の教員も関わることで、より深い学びのツアーにしたいと考えています。もちろんそこには、学生の学びがあり、学生が主役になります。エコツアーは、自然を保全しながら観光客を誘致し、地域経済を活性化させるアプローチのことです。このモデルを参考に、鳥取県の自然の豊かさを活かしながら、経済的な利益を創出する施策を検討しています。
また、このようなアプローチを模索するにあたり、本学の経営学部と環境学部は非常に相性が良いと考えています。地方大学である本学にとって、自然の豊かさを強調するだけでなく、それをどのように魅力的に活用し、どのように資源として活かすかが重要です。この試みによって地域経済の発展を促し、自然保護とのバランスを保ちながら持続可能な発展を目指す必要があります。
この取り組みを通じて、学生の成長や地域社会に新たな価値を生み出していきたいと考えています。
三つ目は、本学の学生が自治体や商工会議所、特に工業部会の企業の方々からご提出頂いたSDGsに基づく課題に取り組む「共創プロジェクト」です。
学生たちは、自らの興味関心に基づいた課題を選び、解決策を模索していきます。このプロセスは学生主体で進められる一方、企業や地方自治体からの期待に応えるため、単独での対応が難しい部分をサポートする意味で、教員がアドバイスを提供するなど、適切な指導を行っています。
既に本学独自の展開として実績を積み上げており、学生の自主的な参加と成長を促す意義のある試みです。さらに、本プロジェクトは企業が抱える問題の改善のみならず、学外に対して本学の特色をアピールする具体的かつ重要なポイントにもなっていることから、非常に有意義な学びの場となっています。
このような既存の取り組みもさらに強化し、地域社会との連携も深めていきながら、学生たちがSDGs達成に貢献できる人材へと成長することを期待しています。
