
SDGs 大学プロジェクト × Josai Univ.
目次
城西大学の紹介


城西大学は、「学問による人間形成」を理念に掲げ、1965年に創立。豊かな自然環境に位置し、優れた研究者と教育者が集まる大学として、理想の実現と人間愛、知恵、勇気を持った有用な人材の育成を目指しています。また、多様な視点から問題を解決できる人材育成にも注力し、現在は特にSDGsの達成に向けた持続可能な社会の実現を推進しています。
城西大学ではグローバルな視点から国際交流や留学プログラムが充実しており、学生たちが世界中で活躍できる力を身につけることを支援しています。豊富な研究機会や実践的な教育プログラムを経て、卒業生たちは社会のさまざまな分野でリーダーとして活躍しているのです。
さらに、学生の「協創力」を育むためのリベラルアーツ教育にも力を入れ、学生が地域社会に飛び出し、企業や団体との共同プロジェクトなども積極的に行っています。その一つが「高麗川かわガール」の活動です。
城西大学「高麗川かわガール」の環境保全活動とは


― 今回は、城西大学のキャンパスを流れる高麗川の環境保全に取り組む「高麗川かわガール」顧問である真野博教授と、メンバーである学生の皆さんにお話をうかがいます。高麗川かわガールでは、普段はどのような活動をされているのでしょうか?
小山昂輝さん(以下、小山さん):高麗川かわガールは、2週間に一度、土曜日の朝8時半から大学近くの高麗川で河川敷の清掃、水質検査、生態系調査などの環境保全に貢献しています。収集したゴミや水質データなど、活動報告をFacebookやインスタグラムで発信し、参加者や周囲の方に川への関心を持ってもらえるよう努めています。参加人数は日によって異なりますが、本学の学生だけでなくOBやご近所の住民の方も参加してくださっていて、毎回10名前後のメンバーが集まって活動しています。
― 高麗川かわガールは、管理栄養士や薬剤師を目指す学生の発案によって設立されたとうかがいました。活動を始められた経緯や目的を教えてください。
真野博 教授(以下、真野教授):まず、私が在籍している医療栄養学科は、薬学部で管理栄養士を養成している日本唯一の学科です。高麗川かわガールには、立ち上げ当初から医療栄養学科の学生だけでなく、薬学部で薬剤師を目指している学生や、管理栄養士や薬剤師とは異なる薬科学科の学生など、さまざまな学科の学生が参加していました。
本学のキャンパス内を流れている高麗川は、関東で大きな河川の一つである荒川の支流です。私たちの学部ではさまざまな実験も行っており、その過程で川に影響を及ぼす可能性があります。また、本学だけでなく家庭からの排水も最終的にはこの川に流れ込み、その水を東京都民や埼玉県民が飲んでいると考えることができます。
このような背景から、管理栄養士を目指す学生たちに川や淡水に興味を持ってもらいたいという思いがありました。自分たちが汚した水を飲んでしまう可能性や、環境教育と食育、健康教育が密接に関係している食物連鎖について理解してもらうためにも、高麗川かわガールの活動は最適だと考えていました。

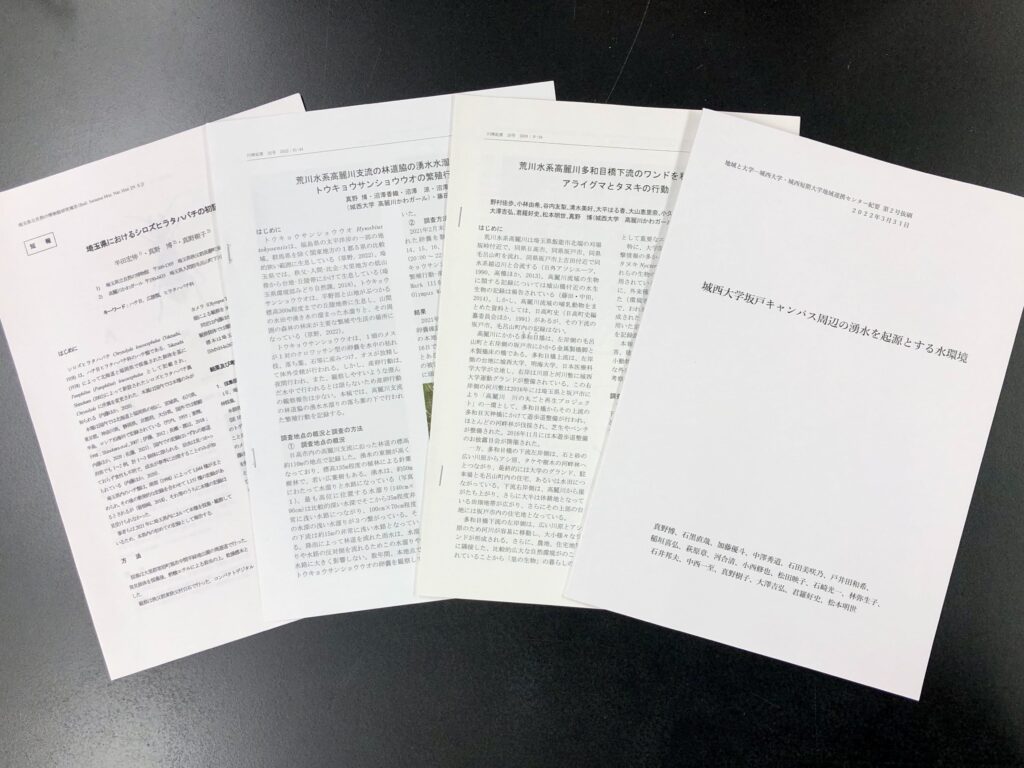
高麗川の清掃や生態調査などの活動を始めてから約10年が経とうとしています。現在では美化活動に加え、高麗川周辺の食材である梅やゆずなどにも注目し、それらを活用することでSDGsにも貢献できる活動を試みています。具体例としては、通常は廃棄されるゆずの皮や種子を活用した食材作りを進め、ゴミの削減に取り組んでいます。
また、最近では荒川を遡るアユに注目した活動も行っています。東京湾で育ったアユは、本来であれば秩父や高麗川まで遡るとされているのですが、荒川には複数の大きな障害物があり、アユたちはなかなか川を遡りきることができません。私たちは自然の循環を考え、さまざまな活動を模索しています。
つまり、高麗川かわガールの活動は、薬学部が発案したものではなく、食や健康に関わる学生たちとの教育の中で生まれた取り組みなのです。
高麗川かわガールで得られる学びや気づき
― 学生の方々が高麗川かわガールに参加されるきっかけには、どのような経緯がありますか?
土屋 明寿美さん(以下、土屋さん):私は学部生の頃から高麗川かわガールの活動を知っていたのですが、休日の朝早い時間に大学へ行くことが難しく、当時はあまり参加できませんでした。その後、大学院生となり、研究室の教授や先輩が活動している様子を目にしたことが、私が参加を決意するきっかけとなりました。
正直なところ、学部生の頃は、高麗川かわガールでは単にゴミ拾いや水質検査をしていると思っていました。しかし実際に活動に参加してみると、先ほど真野先生が仰ったような活動の意義を少しずつ理解できるようになったと感じています。
真野教授:実は、本学の医療栄養学科の1年生は、全員が必修科目の一環として私たちの活動に一度は参加することになっています。この必修科目での参加をきっかけに、私たちのメンバーとして継続的に活動してくれる学生も、毎年数名いますね。今年は、男子学生が1名、毎週積極的に参加してくれています。
― 長年継続されている清掃や水質検査を通じて、成長や意識の変化は感じられていますか?
土屋さん:最近では、河川の様子を見れば水質の状態がわかるようになってきました。実際に薬品を使って水質検査をすると、目で見て感じたことが数値で表れます。高麗川かわガールの取り組みを続けていくうちに、知識も深まってきたと感じています。
勝又 靖行さん(以下、勝又さん):大学の講義では、例えば溶液が川に流れることによって発生する水の汚染などについて学んだことで、水や環境に関する意識が高まりました。高麗川かわガールの活動を通じて、講義で学んだことを実体験できていると感じます。

― 立ち上げ当初と比較して、学生の方々の変化は感じられていますか?
真野教授:これは課題でもあるのですが、正直に言えば、初期と比べると活動の主体は私の研究室の学生たちになっています。初期の高麗川かわガールには、他学科や他のゼミ生も参加していました。しかし、最近では私の研究室以外の学生の参加が減ってしまっています。
一方で、10 年経過したことで、知名度が上がり、他の環境団体や博物館とのコラボレーションが増えてきました。学生の社会性や協創力も高まり、やりがいのある活動なので、参加してくれる学生の幅が再び広がると嬉しいです。一方、メンバーだった卒業生が自分の子どもをつれて、川のイベントに参加してくれることもあり大変心強く感じるようになっています。
広報活動が繋げた学外活動の広がりと新たな可能性
― 近隣の小中学校や地域の団体とも連携されていると拝見しました。学外との連携も、意識して広げているのでしょうか?
真野教授:はい、学外との連携は意識的に進めています。例えば、SNSや大学のホームページで活動を発信することで、それを見た方々から声をかけていただくことがあるのです。最近では栃木の環境団体が訪問してくれたり、埼玉県にある「川の博物館」と共同で美化活動を行ったりしています。
▼ 詳しくはこちら 城西大学 高麗川かわガール&埼玉県立 川の博物館(かわはく)コラボ企画 「高麗川リバーコミング」(josai.ac.jp)
高麗川かわガールを立ち上げた初年度から、大学のホームページやFacebookを活用した広報活動を行っています。特に印象深かったのは、NHKの「ダーウィンが来た」などを撮影している映像制作会社つばめプロの平野伸明さんが、私たちの活動に興味を持って声をかけてくれたことです。彼らとの繋がりが、広報活動の効果を実感する大きなきっかけの一つとなりました。
平野さんとの共同活動を通じて、学生たちは多岐にわたる経験を積むことができました。例えば、NHKの「さわやか自然百景」で高麗川が特集された際には、一緒にドローンを操作して撮影を行いました。また、高麗川が動物たちにとって訪れやすい環境となるよう、撮影を通じて様々な保全活動にも取り組みました。さらに、大学院生たちは平野さんの指導のもと、トレイルカメラを使用して動物の定点撮影を行い、その観察記録を「川の博物館」で発表する論文にまとめ上げました。
これらの経験を通じて、意識的に外部機関との連携を深めることで自分たちだけではできなかったことが実現し、新たな可能性を開くという感触を持っています。それだけでなく、学生にとっては多くの人と繋がることもできる良い機会になっているのではないでしょうか。
また、2025年には、高麗川かわガールが10周年を迎えるため、実は「高麗川物語」というタイトルで特別展示を開催することを計画しています。詳細は未定ですが、例えば高麗川をテーマとした写真コンテストを開催し、平野伸明さんに審査員長になっていただきたいと考えています。先日お願いしてみたところ快諾してくれたため、ぜひ実現したいですね。
― 現在、SNSの発信や運営も学生の方々が担当されていらっしゃるのでしょうか?
小山さん:はい、私たち学生がインスタグラムを運営しています。活動の様子を自分たちで撮影して投稿していますが、現在は突拍子のない投稿というよりは、ありのままの風景を投稿しています。団体として初めてSNSを運用しているため、奇を衒わない形で情報発信を続けています。
「継続は力なり」過去からの継続と環境の変化
― 学生の方から発案された活動などがあれば教えてください。
真野教授:我々のキーワードの一つは「継続は力なり」なので、過去から継続して取り組んでいる活動が多いです。最近新たに始めたのは、俳句作りですね。昨年卒業した大澤くんが毎回一句作っていましたが、最近はどうでしょう?
小山さん:最近はネタが尽きてしまい、保留中です。季語がなくなってしまって…。
真野教授:俳句は何百年も続いている文化ですから、まだまだあるはずですよ(笑)
ほかに皆さんの印象に残っている活動はありますか?
土屋さん:継続していると言っていいのかわかりませんが、学生同士の仲を深めるために大学院生が主体となって開催した、昨年のバーベキューでしょうか。
真野教授:「バーベキュー」とだけ聞くと普通のことのように思われるかもしれませんが、コロナ禍は大人数で集まることが困難な時期でした。コロナ禍前は定期的に交流の場を設けていたのですが、中止していたのです。
世の中が落ち着く中、再開を見計らうことが難しかったのですが、大学院生が中心となって慎重に企画を進めてくれたことで、ようやく再開することができました。
― やはり、コロナ禍前のほうが活動はしやすかったですか?
真野教授:実は、清掃活動の一環としてカヌーを使用していました。しかし、川の水位が低下し、清掃エリアの一部が泥地と化してしまったため、カヌーを使った活動ができなくなってしまいました。
原因ははっきりしていませんが、2019年に発生した台風19号の影響で川の流れが変わったか、または温暖化による影響かもしれません。残念ながら、現在はカヌーを楽しめる状態ではなくなってしまいました。
カヌーが活動の目玉の一つではあったので、私にとっては大きな課題です。まずは、年に一回は実施でるようになればと思っていますが、自然環境が相手となっては、どうしようもない部分もありますね。
外部団体との連携活動で深まる高麗川かわガールの意義
― 特に印象に残っている活動や、特徴的な活動・イベントはありますか?
土屋さん:強く印象に残っているのは、やはり外部の方々との関わりです。昨年は、栃木県の団体「百目鬼(どうめき)川をきれいにする会」と交流し、環境活動に取り組みました。
▼ 詳しくはこちら 【埼玉坂戸キャンパス】栃木県益子町の「百目鬼川をきれいにする会」と城西大学「高麗川かわガール」との交流研修会が行われました(josai.ac.jp)
彼らは栃木を拠点に環境活動を行っており、私にとっては初めて外部との情報交換ができる機会となりました。普段はなかなか接点を持てない方々との交流を通じて多くの学びを得ることができ、活動の意義を深く理解する機会になったと感じています。
当日は高麗川に来ていただき、私たちがいつも取り組んでいる活動に参加してもらいました。清掃活動の後は近郊の弓削田醤油で工場見学をしたり、一緒に昼食をとるなど、さらに交流を深めました。
真野教授:この交流活動のセッティングは、卒業生である大澤くんに一任しました。彼が先方との連絡やスケジュール調整、バスの手配など、この経験を通じて彼の調整力やスキルが向上した印象を受けましたね。ここまでの話は、我々が主体となって外部から支援を受けるケースでしたが、逆に他の環境団体に助っ人として参加することもあります。


土屋さん:例えば昨年の夏、私はNPO荒川流域ネットワークという団体の「アユ漁体験と魚捕り」のイベントにサポートとして参加させていただきました。

真野教授:土屋さんにサポートしてもらったのは、高麗川で行われた100名ほどが集まるイベントです。地引網をつかった漁でアユなどの魚を獲り、参加者の方に自然に触れたもらったり、魚を振るまったりしています。
▼ 詳しくはこちら 【医療栄養学科】【医療栄養学専攻】【取組】【管理栄養士とSDGs】「鮎を獲って食べる」子どもたちの環境教育•食育プログラムをサポート(josai.ac.jp)
土屋さんには、私と松本 明世教授が高麗川で捕った約200匹のアユを調理し、塩焼きにして参加者の方々に提供する手伝いをお願いしました。参加者である親子にアユの塩焼きを提供することで、管理栄養士を目指す学生たちにとって、食べ物と環境が密接に繋がっていることを実感してもらえたのではないかと考えています。
土屋さん:当日は200匹のアユを調理するだけでもかなり大変だったのですが、頑張りました。当日の経験はとても印象に残っています。
JOLA2024優秀賞受賞がもたらした活動の広がりと改善点
― 今年、「ジャパン・アウトドア・リーダーズ・アワード」(JOLA2024)にて優秀賞を受賞されていらっしゃいました。学外との連携などを含め、周囲や学生の方々、活動に関する変化はありましたか?
真野教授:まず、「ジャパン・アウトドア・リーダーズ・アワード」にノミネートされるためには、自分たちの活動を振り返った文書を作成しなければなりませんでした。いわゆる大学の「ルーブリック評価」のように、活動の良かった点や悪かった点を自己評価しなければならないのです。
▼ 詳しくはこちら 【医療栄養学科】城西大学の環境ボランティアグループ「高麗川かわガール」が活動10年(josai.ac.jp)
この評価を行うことで、私たちの活動にどのような点が欠けていたかが明確になり、独自の方法やメソッドの開発が不足していることがわかりました。そこで、他の団体がどのような活動をしているのか調べたところ、多くの団体が自分たちの活動に関する書籍を出版していることがわかりました。私たちもそのような活動を検討しなければならないと感じており、改善点や今後の取り組みが見えてきたと感じます。
このアワードは、学校教育としてキャンプや飯盒炊爨(はんごうすいさん)などの野外活動に関わっていた団体の方々が中心となって作られたもののようです。野外教育的な視点が組み込まれており、私たちもその意義を実感することができました。
また、受賞式ではさまざまな団体の方々と出会い、新たな繋がりを築くことができました。例えば、今回のアワードには多くのアウトドアメーカーが協賛されていました。そのなかの、某メーカーと連携できないか協議中です。大学とアウトドアメーカーの連携事例はまだ少ないため、ぜひ実現させたいですね。
今後の展望

― 新たに始めたいことや注力したいことなど、皆さんの今後の展望を教えてください。
勝又さん:私が新しく取り組みたいプロジェクトの一つとして、外来種の駆除があります。たとえば、高麗川に生息するコイやアカガミはアユの稚魚を食べてしまうため、これらの駆除活動を始めたいと考えています。
具体的な取り組みとしては、ミシシッピアカミミガメを捕獲し、その甲羅を肥料として利用する手法があります。城西大学の近くにある畑で、この亀の甲羅を使った肥料の効果を試してみることはできないかと思っています。
小山さん:私は、来年度には研究室のゼミ生が約3人入る予定なので、現在の活動を次世代に引き継いでいきたいと考えています。また、高麗川には大きなコイが生息しているため、個人的にはこれらのコイの観察にも挑戦したいと思います。コイの生態や行動について詳しく学びたいです。
土屋さん:私は、活動参加の人数を増やすことに注力したいと考えています。現在は大学院生やOBが中心となって活動していますが、今後は学部生の参加も増やせるように、運営方法や日常のコミュニケーションを工夫し、高麗川かわガールの活動を広く伝えていきたいです。
また、先ほどの外来種駆除に関する話を受けて、駆除した生物や植物を利用した新しいレシピの開発も面白いのではないかと思います。このような取り組みが実現すれば、活動の可能性もさらに広がるのではないでしょうか。
真野教授:私から補足すると、本学では数年前まで土曜日も授業が行われていました。当時の高麗川かわガールのメンバーは、土曜日の授業前に1時間活動していました。しかし現在は、土曜日の授業が廃止されたため、大学院生は土日も研究を続けておりますが、学部生の参加が難しい状況です。この点については、改善を検討する必要があるかもしれませんね。
私の今後の展望としては、まずは2025年の周年展示「高麗川物語」を学生たちと協力し、しっかりと良いものにしたいと考えています。2025年秋に城西大学坂戸キャンパスの水田美術館で開催しますので、足を運んでいただければ嬉しいです。
