
SDGs 大学プロジェクト × Takamatsu University and Junior College. -Part 2-
目次
高松大学・高松短期大学の紹介


学校法人四国高松学園は、高松短期大学を1969年、高松大学を1996年に開学しました。
高松大学には発達科学部子ども発達学科と経営学部経営学科、高松短期大学には保育学科とビジネスデザイン学科、大学院には経営学研究科を設置しています。
建学の精神として掲げているのは、「対話にみちみちたゆたかな人間教育をめざす大学」「自分で考え自分で行なえる人間づくりをめざす大学」「個性をのばしルールが守れる人間づくりをめざす大学」「理論と実践との接点を開拓する大学」です。
2020年8月には、人口減少や情報化・グローバル化の進展等、時代の変化や社会の要請に的確に対応できるように、「Vision2030」を策定。「対話と実践」を重ね、人や地域、世界とのつながりながら、地域の未来を切り拓く方向性を打ち出しました。
地域とのつながりに関しては、大規模災害などに備え、「高松市機能別分団 高松大学防災サポートチーム」を結成。本学の学生によって構成され、避難者の湯堂や指定避難所の運営支援などの活動を行います。また、大規模災害が発生した際は、大学内の施設の一部を一時避難施設として使う予定です。
さらに、香川県内の高等教育機関や産業界、自治体とともに「大学・地域共創プラットフォーム香川」を構成し、オール香川の産官学で「人づくり・地域づくり」に取り組んでいます。
高松短期大学 ビジネスデザイン学科の紹介
ビジネスデザイン学科は、秘書科(1983年に創設)の伝統ある教育を継承し、デザイン思考を新たに取り入れ、2024年4月に学科名称を変更してスタートしました。
ビジネスデザイン学科の教育研究上の目的は、「職業人としての幅広い教養と高度なビジネスの専門知識・技能を有し、社会人としての基本的なマナーや品位を備え、周囲からの信頼を得て、第一線で活躍する人材を育成すること」です。
ビジネスの現場で必要な幅広い教養、ビジネスの基本知識、マナー、職業人としての高度な知識や技能を身につけるための科目をバランスよく配置し、理論と実践を体系的に学べるよう配慮しています。さらに、少人数制の研究室活動や現場での実習、地域との連携・交流を通して、人間性や実践力を高めます。
中でも、学生個々がビジネスの原理を理解した上で、実際に香川県産品を素材とした商品開発に取り組み、販売戦略を考案することにより、ビジネスの全体像を体験的に学習することを目的とした「さぬきマルシェ」への出店についてご紹介したいと思います。
実践で学ぶビジネス力 「さぬきマルシェ」出店への挑戦

― ビジネスデザイン学科で取り組まれている「さぬきマルシェ」への出店について、まずはお取り組みの概要を教えてください。
ビジネスデザイン学科では、学生が実際に商品販売を体験することにより、ビジネスについて学ぶことを目的として、「さぬきマルシェ」への出店を行っています。
この取り組みは、学科の専門科目である「ビジネスデザイン」と「ビジネスデザイン演習」の一環として実施されており、学生は商品の仕入れから販売までを担っています。出店準備はもちろん、マルシェ会場では、学生たちが屋外にテントを設け、地元の業者から仕入れた商品を実際に販売するという取り組みです。
▼ 詳しくはこちら さぬきマルシェinサンポート高松に出店しました!( takamatsu-u.ac.jp )
「さぬきマルシェ」は、香川県産の食材や加工品を生産者が直接販売する、屋外型の市場イベントです。JR高松駅やシンボルタワーの整備など、高松港の再開発とともに、2011年にスタートして以来、地域の賑わいづくりに貢献していくために始まったと聞いています。


― 「ビジネスデザイン」や「ビジネスデザイン演習」では、どのようなことを学べるのでしょうか?
本学科の卒業生は、商業関係や金融関係、医療関係など、多くの人々と関わる企業や医療機関などに就職する傾向があります。「ビジネス」という言葉には、公的機関から営利企業まで幅広い活動が含まれますが、とりわけ企業の受付窓口や販売の現場では、不特定多数のお客さまを相手にすることが多くありますよね。そこで、学生が職業人として必要となるコミュニケーション能力やビジネススキルを養うため、「ビジネスデザイン」を開講しました。
したがって、「さぬきマルシェ」への出店は、座学で学んだ知識を活かすための実習の場と位置付けています。「ビジネスデザイン演習」では、授業で学んだことに基づき、業者からの仕入れや、お客さまへの販売など、ビジネスの一部分を実践することで、学生の理解をさらに深めることをめざしています。
2011年に始まった「さぬきマルシェ」は、開始当初は全国的にも珍しいイベントの一つでした。本学科では、この貴重な機会を学生に提供することで実践的な学びの場を創出したいと考え、長年にわたり取り組んでいます。
近年では、マルシェが全国的に広がっており、「さぬきマルシェ」でもキッチンカーの出店が増えるなど、初期と比べてその形態は随分と変化しました。環境の変化や時間の経過に伴って、より多様な楽しみ方を提供する場へと進化を遂げていると感じています。
商品企画から販売まで!学生が体験するビジネスの難しさ


― 「さぬきマルシェ」への出店にあたって、学生の方々はどのような役割を担っていますか?
学生は、商品の仕入れから販売、店舗装飾に至るまで、ビジネスにおけるさまざまな実務を経験しています。特に、5月から7月ごろの天候が変わりやすい上に、暑くなる時期に出店を行うため、適切な商品の仕入れ量を予測することが重要な課題となります。この経験は、将来ビジネスに携わる上で必ず直面する重要な問題であることから、特に力を入れて学んでもらっています。
店舗装飾では、販売のターゲット層を明確にし、それに合わせた魅力的なディスプレイを考案することが求められます。特に、客層の設定に重点を置き、お客さまの目を惹く工夫を凝らすことで、商品をより効果的にアピールし、購買意欲を高めることをめざしています。
また、マルシェ当日の接客では、お客さまへの呼び込みや商品説明など、臨機応変な対応力が求められます。事前に全ての対策を完璧に立てることは難しい部分もありますが、授業でも可能な限り心構えを養ってもらっています。
何よりも大きなポイントは、仕入れた商品を全て売り切ることです。これは学生にとっても大きな目標であると同時に、大きなプレッシャーでもあります。しかし、仕入れが少なすぎてしまうと、成果としては不十分です。大きな儲けを生み出すことが目標ではありませんが、計画的に商品を仕入れ、売り上げ目標を達成できた時の達成感は、学生のモチベーションを大きく高めていると感じます。
ちなみに、将来的には学生自身が企画したオリジナル商品を販売することをめざしています。そのために毎年オリジナル商品を企画し、企業へのプレゼンテーションを行っていますが、商品化にはまだ多くの課題がありますね。今後も学生とともにこれらの課題に取り組み、実現に向けた努力を続けていきたいと考えています。
― 特産品を販売される際の工夫や特徴、課題などはありますか?
特別なこととは言えないかもしれませんが、学生は販売する商品について、事前に試食や食べ比べを含めた調査を行い、商品の魅力や特徴をしっかりと把握しています。マルシェ当日はお客さまからの商品の味や原材料に関する質問に的確に答えられるよう、事前に商品知識を蓄えておくことは非常に重要です。
現在、本学では3つの業者と連携し、蜂蜜製品、卵製品、寿司を仕入れて販売しています。これらの商品は、「さぬきマルシェ」の実行委員の方々によって選定された地元の特産品です。
もちろん、既存の特産品を取り扱うからこその課題も存在します。学生が販売する商品は、仕入れ元の実店舗でも販売されているため、マルシェの店舗はいわば「チェーン店」のような位置付けになります。実店舗には、魅力的なロケーションがあり、マルシェでは取り扱っていない商品が揃っており、さらに根強いファンも存在します。そのため、学生の出店が実店舗にとって「ライバル」となる側面もあるのです。
そのため、マルシェへの出店では、実店舗と共存し、お互いを補完し合う関係を築くことが求められます。私たちは、マルシェでの出店を単なる販売機会と捉えるのではなく、実店舗の広告塔としての役割を果たし、今後はさらに多くのお客さまを実店舗へ誘導することを意識していく必要があると感じています。
マルシェが育む、学生たちの成長と変化

― さぬきマルシェへの出店を通じて、学生の方々からどのような変化や成長を感じられていますか?
マルシェ当日は、学生の意外な一面を発見することがあります。普段は控えめな学生が、お客さまへの呼び込みでは大きな声を出してくれたり、周囲の変化に臨機応変に応対してくれる学生がいたりと、授業ではなかなか見られないこれらの一面に、驚かされることも少なくありません。
さらに、学生はそれぞれに得意な役割を持っており、自然と役割分担を行いながら協力しています。約3ヶ月間にわたる準備期間を通じて、ビジネス現場で必要とされるさまざまなスキルやその過程での苦労を学んでくれていると感じます。
― 出店に向け、初めての経験も多いなか、学生の方々はどのように連携されていますか?
学生の中には、グループワークの経験が豊富な学生もいれば、そうでない学生もいるため、全員が同じ方向に向かって取り組むには、ある程度の時間と工夫が必要です。
特に、コロナ禍の影響で高等学校における対面でのグループワークの機会が減少したことで、グループワークに苦手意識を持つ学生が増えていると感じています。グループワークのスキル向上は、教員にとっても重要な課題の一つになっていますね。また、「ビジネスデザイン」は1年生後期から始まるため、入学から半年経ったタイミングでは、学生同士の距離感が近いとは言い切れないこともあり、スムーズな連携が難しい場合があります。
このような背景から、毎年11月に行われる大学祭での模擬店出店を、「さぬきマルシェ」に向けた重要なステップとして位置付けています。大学祭での経験は、学生の協調性を高める機会にもなり、団結力を深めることに繋がっています。
実際に、大学祭やマルシェの準備などを通して、学生のコミュニケーション能力は大きく向上します。特に、大きな売上を上げ、目標を達成したときの達成感は、学生のモチベーションを大幅に高めるだけでなく、自信と学生同士の信頼へと繋がっていますね。
今後の目標と展望

― 今後、新たに取り組みたいことやさらに注力したいことなど、将来の展望や目標を教えてください。
なによりも「本学オリジナル商品をつくりたい」というのが、現在の私たちの最大の目標です。既存商品の販売だけでなく、独自の商品企画から販売、そしてその後の展開に至るまでの一連のプロセスを、学生たちが経験できる授業を実施したいと考えています。これにより、学生たちはビジネスの幅広い工程を体験し、より実践的なスキルを身に付けることができるでしょう。
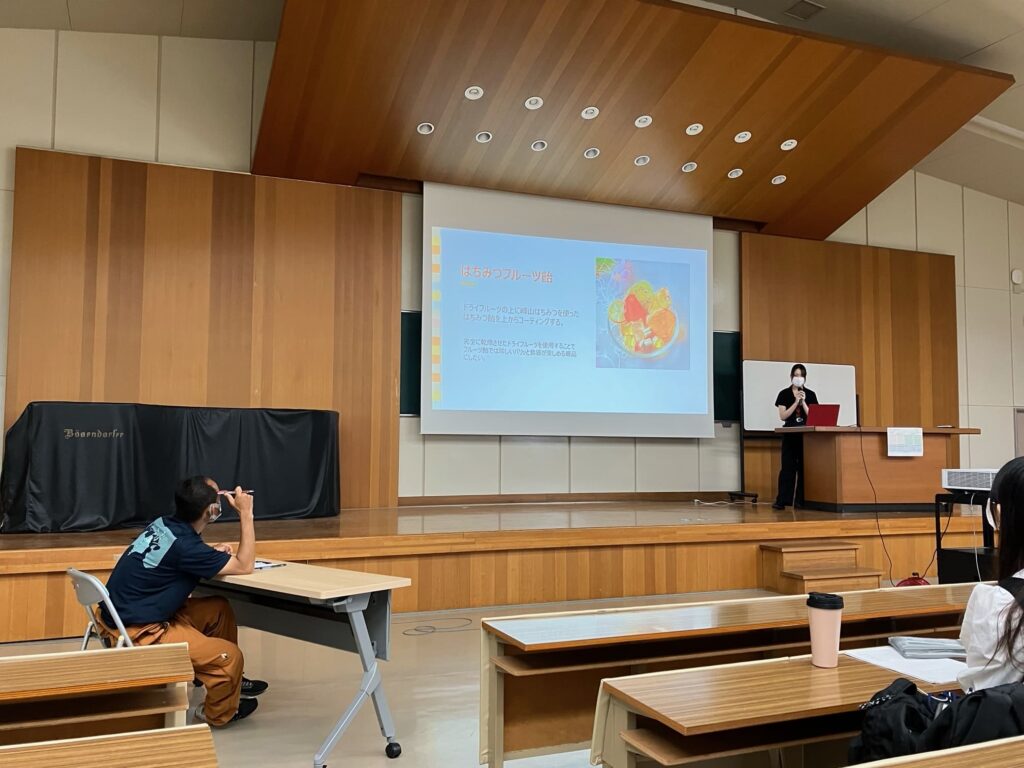

また、先ほど「学生が企画した商品を企業の方々にプレゼンテーションする機会を設けている」とお話ししましたが、学生は毎年入れ替わるため、ノウハウの継承が大きな課題となっています。特に2年制である短期大学では、卒業までに商品を完成させることが難しく、途中まで築き上げた成果を次の世代に繋げる仕組みづくりに課題を感じています。
教師としては、学生が職業人になる前に、将来の仕事に繋がる実践的な経験を積ませたいという強い思いがあります。オリジナル商品の開発によって新たな課題も生まれるでしょうが、それらもまた学生の成長を促す絶好の機会となるため、試行錯誤の最中です。
近年の「さぬきマルシェ」では、オリジナル商品を販売する高校生のブースも目立つようになってきました。今後は、大学入学前から商品開発を行った経験を持つ学生も増えてくることでしょう。そこで本学では、より高度な商品開発の授業を展開し、学生たちのスキルアップを支援したいと考えています。
また、本学科は、今年度から「ビジネスデザイン学科」に名称を変更しています。
▼ 詳しくはこちら 高松短期大学ビジネスデザイン学科 公式サイト( takamatsu-u.ac.jp )
名前が示す通り、本学科では「ビジネスとは何か」「デザイン思考とは何か」とという2つの観点を重視し、それらを組み合わせた教育を行っています。学生たちがビジネスの現場でデザイン思考を活かせるような人材に成長することをめざし、今後もさまざまな取り組みを進めていきたいです。
