
SDGs 大学プロジェクト × Kanazawa Institute of Technology.
目次
金沢工業大学の紹介


金沢工業大学は、石川県野々市市(ののいちし)に位置する私立大学で、1957年に北陸電波学校として開講したのがはじまりです。その後、1965年に金沢工業大学を開学し、工学部機械工学科、電気工学科が設置され、現在では工学部、情報フロンティア学部、建築学部、バイオ・化学部の4学部12学科を擁しています。
教育実践目標として「自ら考え行動する技術者の育成」を掲げ、問題発見から解決にいたる過程・方法をチームで実践しながら学ぶオリジナルの教育を展開しています。また、企業や自治体・団体等に勤務する社会人共学者による授業参画も推進。それに加え、世界最高峰の米国研究開発機関と共同して「イノベーション力」教育を行っており、金沢工業大学は世代や分野、文化を超えた共創学修で「グローバルな視野」と「イノベーション力」を実践的に身につけることができます。
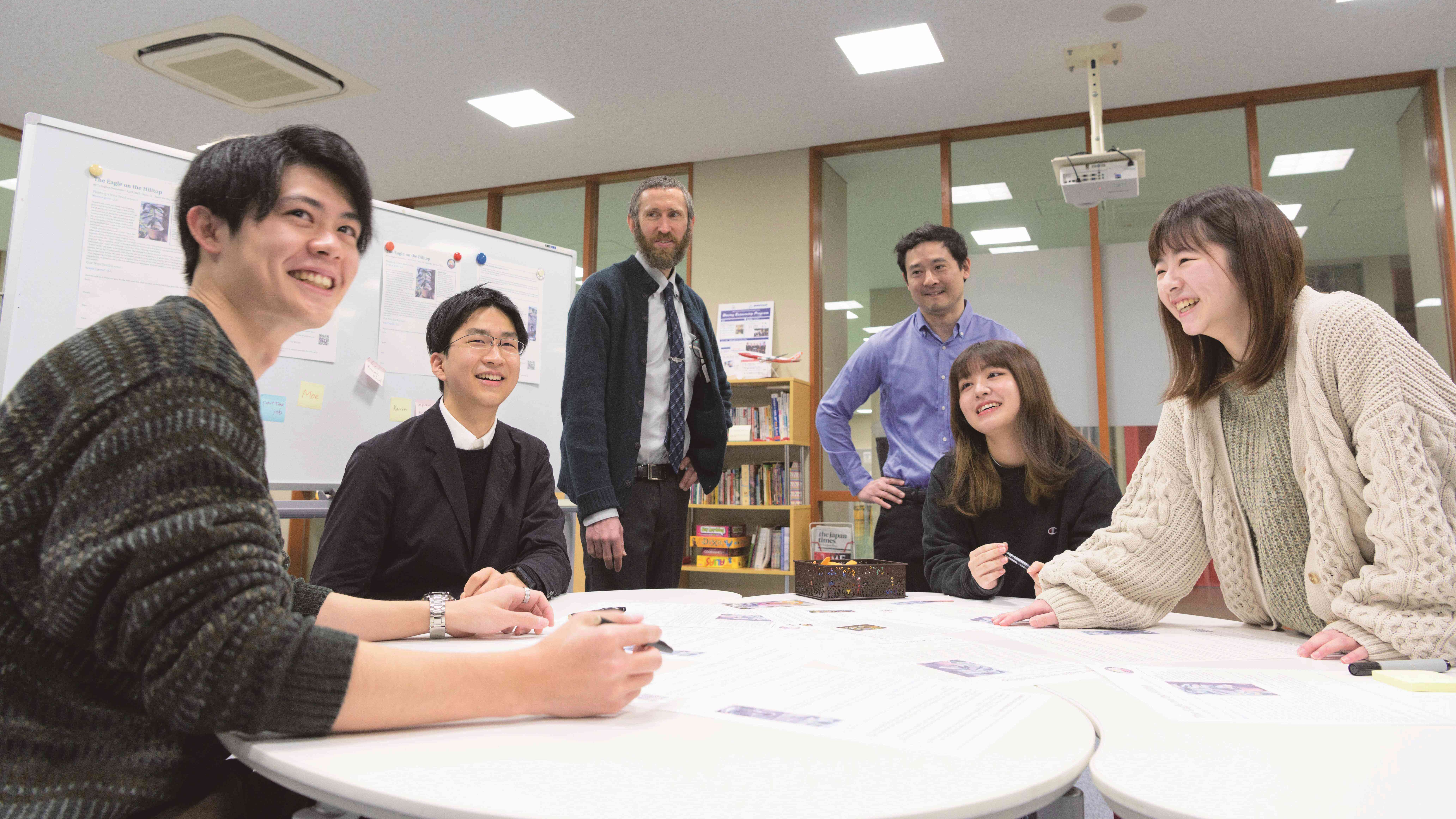
また、キャンパス内には学生のアイディアをカタチにする「夢考房」という支援施設があり、モノづくりの一連のプロセスを体験すると共に、スケジュール管理、予算管理、組織運営を学生が主体的行う「夢考房プロジェクト」が課外活動として運営されています。金沢工業大学では、夢考房プロジェクトのほか、各学科の研究室やSDGsに関わるプロジェクトなど50を超える課外活動に学生が所属しています。
現在世界は、持続可能な社会の実現(SX:サステナビリティトランスフォーメーション)に向けて大きく変化しています。世界の国々やグローバル企業などでは、地球環境と経済成長を両立させ、産業構造の変革を図るGX(グリーントランスフォーメーション)、ビッグデータやAI、IoTなどのデジタル技術を活用して新たな製品やサービスを生み出し、ビジネスを変革させるDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現する社会が求められており、金沢工業大学は、世界が目指す持続可能な社会を実現するために、2025年度より6学部17学科体制へと進化し、文理の枠を超えた教育の実践を目指しています。
第一回内閣官房長官賞を受賞したSDGs推進センター

-SDGs推進センターの設置経緯について教えてください。
SDGs推進センター 薮内様:SDGs推進センターは、日本の地方から地球規模課題の解決策を創造・拡大していくため、また全学体制でSDGsアクションを推進するために学部学科の「横串を通す役割」として2017年12月1日に開設されました。
このセンターはSDGsアクションを推進するに加えて、学内外の様々な活動を結びつけるハブ機能としても役割を果たしています。
設立された年には、SDGs達成に寄与する優れた取り組みを行っている企業や団体を表彰する第一回ジャパンSDGsアワードにおいて、推進副本部長(内閣官房長官)賞を受賞した実績があります。
SDGsについての学びを深めるSDGs推進センター
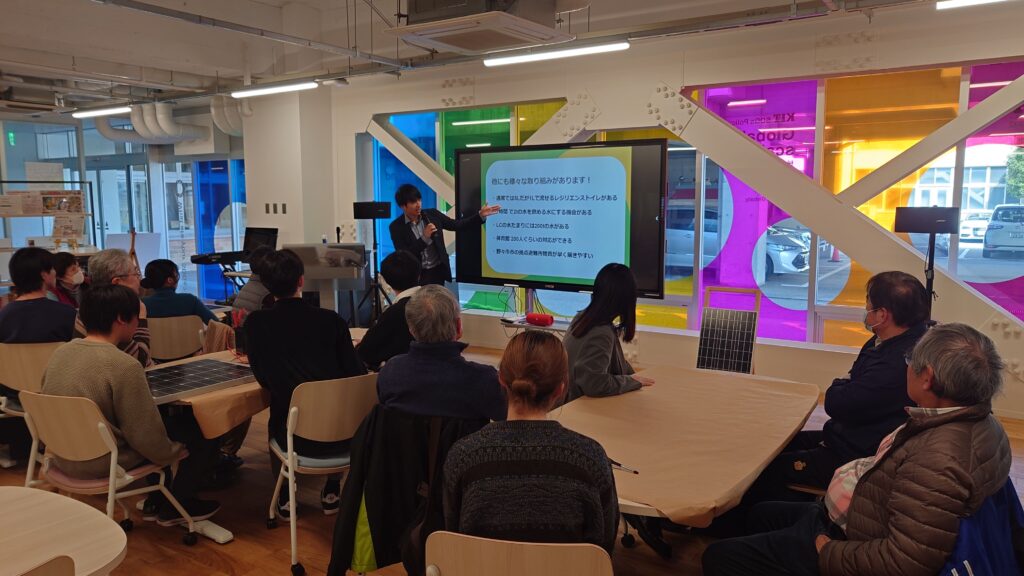
-SDGs推進センターについて教えてください。
SDGs推進センター 薮内様:SDGs推進センターの主な取り組みには、本学におけるSDGsへの取り組みを中心に、ゲーミフィケーション教材の開発とその提供、ゲームを活用した行動変容を促すためのワークショップの開催などが含まれます。
また、情報フロンティア学部経営情報学科の平本教授がSDGs推進センターの所長を務めており、SDGsの活動に取り組む学生団体「SDGs Global Youth Innovators」の活動拠点や平本研究室をはじめとしたゼミ生がSDGsに関する研究の場としても活用されています。
「私たちは私たちの未来を救うために」を理念に、SDGsに取り組むSDGs Global Youth Innovatorsには、大学2年生や3年生を中心に、大学院生も含め、約30名ほどが所属しています。このセンターでは、学生たちの活動を支援するために、大学の教授や准教授、大学職員、大学の研究員も関与しています。これにより、多くの人々とのつながりが生まれています。


イメージとしてはサークル活動に近いかもしれませんが、SDGs Global Youth Innovatorsの活動は学生団体としての活動となります。学生団体での活動を通じて、SDGsに関する取り組みが評価されて表彰されたこともあります。そのほかにも、学外からの依頼で行われるSDGsに関するイベントへの出展や自治体や企業・団体への研修なども、学生が中心となって行っています。
活動分野としては大きく、ビジネス分野・教育分野・地域デザインの3つに分かれて活動していますが、これらの中で特に力を入れているのは教育分野です。
本学がある野々市市内の学校に対してはもちろんのこと、日本全国にSDGs教育を普及させるために、教材の作成や研修を行っています。ビジネス分野では、実際に企業の方と関わりながらSDGsに関するゲーム作りをしています。また、地域デザインにおいては、本学が所在する野々市市のまちづくりを学生が主体となって行ったり、自治体と共同で地域の課題解決に取り組んだりしています。
本学は教育機関ですので、このような活動を通じて、より多くの方々にSDGsに関する視点を持っていただき、学びを深めていただけることを願っています。
「ゲーム × SDGs」で学びを深める手助けを
「楽しくゲームをしながらSDGsに関する学びを深めてほしい」との想いから、さまざまなゲーム開発に取り組むSDGs推進センター。
ここでは、SDGs推進センターの薮内様のほか、金沢工業大学大学院修了生で、現在はゲーミフィケーション教材を開発する株式会社LODU(ロデュ) COOの亀田様にもお話を伺いました。
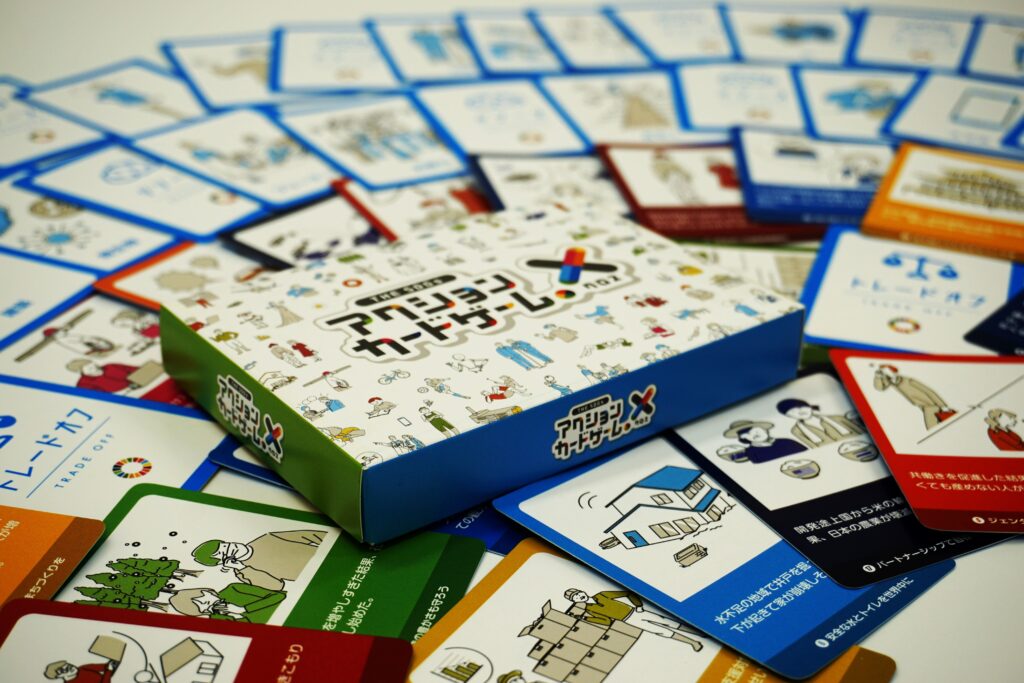
-SDGsを学べるゲーム教材が誕生した背景について教えてください。
SDGs推進センター 薮内様:SDGs推進センターでは、これまでにいくつかの教材を開発していますが、特にフォーカスしているのは、ゲーミフィケーション教材です。
ゲームにフォーカスしている理由として、本学大学院修了生でもある株式会社LODUの亀田さんが在学中にされた、とある教授とのやりとりがきっかけです。
株式会社LODU 亀田様:私はもともとゲームが好きでしたので、大学2年生くらいまでは、課題や授業等の最低限のことをし、あとはゲームだけをするという生活を送っていました。
しかし、このような生活の中でも、どことなく社会課題の解決自体には多少の興味がありました。現在SDGs推進センター所長であり、情報フロンティア学部の平本教授にSDGsの存在を教えていただいたのを機に、私自身もSDGsについて調べていくうちに、より関心が高まりました。
世界を良い方向に持っていこうとするSDGsへの動きに対し、全世界の国々のリーダーたちが合意して推進していることに強い感銘を受けたからです。このような思考が高まってきた中で、平本教授からも「SDGsに関する取り組みを何かしてみないか」と声を掛けられたのがきっかけです。
平本教授は私がゲームに対して高い関心を持っていることをご存知で、2年生の頃に「SDGsとゲームを組み合わせたゲームの開発をしてみてはどうか」と提案してくださり、平本教授のご支援を受けながらゲーム開発に取り組むこととなりました。

その当時、薮内さんは大学は別であったものの、一緒にゲーム開発に取り組んでくれた一人です。ゲーム開発するにあたって資金も必要でしたので、クラウドファンディングを活用しました。結果、クラウドファンディングは大成功で「自分の好き × 課題解決」が、多くの方々のご支援と評価につながったことに喜びを感じました。
私は、SDGsや社会的な課題解決に関するビジネスは、非常に意義のあるものだと思っています。サステナビリティと幸福、楽しさ、快適さをトレードオフにさせないという部分に重きをおいてきました。このトレードオフの部分は比較的若者からネガティブに捉えられがちであるため、「ゲーム」という楽しさの要素を取り入れたことがクラウドファンディングの成功要因であると考えています。
最初に開発したゲームであるTHE SDGsアクションカードゲーム「X(クロス)」は今でも根強い人気があり、「ゲーム × SDGsに関する学び」は多くの人々に受け入れられています。今後も平本教授や仲間と共に、引き続きゲーム開発を進めていく予定です。

SDGs推進センター 薮内様:開発したゲームを授業に取り入れてもらい「ゲームが楽しかった」という感想をいただくのも大切ですが、本学で開発しているゲームは「楽しさと学びを両立させたもの」をコンセプトとしています。
ゲームを通じた学びにとどまらず、さらにSDGsについての理解を深めていただきたいとの考えから、ここ数年でゲーム以外にもテキスト教材や動画教材の開発に取り組んでいます。
昨年度までの5年間においては、文部科学省の補助授業の一環として、SDGsの教育を展開するツールとして本学で開発したゲームに加え、より深い知識を提供するためにブラッシュアップされた教材も制作しました。
これらの教材は、ホームページ上で無償で公開しており、興味を持たれた先生方にも負担なく活用していただけるようにしています。また、SDGs教育を楽しく広めるための取り組みにも力を入れています。
▼ 詳しくはこちら SDGs Education -教育プロジェクト- (kanazawa-it.ac.jp)
SDGs教材ゲーム「コレクティブ・インパクトゲーム」開発秘話
「コレクティブ・インパクト」とは、企業や行政・NPO・市民など、さまざまな分野の人々が各領域を越えて、共に社会問題に取り組むことで生まれる成果を意味します。
「コレクティブ・インパクト」という言葉は、2011年にスタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビューにて発表されてから世界各地で実践されており、環境問題やヘルスケアの問題など多くの社会問題の解決に役立っています。
SDGs推進センターが株式会社LODU、スマートシティ・インスティテュート、東京海上日動火災株式会社と製品化した「コレクティブ・インパクトゲーム」について、伺いました。
コレクティブ・インパクトゲームとは?
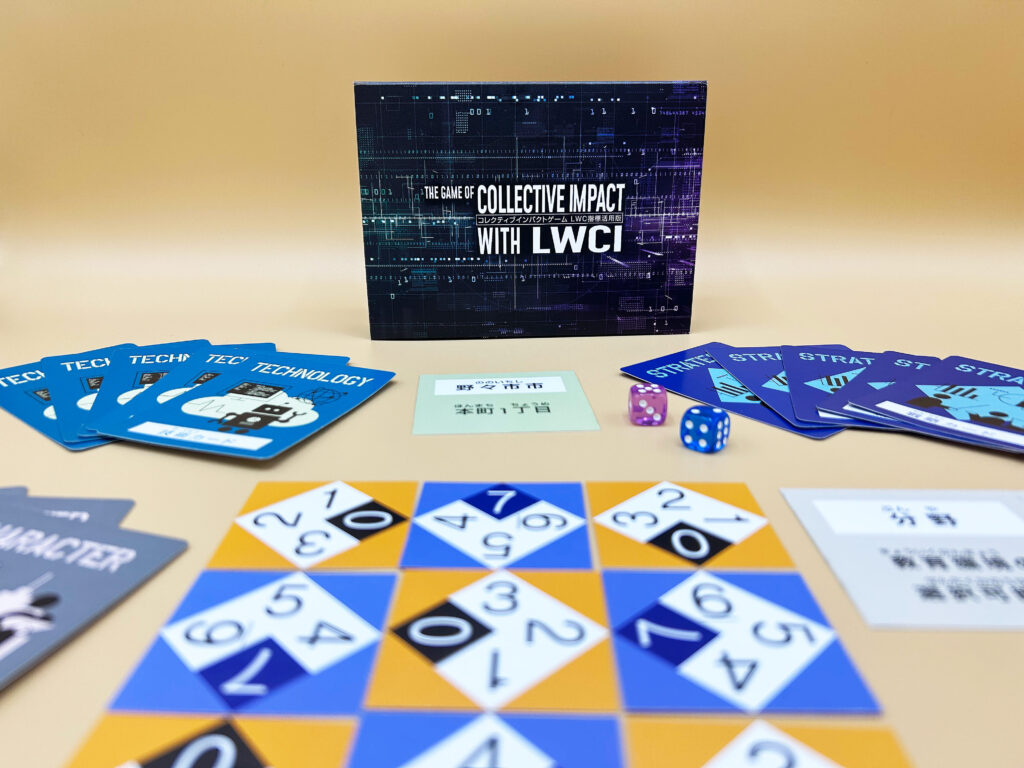
-コレクティブ・インパクトゲームとは、どのようなゲームか教えてください。
株式会社LODU 亀田様:コレクティブ・インパクトゲームは、2つのサイコロを振って遊ぶゲームで、対象年齢は10歳からが対象です。
基本的にプレイヤーは、自治体・教育機関・自治体・市民という4つのキャラクターになりきり、協力し合ってWell-beingのまちづくりを目指すのが目的です。
Well-beingとは:「well(よい)」と「being(状態)」を組み合わせた言葉であり、個人や社会における良好な状態を指します。すなわち、人々が「心豊かな暮らし」を実現することを目指す概念です。 サイコロのほかにボードを使用しますが、ボードには縦6つ、横6つの計36個のマスがあります。
ゲームを始める際、まず最初に任意の自治体を設定します。次に設定した自治体に実在する地域6つとLWC指標6つを選定します。
LWC指標とは:Liveable Well-Being City指標の略で、市民の「暮らしやすさ」と「幸福感(Well‐Being)」を指標で数値化・可視化したもの。
例えば、金沢工業大学がある野々市市(ののいちし)を自治体として選んだとしましょう。次に、LWC指標にある「健康分野」を選定した場合、36マスあるうちの1つは「野々市市の健康分野」というマスができます。
このように、ボード上にある36マスすべてに「地域 × LWC指標の項目」を設定していきます。36個あるマスは最初はレベル1からスタートしていきますが、サイコロを2つ振って出た目で、設定した36マスのどこかに該当し、そのマスのレベルが1上昇するという仕組みです。また、これは「野々市市の健康分野」が少し良くなったということを表しています。これを繰り返していくことによって、どんどんウェルビーングなまちにしていくことがこのゲームのゴールです。
また、単純にまち全体のウェルビーングを向上させていくのとは、別にキャラクターごとに設定されている個人ミッションも存在しています。
例えば教育機関であれば、教育分野を全部の自治体で上げることをクリア条件にしたり、マスの中には個人ミッションのマスもありますので、個人の努力でレベルをあげたりすることもできます。
その際に、それぞれのプレイヤーに配布される技術カードや、ゲーム中に獲得できる戦略カードを使用すると、ミッションを制限時間内に達成させていきながら、レベルアップも図ることができます。
SDGs推進センター 薮内様:各プレイヤーがキャラクターとして、Well-beingを目指すのですが、プレイヤーAさんが教育分野の担当であれば、教育の質を上げるのを個人ミッションとして目指していきます。
個人ミッションとは別に全体のミッションもありますので、全体ミッションは皆んなと協力しながら、Well-being指標の高いまちをつくっていくといった感じで進めます。
コレクティブ・インパクトゲームでWell-Beingの意識を高めたい

-1024x576.jpg)
-コレクティブ・インパクトゲームへの製作者側の想いを教えてください。
株式会社LODU 亀田様:先ほども触れましたが、コレクティブ・インパクトゲームのベースとなっているものは「Well-Being(地域幸福度) 指標=Liveable Well-Being City指標(以下LWC指標)」です。
SDGs推進センターと東京海上日動火災株式会社、弊社が共に開発したコレクティブ・インパクトゲームは、LWC指標を作成・開発された一般社団法人スマートシティ・インスティテュート(以下SCI-Japan)さんにお墨付きをいただいた公式ゲームです。
LWC指標のようなWell-Beingに関する指標は、自治体が中心でやるものという印象が強いですが、自治体だけで進めるものではなく、企業や市民、教育機関などを巻き込みながら、より大きなインパクトへと発展させていく必要があります。
コレクティブ・インパクトゲームの開発にあたり、最初は手探りの状態が続きました。しかし、LWC指標を提唱したSCI-Japanの南雲さんにお話を伺ったり、平本教授や学生とテストプレイや話し合いを重ねる中で、約1年間の試行錯誤を経て、ようやく開発に至りました。
コレクティブ・インパクトゲームのワークショップを開催する中で、皆さんから好意的な反応やご意見をいただいたことで、私自身もコレクティブ・インパクト向上への想いがより一層強くなっています。
コレクティブ・インパクトゲーム開発で苦労した点
-コレクティブ・インパクトゲームの開発で苦労した点を聞かせてください。
株式会社LODU 亀田様:LWC指標の普及に取り組んでいる自治体がありましたが、オープンデータの活用というワードだけでとっつきにくい印象があり、難しい概念だと煙たがられてしまうという課題があるとよくお聞きしました。また、市民の方々をどのように巻き込めばよいか、悩んでいる自治体も少なくありませんでした。
そのため、もしLWC指標に関するゲームがあれば、勉強会などでのアイスブレイクや学びの入口としての利用に適しているかもしれないと、テストプレイの段階から手応えを感じていました。
ゲームに対するニーズはあるものの、難易度を上げずにゲームが苦手な方でも楽しんでいただくための工夫は、どのゲームにおいても重要です。
私たちのゲーム開発では、従来のゲームシステムを踏襲せず、すべてを新たに設計したことを特徴としています。これにより、今までになかった別の調整やゲームデザインが求められ、ゲームが学びと紐づくようにもしなくてはいけない部分に非常に苦労しました。
さらに、ゲーム時間を短くしながら難易度を下げつつ、楽しみながら学びをどう深めていくかという部分は永遠のテーマとなっています。しかし、このような苦労する点があるからこそ、価値のあるゲームが提供できると思っています。
SDGs推進センター 薮内様:ワークショップ開催した際、企業の方や大学関係の方も集まってくださり、「ゲームそのものとして楽しかった」という意見をいただいた一方で、このような部分をもう少し強めた方が学びが深まるのではという意見等改善提案をいただくこともできました。
より良くするためのアドバイスがいただけると、やりがいにもつながります。いただけた意見を上手に反映できるようブラッシュアップに努めました。
LWC指標を活用しながら若者中心でウェルビーングなまちづくりを推進する

-ウェルビーングなまちづくりのために、具体的にはどういう取り組みが必要でしょうか。
株式会社LODU亀田様:ウェルビーングなまちづくりを推進するには、特に若者をどう巻き込んでいくか、若い世代にどのように広めていくかが課題と感じています。なぜなら、「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」によると、日本の若者は諸外国の若者と比べて自己肯定感が低いというデータがあるからです。
少子高齢化、人口の一極集中が進む中、地域の魅力の伸ばしつつ課題を解決していくためには、若者自身が自己肯定感を高めながら、自分たちの住みたいまちづくりに参加していくことが重要だと考えています。
LWC指標や、コレクティブインパクトは、それを促進するためのツールとして効果的なものです。具体的には、学生主体で、ウェルビーングなまちづくりを実現するためのアイディアコンテストがすでに実施されています。
ここで出たアイディアを、金沢工業大学の学生が多く住んでいる野々市市の市長や、南雲さん等に提言し、実際にアイディアを評価していただくものです。このコンテストで、賞を獲得した学生の中では、すでに市と連携しながらアイディアの実現に向けて動いているものもあります。アイディアは、LWC指標をベースに考えられているので、データを根拠にしながら若者が中心でウェルビーングなまちづくりを推進することができます。
アイディアコンテストはまだ始まったばかりですが、この取り組みを野々市市以外の自治体にも展開したりそれ以外の全く新しい取り組みを実施したりすることで、次から次へと若者がウェルビーングなまちづくりに参画し影響力を持てるような環境を作っていきたいと思います。
特に金沢工業大学は教育機関ですので、若者を多く巻き込んでコレクティブ・インパクトやWell-Beingの向上に努める必要があります。
SDGs推進センター 薮内様:亀田さんとは金沢工業大学の大学院で一緒に活動してきましたが、私はSDGsに関する活動を通じて、未来にポジティブな印象を持てるようになりました。
今、SDGsに取り組む本学の学生の中でも、まだまだ将来への不安や悩みを抱えている学生はいると思います。
しかし、私たちがSDGsに関する活動を通じて将来をポジティブに捉えられるようになったように、学生たちにもこの活動を通じて将来こんなまちづくりに関わってみたい、こういう活動をしたいなどポジティブな希望を持ってもらえたらと思っています。
株式会社LODU 亀田様:コレクティブ・インパクトゲームは決して若者がターゲットではありません。
若者だけでなく、より多くの方たちがこのゲームを通じて、コレクティブ・インパクトを生み出すためのまちづくりやWell-Beingについて考えるきっかけになればと思っています。
SDGs推進センターでの今後の展望
-SDGs推進センターでの今後の展望があれば教えてください。
SDGs推進センター 薮内様:SDGs推進センターの活動内容には、教育、ビジネス、地域デザインの分野が含まれます。この数年活動していく中で、これら3つにおける横断的な取り組みが増えてきました。
例えば、SDGs推進センターで開発したゲームを大学のある、野々市市での研修教材として活用されるケースがあります。また、研修を通じて指標が低かった場合、どのように指標を上げていく必要があるかを考える場面が増えてきました。
指標向上のためにも、SDGs推進センターが市民向けのワークショップをしたら良いのではという意見や、市民がさらに参画すると、より良いまちになるのではという意見も学生から寄せられています。
本学の学生も一緒になってまちづくりに参画することで、さまざまな関わりが生まれています。このように、本学が窓口になることで、より多くの方たちをつなげ、コレクティブ・インパクトや幸福度の向上に貢献できたらと思っています。
2025年4月にWell-beingをテーマにした新たな学科が誕生!
-貴学では来年度、新たな学科が新設されると伺いました。どのような学科か教えてください。
SDGs推進センター 薮内様:2025年4月に環境デザイン創生学科が新たに設置されます。この学科では、SDGsやWell-beingをテーマにした学びが深められる学科です。これらをメインにした学科ですので、まちづくりだけでなく、幸せとは何かを考えたり、実践的な授業を通じて学ぶことが可能です。
本学は工業大学というイメージがあるかと思いますが、この環境デザイン創生学科は文理融合型の学科として創設されます。理系大学でありながら、文系の方々が活躍できる点が特徴です。
新設される環境デザイン創生学科で学んだ学生の就職先は、自治体のSDGs関係の部署やコンサルティングを担う部署でなどが想定されます。SDGsに興味がある学生によって、学びがより深められる学科になるのではと感じています。
「好き × 課題解決」で起業へチャレンジ
-亀田様は金沢工業大学での学びや平本教授との出会いがきっかけで起業につながったのでしょうか。
株式会社LODU 亀田様:はい、そうですね。今振り返ると、やはり平本教授や大学のサポートがあったからこそ、現在の私があるのだと感じます。
ゲーム開発やクラウドファンディングの経験を通じて、小さな成功を積み重ねる環境が整っていたことや、実践的な活動が多かったことが、今の私につながっていると思います。
高校生までは、大学は座学が中心と考えていましたが、グループワークを中心としたプロジェクトデザインという授業や、課外活動等、学んだことを社会実装していくような活動が多かったので、私が想像していた以上に充実した大学生活でした。
▼ 詳しくはこちら KITの特色ある教育 プロジェクトデザイン教育 (kanazawa-it.ac.jp)
楽しさを感じ始めると、学びも一層楽しくなり、授業内容もSDGsに関連づけることで、さらに楽しくなりました。大学生活で経験した成功体験は、今の私にとって非常に重要な経験です。
大学院在学中に仲間とともに起業し、今は大学の研究員と両立して取り組みを進めていますが、ゲームを製品化したときは関わった全員で喜びを分かちあいましたし、社外の方にゲームを紹介し評価された瞬間は何にも変え難い喜びを感じました。
今はまだゲームに特化した会社ですが、私たちのコンセプトは「さまざまな方々の『好き』に関わり、行動変容や意識変容を促す」ことです。そのため、平本教授から学んだ「自分の好き×課題解決」の理念を基に、SDGsに絡んだ事業を展開していきたいと思っています。「自分の好き × 課題解決」の連鎖でワクワクがつながり、より大きなインパクトを与えることを目指しています。
繰り返しになりますが、このような意識や起業につながったのも金沢工業大学に入学したおかげであり、平本教授の支援があったからこそ、自分の可能性を引き出し、「自分のしたいことをしていいんだ」と考えられるようになりました。
SDGsなどの社会的課題に取り組むことで、自分のやりたいことが実現できると同時に、周囲の応援や評価にもつながるというのが、”金沢工業大学での学び”です。
このような流れこそが、持続可能な循環を生むのだと感じています。
学生たちへのメッセージ

-貴学を目指す学生たちへメッセージをお願いします。
SDGs推進センター 薮内様:今は高校でもSDGsについて学ぶ機会が増えているかと思います。そのため、大学への進学を機にSDGsに関する学びを深めたいと考える方もいると思います。
本学では、国連とともに進めている活動もあり、グローバルな活動にも積極的に取り組んでいます。特に、SDGsはグローバルの視点でも活躍できる分野でもありますので、ぜひ本学に興味・関心を持ってくださると嬉しいです。
株式会社LODU 亀田様:私は金沢工業大学の卒業生であり、大学院にも進んだ経験もあります。その経験からお伝えしたいことは、SDGs推進センター自体もですし学科での学びとしてもなのですが、理論的な知識や専門的な技術を学べる環境が整っていると感じています。
特にSDGs推進センターが設置されていることによって、学生プロジェクトと通じて、より実践的な取り組みにつながる環境があります。例えば、大学が位置する地方自治体においては、地域資源を活用しながらじっくりと関わる経験ができる点が大きな強みです。
このように、学生のうちから社会実装に取り組めることは、金沢工業大学の特徴の一つです。社会に貢献したい方や、実際に社会を変えていきたい方と一緒に取り組んでいけたらと思っています。
また、来年度には新たな学科も新設され、さらにSDGsに関する学びが深められる環境が整います。もしSDGsに対して少しでも興味や関心がある方は、大学での学びだけでなく、SDGs推進センターでの活動もかけがえのない財産になると思います。ぜひ一緒にゲームを作ったり活動していきたいですね。
