
SDGs 大学プロジェクト × Osaka Metropolitan Univ.
目次
大阪公立大学の紹介


大阪公立大学は、大阪市立大学と大阪府立大学の統合により2022年4月に誕生しました。
大阪府と大阪市が設立団体となり発足した公立大学法人大阪が運営するこの大学は、地域社会との関わりを重視しつつ、グローバルな視点を持った教育・研究に力を入れています。
「総合知で、超えていく大学。」をキャッチフレーズに、1学域11学部、15大学院研究科を擁する総合大学として、複雑な社会課題の解決に向けて、個々の専門知を深めつつ他領域を融合した「総合知」の育成を重視しています。


大阪市立大学と大阪府立大学はともに約140年の歴史を持つ公立大学で、大阪市立大学は1880年に発足した大阪商業講習所を源流とし、大阪の経済発展に対応した人材を育てるために設立されました。一方、大阪府立大学は1883年に発足した獣医学講習所を源流とし、2005年4月に大阪府立大学(旧)、大阪女子大学および大阪府立看護大学の3大学が統合・再編され、工学、農学、生命環境科学などの理系分野に強みを持つ大学でした。
両大学とも、医療、工学、環境科学などの分野で特に卓越した研究を行ってきた大学ですが、統合後はその強みをさらに伸ばし、異分野を融合した新たな学問の創造と多様な人材の育成を目指しています。
特に現代システム科学域では、学問分野の領域を超えた学びにより、複雑化する現代の社会問題に立ち向かい、サステイナブル(持続可能)な社会の実現に貢献できる人材の育成を目指しています。
大学院を含めた学生数は約16,000人で、5つのキャンパスと2つのサテライトを有し、公立大学としては日本最大の規模です。2025年には新たに森之宮キャンパスの開設が予定されています。今後、さらなる発展が期待されている総合大学の1つです。
環境部エコロ助では、「恋と環境にやさしく」をテーマに活動

2001年に設立された環境部エコロ助(以下、エコロ助)は、マスコットキャラクターであるカッパの「エコロ助くん」とともに「恋と環境にやさしく」をテーマに活動を展開しています。
もともとはサークル活動として始まったエコロ助ですが、現在は正式な部活動として運営されています。部員数も年々増加しており、大阪公立大学の学生の間で環境への意識の高まりが感じられます。
エコロ助では、以下の3つを活動理念としています。
- できること・気付いたことから、楽しくエコ活動
- 人の心を通して環境問題を考える
- エコロ助のことを思い、それぞれの視点からデザインする
これらの活動理念からも、環境に対するだけでなく、人や社会に対する「やさしさ」を感じられる雰囲気が、エコロ助の大きな特徴です。
今回は、エコロ助の活動内容について、副代表の鉄田さんと小川さんにお話を伺いました。
環境部エコロ助の主な活動内容
-エコロ助はどのような体制で活動されていますか。人数構成や活動頻度についても教えてください。
鉄田副代表:エコロ助には、通年で活動する班として「農業班」と「RPC(Rerepack & Paper Collectors)班」があります。さらに「企画局」という部署があり、これらの班活動以外のプロジェクトは企画局の傘下で活動しています。今年度実施したものとして「りちゃいくるプロジェクト」や「環境教育プロジェクト」などもあり、全体的に柔軟な組織構造を持っています。
部員は基本的に農業班かRPC班のどちらかに所属し、3年間その班で活動を続けます。ただし、各班の班長は同じ人が続けてしまう傾向にあるため、企画局が立ち上げるプロジェクトを通じて、他のメンバーもリーダー経験を積めるよう工夫しています。企画については、部員からの持ち込みも歓迎しています。部員が自ら興味を持ったテーマや実施してみたい活動を自由に企画・提案できる環境を整えています。
今年は新たに1回生が入部し、部員は約120名に増えました。部員は基本的に農業班かRPC班のどちらかに所属しますが、複数の班を兼任している部員もいます。それぞれの班には約70名のメンバーが所属しており、無理のない範囲で一人あたり週1〜2回のシフト制で活動しています。
また、企画局の下で活動したプロジェクトには、りちゃいくるプロジェクトや環境教育プロジェクトがあります。プロジェクトごとにメンバー数は異なります。例えば、りちゃいくるプロジェクトは自転車のリサイクルを行うプロジェクトで、力仕事が多いことから十数名のメンバーで活動しています。
一方、環境教育プロジェクトは、子供たちへの環境教育を行うプロジェクトで、企画は4〜5名で進め、イベント当日は他のメンバーの協力を得て開催しています。

-主な活動である農業班とRPC班について教えてください。
鉄田副代表:農業班は、堺市にある中百舌鳥キャンパスの敷地内で、週3~4回の頻度で水やりや作物の栽培を行っています。毎年育てる作物は異なり、栽培内容はその年の班長が主体となって決めています。野菜だけでなく、花も育てており、環境部として農薬を使わない有機農業にこだわっています。有機農業に精通している顧問の先生の指導のもと、環境に配慮した農法を実践しています。
しかし、農薬を使わないため、雑草や害虫の管理が非常に大変です。特に水やり作業だけでも相当な時間と体力を必要とすることを実感しています。それでも、収穫した作物を班員全員で分け合い、自宅に持ち帰って食べる際には、達成感と大きな喜びを感じます。
一方、RPC班は、お弁当の空き容器、古着、使い捨てコンタクトレンズの空き容器などの回収活動を担当しています。お弁当の空き容器はリサイクル資源として収集し、古着は杉本キャンパスにあるOMU Fashion Swapさんに送っています。そこで再販売され、新たな形で活用されています。
使い捨てコンタクトレンズの空き容器の回収は、大阪市にある粧美堂さんからの依頼で始めました。集めた空き容器は粧美堂さんに送られ、リサイクル素材として再利用されています。先日、粧美堂さんからはお礼として、リサイクルされたコンタクト保存用ケースを500個ほどいただきました。
-企画局の活動内容について教えていただけますか。
鉄田副代表:企画局は、持ち込まれた企画や発案されたプロジェクトに対し、リーダーを任命したり、メンバーを募集することで、新たなプロジェクトを立ち上げる役割を担っています。新たに企画されたプロジェクトでは、1回生や2回生にリーダーを任命し、彼らにリーダー経験を積んでもらうことを目的としています。
しかし、リーダー経験の浅い1回生や2回生がリーダーを務める際には、心細い部分に配慮するため、私の代から上回生がリーダーをサポートする体制に変更しました。
-りちゃいくるプロジェクトや環境教育プロジェクトについて教えてください
鉄田副代表:中百舌鳥キャンパスは広大な敷地があり、学生たちは校舎間の移動に自転車をよく利用しています。
しかし、卒業する際に自転車を放置していく学生が多く、その結果として放置自転車が増加する問題が発生しています。まだ使える自転車を廃棄するのはもったいないので、それらを修理してリサイクル販売する「りちゃいくるプロジェクト」が発足しました。
ただ、想像以上に難易度が高く、このプロジェクトは長らく休止していました。しかし昨年、地元のサカイサイクルさんのご協力をいただき、プロジェクトが復活しました。部品のご提供に加え、修理方法についてもご指導を賜り、メンバーは修理技術を習得し、リサイクル販売につなげることができました。
その結果、計5台の自転車を修理し、SNSや口コミを通じてすべて販売することができました。長期間休止していたプロジェクトが復活し、再び自転車のリサイクルを実現できたことは、プロジェクトに携わった全員にとって大きな喜びでした。

また、エコロ助は学内だけでなく、学外でも積極的に活動しています。環境教育プロジェクトでは、子どもたちに環境について学んでもらうことを目的に活動を展開しています。堺市のご協力を得て、近隣のショッピングモールで子どもたちと一緒にエコ工作やエコレンジャーショーを行い、楽しみながら環境問題について理解を深めてもらう機会を提供しました。
私自身も1回生の時に、エコレンジャーの役者として参加しましたが、何より子供たちがとても喜んでくれたことが印象に残っています。
学園祭でのゴミ回収も担当するエコロ助の新たな取り組み

-学内・学内と多くの場所で環境活動に取り組んでいるエコロ助ですが、何か新しい動きはありますか。
小川副代表:私たちは、学園祭で模擬店を出店するだけでなく、学園祭で発生するゴミの回収も担当しています。これまで、ゴミ回収にかかる費用は部費で賄っていましたが、今年からは出店者の方々からゴミ回収費をいただき、その費用をゴミ袋や衛生用品の購入に充てることにしました。
集めた回収費は、消耗品の購入だけでなく、ゴミ回収の効率化を図るための資材の購入にも活用する予定です。例えば、これまで学園祭で使用するゴミ箱として大学の備品を借りていたところを、リサイクル素材で作られた軽量のゴミ容器を購入し、自前のゴミ箱を設置する事などを構想中です。
このように、環境活動の拡充を図りながら、さらに活動を推進していきたいと思っています。
1人では難しい環境へ取り組みも、メンバーとの協力で環境活動の和が広がる
-エコロ助の活動を通して、部員の皆さんにはどのような変化が見られますか。
鉄田副代表:エコロ助に入部する学生の多くは、必ずしも「こういう環境活動をしたい」という明確な意思を持っているわけではありません。仮に「環境活動をしたい」と思っていても、「何から始めればいいのかわからない」「1人では活動しにくい」と感じる人もいるでしょう。
しかし、エコロ助の活動は非常に多岐にわたるため、「入部すればいろいろな活動ができるかもしれない」「自分の経験が広がるのでは」と期待して参加する人や、単純に「雰囲気が良さそうだから入部してみよう」と感じる人も少なくありません。
どのような理由であれ、入部後は、1人では取り組みにくい環境問題も、仲間と協力することで大きな力となり、環境活動の輪が広がっていくことを実感できると思います。これは、年々部員数が増加しているエコロ助ならではの強みだと思います。
部員たちが一番落ち着ける場所。ハートフルな雰囲気のエコロ助
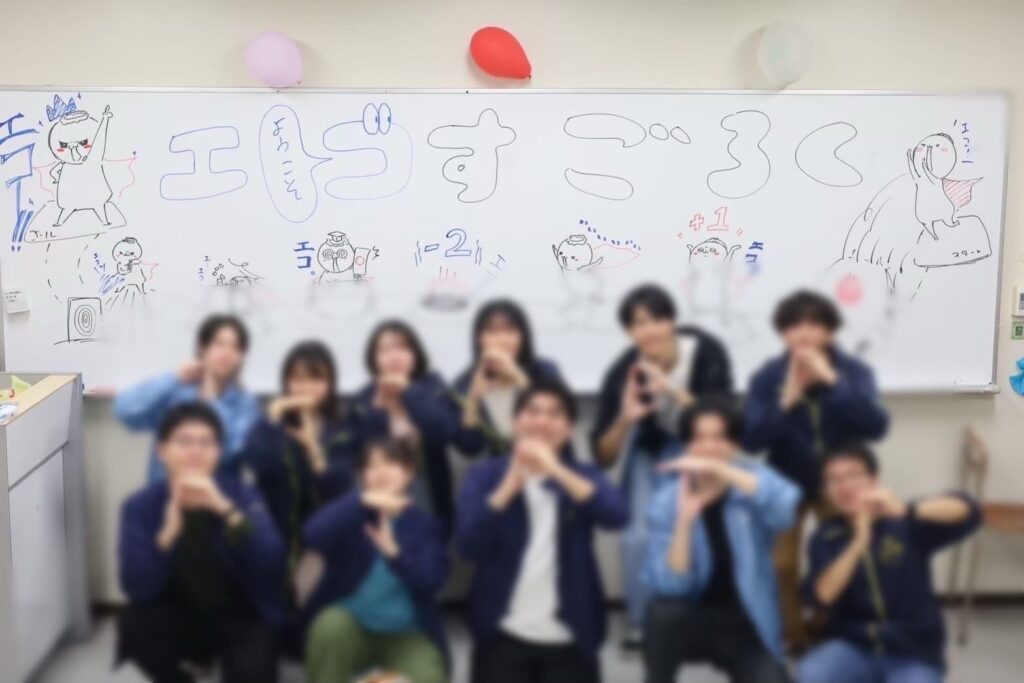
-エコロ助はどのような雰囲気ですか。
小川副代表:エコロ助は、約20年の歴史を持つ団体であり、環境問題に取り組んでいることから、部の雰囲気はいつも緩やかで和気藹々(わきあいあい)とした雰囲気です。実際、多くの部員からも「一番落ち着く場所」と表現されます。多種多様なメンバーが多いこともあって、他の部活とは違った雰囲気があります。
部活動内外での集まりにおいても、エコロ助は上回生と下回生の垣根を感じさせない交流が特徴です。特に、上回生は下回生とのつながりを大切にし、部員同士のつながりを深めるよう意識的に努めているため、上回生が下回生に厳しくするような様子はほとんどありません。
恐らく、環境問題やSDGsに関心を持っている部員が多いことから、多様な価値観を尊重し合える風土が自然と醸成されているのではないでしょうか。
-4年間同じ班で活動する中で、モチベーションを維持しなくてはいけない場面などはありますか。
小川副代表:あまりモチベーションが落ちることはありません。エコロ助の活動は多岐にわたり、常に新しい挑戦があるため、マンネリを感じることがないからです。私が入部してから3年が経過しましたが、3回目の活動においても、毎回新鮮な気持ちで取り組むことができています。
鉄田副代表:私は1回生の時に、環境教育プロジェクトにおいてエコレンジャーの役を担当しました。これまでにない経験でしたし、子どもたちがとても喜んでくれたのが何より嬉しかったです。先輩方から「すごくかっこ良かった」と褒めていただいたことも、大きなやりがいになり、モチベーションが落ちることは今までなかったですね。
人とのつながりや先輩たちの姿があったからこそ、今のエコロ助の姿がここに
-エコロ助の活動を通じて、部員の中ではどのような意識が醸成されていきますか。
小川副代表:「環境部」と聞くと、硬い印象を持たれるかもしれませんが、実際は子どもたちと関わるイベントや地域おこしの活動など、親しみやすい雰囲気が特徴です。新入生歓迎会でも、和やかな雰囲気に惹かれて入部する学生が多いと感じています。
新しく入部したメンバーは、環境系のイベントやボランティア活動を通じて、多くの方々との交流の機会を得ることができます。同様の活動を行っている団体や企業、さらには堺市や大阪府といった行政機関との連携もあり、様々な気づきや学びを得る場面が非常に多いです。
私自身も活動を通じて多くを学んできましたし、後輩たちもその実感を持っていると思います。この部活の意義は、環境問題を「自分事」として捉えられるようになることにあります。私自身も、ある程度環境問題について「知っている」と思っていたものの、実は知らない側面があったことに気づかされ、もっと学びを深める必要があると感じた経験があります。
様々な方との対話を通じて、「面白そう」と感じるアイデアや、自分では思いつかなかった発想に触れる機会も多く、エコロ助はとても刺激的な部活だと思います。
鉄田副代表:私自身は、特に「環境活動をしたい」という明確な理由があって入部したわけではありません。しかし、先輩方の熱意や、地域活動への積極的な姿勢に触れるうちに、環境活動が非常にやりがいのあるものだと気づきました。
現在、3回生となり、私も先輩方の背中を追うように様々な企画に参加しています。エコロ助は、歴代の先輩方の活動の思いが後輩たちに受け継がれ、共に活動していくという、継承の力がある部活だと感じています。
今後の展望
-エコロ助の今後の展望について教えてください。
小川副代表:将来的には、私たち環境部エコロ助が主体となり、地域ネットワークの形成を進めていきたいと考えています。
大学生という世代は学生と社会人の中間に位置するため、私たちがハブとなり、さまざまな方たちとつながりを持つことができればと考えています。そして、エコロ助の活動拠点である堺市をさらに盛り上げていければと思っています。
そのために、「関わる人を増やす」「関わった人と継続して関わっていく」「エコロ助の存在を広めていく」という3つの目標を掲げて、これからも取り組んでいきたいと思っています。
環境部エコロ助への活動に関心がある学生たちにメッセージ

-エコロ助への関心を持つ学生たちも多いと思います。最後に関心がある学生たちにメッセージをお願いします。
小川副代表:私たち環境部エコロ助は、環境問題を身近に感じてもらえるよう、できることや気づいたことを自由な視点で楽しみながら取り組んでいます。上回生は学内外で様々な方々と連携しながら活動を企画しており、1人ではできないことや思いもよらない発想に出会えるのが、この部活の魅力です。楽しく、かつ真面目に活動する部活は他にあまり見られないと思います。
大学生にはぜひ、私たちの部活に入ってほしいと考えています。環境部エコロ助は、部活動という形をとっていますが、サークルと部活の中間のような存在です。大学からの補助金を受けて活動しているため、責任も伴いますが、それに見合う成果を求められることで、より充実した活動が実現できます。
創立から約20年にわたって、私たちは環境問題に真剣に向き合ってきました。その結果、大学からの信頼も得ており、産学官連携として行政や企業とも協力できる環境にあることに感謝しています。環境問題は1人で解決するのは難しいかもしれませんが、仲間と協力することで大きな成果を生み出すことができます。
この記事を読んで、少しでも環境部エコロ助に興味を持っていただけたら、どんな形でも構いませんので、一緒に活動してみませんか。皆さんの参加をいつでもお待ちしています。
