
新社会人にオススメの本:愛知学院大学の青木均先生が選ぶ
LIVIKAが新たに始める新社会人向けコンテンツでは、大学の教員が厳選したおすすめの本を紹介し、読書の機会と成長の機会を皆さんに提供します。このコンテンツは、通常あまり触れることのないジャンルの本に挑戦したい方に最適です。大学の教員がどのような本をおすすめするのか、さらには教員自身が影響を受けた本についても取り上げていく予定ですので、ぜひお見逃しなく!
記念すべき第1弾は、愛知学院大学の青木均教授にお願いしました!
目次
青木均先生のプロフィール
研究テーマ
小売業態の国際移転に関する研究を行っています。具体的には、スーパーマーケットやコンビニエンスストアが海外からもたらされ、それがどのように日本において発展したのかを研究しています。
先生がオススメする新社会人向けの著書は何ですか?
小売マーケティング・ハンドブック
【 青木均先生からのコメント 】特に流通業界(小売業のほか、卸売業など)や製造業の方に読んでほしい本です。小売業者が果たす社会的役割から、消費者の購買行動、店舗開発、プロモーションなど、小売マーケティングの基本を分かりやすく解説しています。この本は、販売士検定試験や中小企業診断士試験など、小売関連資格の受験勉強にも役立つ参考書です。※ 2024年4月に改訂版出版決定!
新社会人の方に向けて、オススメする書籍はありますか?
日本語の〈書き〉方
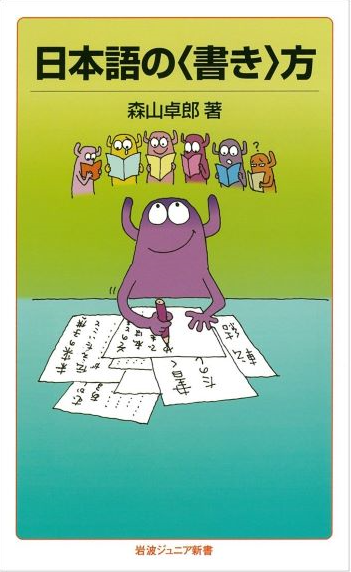
【青木均先生からのコメント】論理的思考を身につけるためには、日本語の文法に関する書籍を読むことがおすすめです。大学での教育では、論理的思考力を養うことが主な目的の一つとされています。この能力は、社会人として成功する上でもますます重要になっています。
しかし、私が学生たちを見ていて感じるのは、日本語の文法に不十分な人が多いということです。たとえば、主語と述語の一致や副詞の使い方、助詞の性質、接続詞の使い方などについて、多くの学生が十分な理解を持っていないようです。これらは学校で習うことがありますが、実際に練習を積んでいない人が多いためです。この問題は、学生のレポートを読む際にも感じられます。文章の主語と述語が一致しない文章が多く見られるため、卒業論文を書く際にも問題が生じることがあります。
したがって、私は新入社員の方々に、論理的思考を身につけるために、日本語の文法に関する書籍を読むことをおすすめします。
日本人のための日本語文法入門
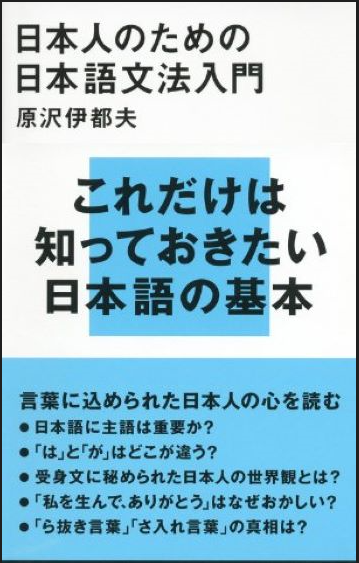
【 青木均先生からのコメント 】時制には、過去や現在、進行形など様々な種類があり、英語の読み書きであれば意識すると思います。しかし、日本語においては(当たり前すぎて)時制についてあまり意識することがないかもしれません。しかし、日本語にも時制に関する法則が存在することが、この本で書かれています。改めてそのことを知り、自分自身も不足している部分を感じました。
「具体⇄抽象」トレーニング 思考力が飛躍的にアップする29問
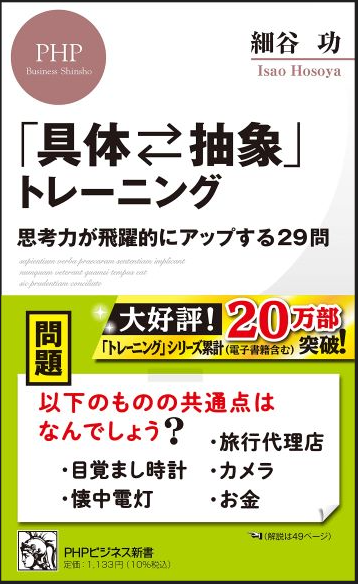
【 青木均先生からのコメント 】学生や卒業した社会人と対話する中で、私が感じたことは 頭の良い人たちはどのようにして考えているのかということでした。私の意見としては、頭の良い人たちは、抽象的な概念と具体的な事象をうまく結びつけることができると思います。
具体的な事象が複数ある場合でも、頭の良い人たちは整理し、簡潔にまとめることができます。また、抽象的な概念を説明する際には、学問的な専門用語などを使っても、世の中の具体的な出来事と結びつけて説明できます。このような能力を持つ人は、頭が良いと言えるでしょう。さらに、彼らは説得力があります。
私は、このような能力を持つ人たちのことを考えながら、具体的な事象と抽象的な概念を行ったり来たりしながら思考できる本があるかどうか探していました。大学生の時から当然、徹底的にトレーニングすべきだったと思います。社会人になってからも、プレゼンを上手に行うためや、取引先との交渉をうまく行うためにも必要なスキルだと感じ、この本をおすすめします。
RANGE(レンジ)知識の「幅」が最強の武器になる
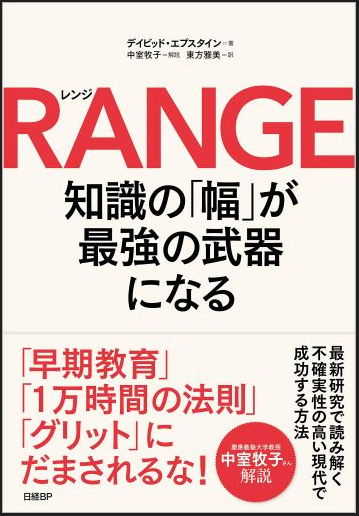
【 青木均先生からのコメント 】現代では、専門知識を蓄え、専門特化することが重要だと言われています。つまり、スペシャリストになることが求められます。実際、私たちの大学でも、学生たちに会計学を学び、将来的に会計のスペシャリストになるようにしたり、マーケティングを学び、マーケティングスペシャリストになるように教育しています。
しかし、私はスペシャリストになることも重要ですが、同時に広範な知識を持ち、柔軟に対応できる人であることも重要だと思います。ジェネラリストとスペシャリスト、どちらが良いのかということは難しい問題であり、最終的には価値観によると思われます。
マーケティングの専門家であっても、マーケティングの知識だけでなく、会計の知識や経済学の知識が必要であり、文学や絵画、歴史などの知識も持っていることが望ましいです。私たちがする仕事を真剣に行うためには、幅広い知識が必要だと思います。
また、他の分野から解決策を借りる必要がある場合、解決策を任せることができる人材を理解する必要があります。教育としては、スペシャリストを必要とする場合に備えた専門教育が必要であることには間違いありません。ただし、幅広い知識も必要だと感じます。
教養教育に関しては、最近は減少傾向にあります。昔は文部科学省の決定により、教養教育に存在感があったのですが、現在は多くの大学で教養教育が縮小されています。
私は、教養教育が重要だと考えます。教養教育は、知識や技能だけでなく、人間性や社会性を養うことができます。私たちが生きていく上で必要なのは、単に専門知識だけではありません。社会や環境が変化する中で、柔軟な思考力や判断力を養うためにも、教養教育は必要不可欠だと思います。
一方で、スペシャリストとジェネラリストのどちらが良いかという問いには、明確な答えはないと思います。人によって能力や価値観が異なるため、それに合わせたキャリア形成が必要になってくると思います。スペシャリストになることも重要ですが、広範な知識を持っていることも必要であり、その両方を兼ね備えた人材が求められる時代になっています。
読書をする際のコツやアドバイスを教えてください!
【 青木均先生からのコメント 】私たち大学教員は、本を味わうよりも情報を得るためのツールとして使います。そのため、参考になるかどうかがわからないこともあります。まずは目次を読んで、何が書かれているかを把握し、目次に対応した部分を探して必要な部分だけを読みます。読んでわからなければ最初から読み直すこともありますが、たとえば200ページの本で20ページだけ読んで十分だと思えばそれで済ませます。
先生方が多数の本を読んでいるように見えるかもしれませんが、実際には目次や一部のページだけ読んでいることが多いです。ただ、本棚の中の本の場所やタイトルは記憶しているため、必要なときにすぐに探すことができます。
私たちは、目次と最後の索引に重きを置いています。目次を読んで最初から読んでいく形で読書を進めることで、多くの本を効率的に読むことができます。一方、同じ本を複数回読むこともあります。たとえば、基礎から学ぶと書いてある入門書は何度も読むことがあります。最初に読んで知識を得た後、時間が経ってから改めて読むことで、より深い理解や新たな気づきが得られることがあります。
まとめ
知的好奇心が低いと、時代の変化についていけなくなるおそれがあります。
最近では急速な変化と技術の進歩が進んでおり、新しい知識やスキルを習得することがますます重要となっています。本は、私たちの知識を広げたり、洞察を得るための貴重なツールです。さまざまなジャンルやテーマの本を読むことで、私たちは世界の動向や新しいアイデアに触れる機会を得ることができます。
科学、技術、社会、文化など、多岐にわたる本を読むことで、時代の変化に敏感になり、情報を正しく理解する力を身につけることができます。さらに、本を通じて他の人の経験や知識に触れることで、自分の視野を広げることもできます。
今回のインタビューを通じて、「小売マーケティング・ハンドブック」といった本との出会いや、日本語の文法への危機感、広範な知識を持つことの重要性など、さまざまな学びを得ることができました。
絶えず学び続けて成長することで、私たちは自分らしい未来を築くことができます。そのため、知的好奇心を高め、さまざまな本を読むことを、このコラムを通じて推奨していきたいと考えています。

