
社会貢献活動 × Fukuoka Jo Gakuin Nursing Univ.-Part 7-
目次
福岡女学院看護大学の紹介

福岡女学院看護大学は、明治以来138年の女子教育の歴史のある福岡女学院の姉妹校として、2008年に福岡県古賀市に開校した看護大学です。
教育の特徴は、「あなた方がして欲しいように、他の人たちにもそのようにしなさい」というキリストの教えを基に、人間の尊厳、倫理観を備え、ヒューマンケアリングを実践できる人材の育成により社会貢献をすることを教育理念として掲げています。
ヒューマンケアリング教育とは、 「他の人の看護を通して、看護される側も看護する側も 共に人として成長する」という考えに基づいています。
また、大学は、その使命でもある「教育」、「研究」、「社会貢献」に取り組む際に、「社会の良き道具として成長しよう」をモットーにし、教職員・学生が一丸となって取り組んでいます。
本学の教育研究活動の特徴は、以下のとおりです。
- キリスト教の精神に基づき、博愛の心をもった看護職者を育成しています。
- 「ヒューマンケアリング」を実践し続ける看護職者として、組織的持続的に看護活動の発展普及に努めています。
- ICT教材(ミッションタウン)により、いつでも・どこでも・どのような場面を想定した最先端の看護学が学べるように仮装コミュニティ教材を開発し、あらゆる場面に対応できる看護大学を目指しています。
- 我が国最大規模のシミュレーション教育センターで、コンピューター制御したモデル人形を対象にして1年次から病院実習のような看護体験学習ができる、シミュレーション教育をリードする看護大学です。
- 様々な資格を取ることができます。一次救急救命の国際資格や、多言語コースではTOPEC看護英語試験等の受験等も可能で、グローバルな視野から看護探求を目指すことができます。
- 楽しい学生生活を送ることができます。200本のオリーブが育つオリーブの森の看護大学で、オリーブ祭、収穫祭、バーベキューパーティーといった本学独自の学内行事が楽しめます。
- 2023年、大学院がスタートしました。教員や病院の教育指導者となるための新たな扉が開きました。
- 開学以来就職率は100%です。
宗教部ボランティア活動について
福岡女学院看護大学の学生たちは、サークル活動や学友会活動などを通してさまざまなボランティア活動を行っています。そのうち宗教部委員会では主にホームレス支援活動のボランティアを紹介しており、多くの学生が参加しています。
具体的には、宗教主事(金田)から、福岡市で活動しているホームレス支援NPO「福岡おにぎりの会」が主催するボランティア活動を紹介しています。2010年頃から現在まで、毎年少なくとも20名ほどの参加があるので、コロナ禍中の中断を含めても、のべ参加者はすでに200名を越えていると思います。
福岡おにぎりの会


「福岡おにぎりの会」は1996年以来、市内の路上生活者・生活困窮者の支援活動を行っている市民ボランティア団体です。2004年にNPO法人として福岡市から認定を受け、2021年には認定NPO法人となっています。2009年のリーマンショック時には市内に約600名の野宿者の方々がおられたそうですが、現在でも約150名の方がつねに野宿生活を余儀なくされ、その数はなかなか減少しない状況が続いているそうです。
最近では新型コロナウイルスの影響で失業をした若い方々も少なくないようです。今の世の中、そうした状況に置かれている人たちが実際に存在する、という事実に向き合う経験は、将来看護師や保健師として働く希望をもっている本学学生にとって、とても貴重な学びの場になっています。
福岡おにぎりの会の活動内容

「福岡おにぎりの会」が行っている事業は、下記の7つです。
- 炊き出しなどの「基礎的支援事業」
- 生活保護・年金や健康相談などの「相談支援事業」
- 襲撃などに対する「人権支援事業」
- 病院との連絡を行う「入院支援事業」
- 住居紹介などを行う「自立支援事業」
- チラシや会報などによる「情報提供事業」
- 行政との協力を行う「行政交渉及び行政との協働事業」
学生たちが主に参加させてもらっているのは、このうち「基礎的支援事業」として金曜日夜に行われている炊き出し・夜回りです。12月~3月までのいわゆる越冬期は毎週金曜に、それ以外の時期は第一、第三金曜日に行われています。
学生への募集案内は宗教部からのメール配信で行っています。選択科目「ボランティア論」で紹介されて来る学生もいます。社会連携推進センターが発足してからは学務課学生係に参加届を提出して参加しています。なお市内各所へ車に分乗して移動する必要があるため、毎回の参加人数は4名までに制限しています。集合場所は事務局のある「美野島司牧センター」が中心で、2~3月のみ「大名町カトリック教会」です。
そこでまず集められた支援物資の仕分け作業を行った後、市内各所のコースに分かれ、現地でおにぎりや豚汁、防寒着などを配りながら、安否を尋ねたり相談に乗ったりします。最近は仕分け作業の前に、初回参加者向けの基礎的な知識と心構えについてのレクチャーをスタッフの方からして頂けるようになり、学生にとってより良い学びの機会になっています。また金曜夜回り以外にも、年3回ほどの季節イベント(雑煮大会・焼肉大会など)を行っており、それに参加する場合もあります。
学生の学び
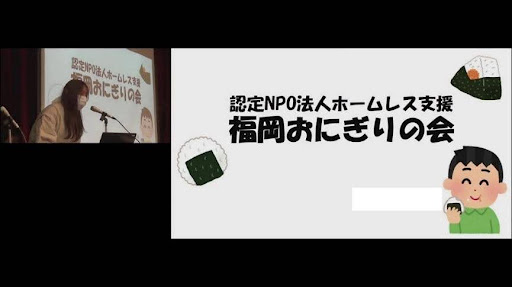
これらのボランティア経験は、その活動の様子をチャペル礼拝の中で紹介して、全ての学生と学びを共有する機会としています。直接に対面したり見聞きした路上生活者の方の生活や健康状態の実態について報告したり、最初は内心持っていた偏見が間違いだったと感じた経験を語ったりしています。
このチャペルを通して参加した学生が経験を他の学生に伝え、また新たな参加者も生まれるという循環が続いています。ただ、夜回りは時間的にも労力的にも負担が大きいため、複数回参加してリピーターや常連となる学生はそれほど多くなく、多くは一回経験者です。それでも学生の普段の生活領域とは異なる場で活動する経験ができることが学生のインセンティブになっているのかも知れません。
なおクリスマス献金の報告にもありましたように、「福岡おにぎりの会」もまた継続的な献金先の1つとして指定されています。
自立支援施設「抱樸館(ほうぼくかん)福岡」

また「福岡おにぎりの会」と関連するボランティアとして、自立支援施設「抱樸館(ほうぼくかん)福岡」における活動があります。「抱樸館福岡」は北九州でホームレス支援を行っているNPO「抱樸(旧北九州ホームレス支援機構)」が社会福祉法人グリーンコープと共に、福岡市東区多の津に設立したホームレス者及び生活困窮者のための自立支援施設で、現在は「福岡おにぎりの会」と連携して自立支援にあたっています。
そこで本学のボランティアサークル「葡萄」の学生たちが、顧問の酒井康江先生の指導のもと、入所者の方々が抱えている健康不安などについて定期的に相談に乗る「健康相談」、そして自立前の方々の居宅生活や自炊生活を支援するための「健康教室」「料理教室」などを行っています。ボランティアサークル「葡萄」の活動紹介の方にも関連記事がありますので、こちらもご覧ください。
「葡萄」紹介記事の内部リンク
これも2011年頃より始まり、コロナ禍が始まるまで継続的に行われていました。部員に配信される情報にもとづいて参加者が募られ、参加学生たちは顧問の酒井康江先生と活動日などを相談し、土曜日など授業のない時を選んで福岡市東区多の津の「抱樸館福岡」を訪れて、これらの活動に参加していました。
健康相談・健康測定会


「健康相談」は保健師の酒井先生と看護学生が入所者の方々のさまざな健康相談に応じるものです。路上生活の長い方はいろいろな健康問題を抱えておられることが多く、それらの健康不安の解消とより良い生活習慣のきっかけになればと行われています。
以前は定期的に、ほぼ月一回のペースで数年に渡って行われていました。一度参加された相談者の方はほとんどがリピーターとなり、また退所して居宅生活に移られた後も引き続き健康相談に来るのを習慣にされる人もいて、大変喜ばれた活動でした。
また抱樸館では毎年、入所者と退所者の方々、スタッフ総出の「きずな祭」というイベントを開催されていますが、そこで「健康測定会」も行っていました。これは看護大学にある骨密度計や体組成計で、現在の体の様子を実際に測定し、その結果に基づいていろいろ具体的な健康アドバイスを行うというもので、これも毎年行列ができる人気企画でした。
またこれからアパートなどの居宅生活に移る入所者の方々のための「健康教室」では食事と栄養、生活習慣病についてのプレゼンテーションを行い、実際に一緒に料理を作ってみんなで頂く「料理教室」というプログラムも毎年春頃に行われていました。これも若い看護学生たちによる楽しく笑いの絶えないイベントとして、入所者の方々に喜ばれていました。
施設の方々も全面的にご協力頂き、良い活動ができていたこれらの活動も、コロナ禍以降はしばらく中断を余儀なくされていました。しかし、2024年からは再び少人数ながら活動が再開されているところです。
おわりに
聖書には、「もし兄弟あるいは姉妹が、着る物もなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなたがたのだれかが彼らに、『安心して行きなさい。温まりなさい。満腹するまで食べなさい』と言うだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら、何の役にたつでしょう」(ヤコブの手紙2:15)とあり、また「世の冨をもちながら、兄弟が必要な物に事欠くのを見て同情しない者があれば、どうして神の愛がそのような者の内にとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく、行いをもって誠実に愛し合おう」という言葉もあります(ヨハネの手紙(Ⅰ)3:17)。
キリスト教主義の看護大学である本学にとって、これらのボランティア活動は付け足しではなく、本質的な活動の1つであるべきだと思っています。学生たちにはチャペル礼拝や授業と共にこうした実際の活動を通して、キリスト教の伝えようとする大切な精神を学んで巣立って行ってほしいと願っています。
