
SDGs 大学プロジェクト × Okinawa Univ.
目次
沖縄大学の紹介

沖縄大学は、実業家の嘉数昇が1956年(昭和31年)の嘉数学園の設立認可(当時の琉球政府)、2年後の沖縄短期大学の開学を経て、1961年に4年制の「沖縄大学」として開学した、那覇市内にキャンパスを有する私立大学です。通称「沖大」と呼ばれています。
沖大は、創立者嘉数昇の「教育の機会均等」の実現への強い思いはもちろん、将来の沖縄の発展を担う若者を生み出したいという沖縄県民の希望により誕生しました。
また、1972年の沖縄の日本復帰時に、同じ私立大学である国際大学(現・沖縄国際大学)との統合の話が持ち上がったことから、沖大は存続の危機に直面し、政治と行政の余波を受けた無認可期間、いわゆる「沖大存続闘争」などの幾多の苦難を、学生と教員、そして地域が一丸になって乗り越えてきた歴史があります。
そんな沖縄の歴史とともに歩んできた沖大ですが、「地域に根ざし、地域に学び、地域と共に生きる、開かれた大学」を使命に、21世紀型の社会として、地球規模でものごとを捉える「グローカル社会(※1)」の視点を持って、他者との対話と協働を通じてより良い社会を創り、日々変動する社会において、生涯学び続ける意志を持ちながら人生を切り拓いていける人間の育成を目指してきました。
そんな沖大では、創立50年の節目に「地域共創・未来共創」を新しい理念とし、さらに、創立60周年には、「OKIDAI VISION 2028 『地域がキャンパス、地域のキャンパス』」を10年後の未来像に掲げて、教育、研究、そして地域貢献に取り組んでいます。
2019年4月には、「食」と「栄養」に関わる管理栄養学科を開設し、3学部5学科となりました。法律・経済・経営という社会基盤を総合的に学んだり、語学を活かした国際的に活躍できるスキルの取得、社会福祉への貢献、健康・スポーツ・福祉の分野で活躍できるプロフェッショナルの育成、未来を担う子どもの教育に関わる分野など、幅広い選択肢の中から学びの場を選ぶことができます。
一方では、国内外の提携大学に、沖大を休学せずに留学ができ、留学先で取得した単位も沖大の卒業単位に加えられる「国内・海外派遣留学制度」も充実させており、この制度の活用によって、沖縄県の外に飛び出して貴重な経験ができることで、将来、社会人として活躍する学生にグローカルな視点を養ってもらう意味でも貴重な体験ができるように取り組んでいます。
沖大で学ぶ学生たちには、「他者との対話と協働を通じてより良い社会を創っていく力」と「日々変動する社会の中で生涯学び続ける意志を持って自ら人生を切り拓いていける力」を身に付けて頂き、そのために沖大・教職員は学生とともに歩んでまいります。
(※1) グローカル社会…「global(地球規模の)」と「local(地域的な)」を合わせた造語で、地域性を考慮しつつ地球規模の視点で物事を考えて行動する社会のこと。
沖大がSDGsを意識したきっかけ
(山代寛学長)沖大が2018年に長期ビジョンとして、「OKIDAI VISION 2028」を掲げる際に、SDGsへの取り組みを明記すべきとの声があがり、これがSDGsという言葉を具体的に意識した始まりとなりました。
ただ、SDGsの内容を掘り下げて確認してみて、沖大のこれまでの取り組みに照らし合わせてみると、以前から沖大でもSDGsの目標達成に資する行動をしていたことにも気付かされ、今後は、よりSDGsに関連する部分を伸ばして行くべきだと考えるようになりました。
同時に、沖大の内外に向けて、今まで沖大でやってきたことが、実はSDGsの目標達成に資する部分であったことを、もっとPRすべきだとも感じています。
玉城先生と沖大との出会い
(山代寛学長)玉城先生とは、昨年那覇市の総合計画審議会に出席した際に出会ったことが1つのきっかけになりました。
私も玉城先生も審議会のメンバー(委員)でありまして、会議の中で玉城委員が、那覇市の総合計画において、SDGsの視点を取り入れた取り組みの重要性、SDGsの大切さを説いた考えを述べられていたことと、行政としての那覇市が、今後SDGsに本格的に取り組むという、具体的な説明もされたことから、私自身、SDGs視点の大切さをこの会議の場で改めて認識するとともに、沖大でもSDGsについて、より具体的に取り入れるべきとの考えに至りました。
そののち、この会議での内容も含め、SDGsについて、学内で議論を重ねる中で、SDGsに関して深い知見をお持ちの玉城さんに沖大で教鞭をとってもらいたいという沖大としての意向が固まり、この意向を玉城さんにお伝えしたところ、快くお引き受け頂きました。
(玉城直美先生)私自身、沖縄の未来につながることをしたいという思いから、大学教員(沖縄キリスト教学院大学准教授)を退職して社会起業家(※2)としての活動を展開しておりました。
その活動の1つとして、SDGsについても注力する中、4年前に沖縄県がSDGsに関して、本格的な取り組みを開始するということが決まり、その沖縄県に対して、専門的な観点から意見や助言をすることを目的とする「沖縄県SDGsアドバイザリーボード会議」も設置されました。
当該会議を構成する委員就任について、沖縄県の方から声をかけて頂き、同時に2年目の会議から現在に至るまで座長を務めさせていただいております。
そのような立場になったこともあり、SDGs目標の達成について、より具体的に取り組む過程で、未来を担う子どもや若者たちへのSDGsの普及がなによりも不可欠であることについて、より強く意識するようになっていきました。
そのような折に、沖大が環境に配慮した学校づくりに取り組み、学生と地域との関係を大切にする「共創」によって地域とともに歩んでいる姿を拝見し、同時にSDGsの目標にも沿っていることに共感していたところ、ちょうど沖大からオファーをもらい、SDGsを講義名に入れて学生たちにSDGsを伝える機会をいただくことになりました。
現在、「国際開発とSDGs」という科目名で、沖大の学生たちに、未来を担う若者がSDGsの視点を持つことの大切さなどを伝えるとともに、沖大のSDGsへの取り組みにも参画させて頂いております。
(※2) 社会企業家…いわゆるベンチャー企業から連想されるような「起業家」と異なり、営利目的ではなく、社会貢献を目的として活動する人々の総称。
「国際開発とSDGs」の授業の内容と、授業を行ううえで意識したこと

(玉城直美先生)これまで、沖大の学生に教えたことがなかったので、まずは学生たちを知るために、学生たちが、SDGsという言葉をどの程度知っているのかを確認するところから始めました。そうしたら、100%の学生がSDGsという言葉を知っておりましたが、SDGsに関して具体的な活動を行った経験は少ないということがわかりました。
さらに、具体的な授業の進め方について、学生たちに、座学が良いか、何かにチャレンジする形でのフィールドワーク(※3)やアクションプログラムが良いかを尋ねてみたところ、何かにチャレンジしてみたいと思っている学生が8割を占める結果となったので、座学とフィールドワーク・アクションプログラムを融合させていく形式をとりました。
まず、SDGsの理論を学ぶに当たって、SDGsの17の目標、全ての理論を1つずつ丁寧に押さえるというよりも、SDGsの視点を持つことで、今までとは少し異なる物事の見え方を養ってほしかったのと、世界中がSDGsの目標達成に向けて取り組む中で、誰もがまだ、明確な答えを持っていないからこそ、未来を担う若者目線で難しい課題についても自分ごととして捉えて、講義の中でみんなで解決策を見出していくようにしてもらいたいとういうことを伝えました。
したがって、講師である私のスタンスは、あくまで学生たちの伴走者であることを伝えて、学生たちに主体性を持ってもらうことを大切にして授業を行いました。
また、学生たちに、SDGsの目標のどの項目に興味があるのかを尋ねてみると、「ジェンダー平等」や「LGBTQ+」(性の多様性)が1番にあがり、その他、貧困問題や、沖縄独自の問題としての交通問題、さらには沖縄の既存の宝物をどう未来に残していくのかなど、学生たちが、身近な問題に興味を持っていたことが分かり、その辺りを中心に授業の中でひとつひとつ取り上げたところ、アンコンシャス・バイアス(※4)やミスコンテストなどの具体的な問題が議論の中心になりました。

ちょうど、2月に沖縄観光コンベンションビューローが、ミスコンテスト休止を発表したこともあり、メディアも注目している内容だったので、5月2日に「沖縄のミスコン休止をSDGsの視点で再提案する」をテーマに公開で講義を行いました。
講義では、沖縄の観光を担うに当たり、若者の意識や視点がどこにあるのか、この問題にSDGsを意識した考え方を取り入れた場合、学生たちからどういう意見や提案があるのかを主眼としたところ、学生たちから素晴らしい提案が多数寄せられました。
この公開講義ののち、沖縄観光コンベンションビューローでは、学生たちから提案のあった意見等を委員会の議題に取り上げてくれて、そのことが学生たちにも伝わり、自分たちの意見が沖縄の観光を担う大人たちに影響を与えられたことに、学生たちはすごく感動し、喜びを感じていました。
その後の講義では、自分たちが暮らす市町村の施策や課題をSDGs視点で取り上げてみることを課題としたところ、それぞれの市町村が抱える問題などについて、SDGs視点での発表ができました。
これらの課題への取り組みを経て、最終的に学生たちそれぞれが解決したいテーマを決めて、同じような課題を掲げている仲間同士が集い、前期15コマの総括として、7月の公開授業で発表する形に持っていきました。
(※3)フィールドワーク…一方的(受動的)に講義を聴くだけの「座学」に対して、実際に地域(フィールド)に出向いて、実践的に学び、理解を深める学習スタイルのこと。
(※4)アンコンシャス・バイアス…人が無意識に持っている思い込みや偏見のこと。
7/25に行われた公開授業の様子

(玉城直美先生)若者と女性の参画はSDGsの中で大きな課題の1つだと認識しています。特に若者はコロナ禍以前から、社会に対して無力感を感じていると思います。そんな中にあって、SDGsの取り組みは、若者のそんな意識を変えてくれるのではと期待しています。
そのような若者・沖大生に対して、「国際開発とSDGs」という講義を行い、5月に「沖縄のミスコン休止をSDGsの視点で再提案する」というテーマを掲げて授業を行ったときには、私が話をし、それを受けて学生同士で議論を交わしながら、新しい視点や考え方を創り出していくような感じでしたが、7月の公開授業では、冒頭から学生たち主体で発表し、議論を展開していくような形式だったので、より活発で面白いものになったと感じております。
学生にとっては、自分たちが発表・発言したものに対して、集まった大人たちからコメントをもらうことで、モチベーションの維持・向上に繋がり、さらにSDGsに取り組みたいという意識が芽生えたのではないかと感じています。
今の学生たちは、特にコロナ禍を経験して、外出もできない、人との接触も制限されるなど、無力感を味わってきましたが、そんな状況でも諦めることなく、真剣に取り組み、今回の講義では、身近に考えられる「性の多様性」から、世界的な大きな問題である「戦争の問題」についてまで色々考え、自分たちの言葉で意見を述べられる姿を目の当たりにし、バイタリティ溢れる学生たちの能力をこれからも伸ばしてあげたいと思っています。
さらに今後は、SDGsをキーワードに、民間と行政、そして学生たちも含めたパートナーシップのもとで発表できるような取り組みにもチャレンジしていきたいと思います。
一方では、そのような学生たちを見て、私たち大人の方がもっと変わる必要があることも再認識させられ、私たち大人も大きな刺激を受けましたので、私自身はもちろん、山代学長をはじめ、沖大の教職員の方々とも連携を図りながらSDGsの取り組みを広めていきたいです。

(山代寛学長)マスコミの方々や沖縄県のSDGs担当者をはじめとした傍聴者がいることで、学生たちには良い刺激となり、素晴らしい発表ができたと感じております。
また、半年間の講義を通して、学生たち全員が参加し、事前によく相談し合って今回の発表に臨んだということが、公開授業の発表を見ていて非常に良く分かりました。
9つの発表の中には、SDGsの目標達成のためにすぐにでも実現可能なものもありましたし、マスコミの方のインタビュー等を受けることで学生たちのやる気の向上にも繋がっているのではと感じています。
そのような様子を見ていると、大学・教職員側も学生たちをバックアップするために、一層の変化が必要ではないかと考えるとともに、より大きな範囲において、私たち大人も含めた社会そのものが変わっていく必要性を感じています。
(兼島徹主幹)公開授業には私も参加させていただきました。今年度の前期15コマ分の総括として、テレビ局や新聞社などマスコミや沖縄県のSDGs担当者、琉球大学の教員、那覇市議もゲスト参加しており、9チームに分かれて、多様なテーマをまとめ、パワーポイントで発表していました。短い準備期間であったにも関わらず、身近な社会課題を自ら見つけ、仲間同士で議論しながら学ぶとともに、地域に足を運んで調査やインタビューを行って、その結果を非常に良くまとめて発表できていたと思います。
そのことは、マスコミを始め、ゲスト参加された皆さんから、「素晴らしかった」という講評を頂いたことでも分かりました。
学生たち自身にとっても、本当に良い経験ができたのではないかと感じています。
さらに、この講義を通じて、学生たちは、主体的に学ぶことに喜びを感じるとともに、大きく成長できたのではないかとも思っております。
一方で、今回の玉城先生の公開授業を通して、本学が目指す授業の在り方の1つがここにあるのだということを強く意識させられました。
半年という短い期間の講義と、発表のための準備時間が少なかったにも関わらず、学生たちが非常に高いレベルで発表が行えたのは、学生たちの頑張りがあったことはいうまでもありませんが、主体性を持たせた授業を展開された、玉城先生の手腕のおかげだと感じています。
大学全体でのSDGsの取り組みにおける現状
(山代寛学長)繰り返しになりますが、沖大は、以前からSDGsに繋がるような取り組みを行っていたという認識にあります。
本学は、「環境と平和の大学」といわれ、「地域共創・未来共創」を大学の理念として様々な取り組みを行ってきました。
そのような中で、今年度は玉城先生をお招きして、SDGsの目的に沿った授業を行って頂き、学生たちはもとより、教職員も刺激になって非常に良い効果が生まれてきています。
私自身も、SDGsの内容と、これまで沖大が手掛けてきたことを照らし合わせるために、講義の1コマを使い、沖大の理念とSDGsの関連について、兼島さんに講義をしてもらったところ、学生たちから、「沖大が、今までもSDGsに関する取り組みをこんなに多く行っていたことを初めて知った」「もっとSDGsについて何かしてみたい」というような声も多く聞こえてきましたので、学生たちのこの声を無駄にしない取り組みを行ってまいりたいと思います。
(兼島徹主幹)沖大は、2019年度から2028年度までの10年間の長期ビジョンとして、「OKIDAI VISION 2028」を掲げ、「地域共創・未来共創」という理念の実現を目指していますが、実際、教職員は目の前にいる学生たちが抱えている諸課題の解決、対応に時間を割かれており、長期ビジョン達成のために、腰を据えて取り組むことがなかなか厳しいように感じています。
そのような現状にある中でも、この長期ビジョンを達成するために、前期5年、後期5年の中期計画を策定し、さらに年次計画(1年)で実効性を担保するような形にして取り組んでおります。
今年度が、ちょうど前期に当たる「第五次中期計画」の最終年度となり、来年度から「第六次中期計画」に移っていくわけですが、長期ビジョンに描く沖大の将来像を示す、「地域がキャンパス、地域のキャンパス」、すなわち、学生が大学の外に出て地域を歩いて考え、一方で、地域の皆さんには、沖大を生涯学習の場として訪れていただくことで、共創力が育まれるという将来像の実現のためにもSDGsの目標達成に取り組むことは非常に意義あることだと考えています。
一方で、学生たちには、SDGsについてより深く考えることで、SDGsの目標にある全17項目、それぞれに関連性があることにも気付いてもらい、SDGsについて、より深く探求していくことで視野が広がっていけばと思います。
そのため、2024年度からの第六次中期計画を実践していくうえで、SDGsともひも付けることを常に意識しながら、学生たちとも情報共有を図り、最終的な長期ビジョンの実現に向けて取り組みたいと存じます。
今後の展望
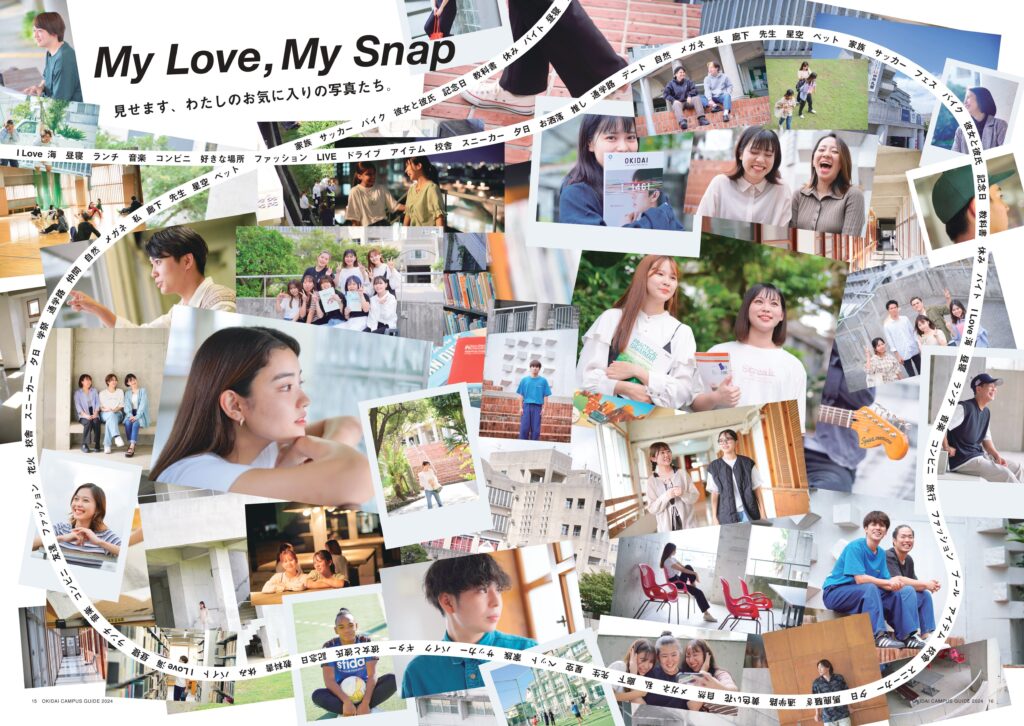
(山代寛学長)小・中・高校とSDGsを学んだ子どもが本学に入学してくることを念頭に、沖大の入試改革を行っていくとともに、教員自身がSDGsの意識を高め、浸透させていくことも必要であり、大学執行部側にその責務があるものだと思っています。
一方、学生たちの学びにおいては、やる気になった学生たちを支えていく仕組みづくりも必要だとの認識にあります。
(玉城直美先生)私の今の立場での思いですが、SDGsの主流化に加えて、若者の主流化を後押ししていきたいと思っております。
また、沖大との繋がりを持たせていただきましたので、この繋がりを大切にして育みながら、沖大のSDGsの取り組みを広めていくのも私の役割の1つだと考えています。
(兼島徹主幹)沖大が地域とともに社会の課題を解決することは、沖大創立からずっと続けてきていたことですので、あえてSDGsと打ち出さなくてもという部分もありました。しかしながら、今回の講義を通してSDGsには世界を変える力があることを実感したので、学生たちにより一層関心を持ってもらうことに着目して、本学の目指す地域共創の実現を加速させるために、SDGsという考え方の活用方法を探っていけたらと思っています。
